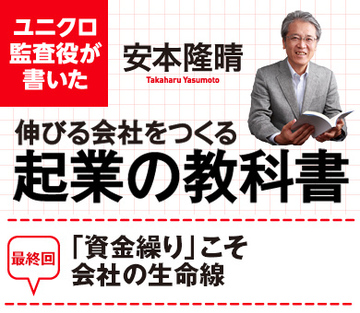鬼頭からの忠告
「鬼頭くん、売上構成を話してあげて」
あー、ちょっと待ってください、と言って鬼頭は自分の席からファイルを持って戻ってきた。
「レディース衣料が28%、キッズ、これは幼稚園児から小学校低学年までの女の子の衣料なんですが、今は32%。残りが靴とか鞄とかの雑貨で、まあ3分の1ずつですね。今はこの雑貨部門が、一番伸びがいいです」 と言ってから、鬼頭は初めて高山の目を見た。
「レディース衣料部門は、本当はうちが一番得意なのだけど、競合も多いところだから…」
「このブランドは、男の子の衣料はやっていないんですか?」
高山は聞いたが、夏希常務は何も反応せず、同じ笑顔のままだった。
「やらない」鬼頭から返ってきた答えは、そっけなかった。
「どうしてやらないんですか?」高山が尋ねた。
「高山くん、うちはレディースファッションのブランドなのよ」
だからなんだっていうんだ、と高山は思った。
生まれる子どもは男女、ほぼ同じ比率じゃないか。お母さんが買いに来る店ならば、男子の衣料があっても別にいいだろうに…、口には出さずとも、高山の表情には感じている不愉快さがそのまま表われていた。
「高山くんには、まずは売り場に出てもらわなきゃね」
「あー、それがいいでしょうね。何も知らないんだから。売り場にいるのが、一番いろんなことがわかりますからね」
なんだ、こいつは、高山は思ったが、夏希常務は鬼頭の言葉をそのまま流して話を続けた。
「そうねえ、いつも中途入社の社員に研修に行ってもらう旗艦店があるの。高山くんもそこがいいわ。鬼頭くん、千葉ショッピングセンター店に連絡して、明日から高山くんが行くって伝えてちょうだい」
「わかりました。連絡しておきます」
鬼頭はファイルを片付けながら低い声で言った。
「あのさ、何か家にあるカジュアルな格好をしていったほうがいいよ。そのスーツ姿で店頭に立つと、店に迷惑だからさ」
このぉ、腹の中では思いながらも、高山はそれを口には出さずに、軽く黙礼だけをした。
「じゃあ、せっかくだから私からブランドの子たちに紹介しましょうね」
夏希常務に連れられて高山は、『ハニーディップ』ブランドのフロアの主要メンバーにあいさつをして回った。
大胆な作り笑顔を返す社員、不愛想な社員、様々だったが、高山は終始、空気の薄さのようなよそよそしさを感じた。とりあえず高山はこれまで接客業で培った愛想の良さで、あいさつをした。
夏希常務は本社に戻り、高山は鬼頭から、事務所の配置、組織、役割など、通り一遍の説明を受けて、その日は終わった。
「疲れたなあ」
夕方、早い時間にアパートに帰った高山は、近くのスーパーマーケットで買ってきた弁当をテーブルの上に置き、スーツの上着も脱がずにベッドに転がった。
空気を読まない高山といえども、初めての職場は、本人が意識している以上に頭のアンテナが働いていたようで、家に着いた途端、一挙に疲れが襲ってきた。
「ガールフレンドでも身近にいれば、こんな時に少しは癒されるのかね…」
手元のリモコンでテレビをつけると、すぐにうとうとし始め、目をつぶった途端に高山は意識を失った。気が付いた時には、窓の外はすでに明るくなっていた。