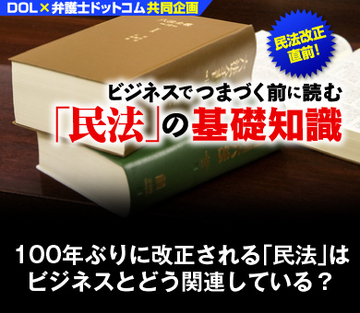120年ぶり!
民法大改正の深層
日清戦争が終結した翌年の明治29(1896)年に産声を上げた民法。それから120年の時を経て、契約ルールを定めた部分が大幅に改正されることとなった。8年間にわたって議論されてきた民法の実質的な改正案がようやく固まったためだ。市民生活の最も基本的なルールを定めているだけに、その影響は大きく広範囲に及ぶ。
都内に事務所を構える弁護士の男性は9月初旬、ある資料を食い入るように読んでいた。
資料のタイトルは、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」。2006年に法務省が、民法の全面的な改正を打ち出して以降、実に8年余りの歳月を経て、ようやく固まった実質的な民法改正の最終案だ。
実はこの弁護士、ある金融機関からセミナーの講師を依頼されていた。その名も「民法改正が与える影響について」。金融機関の取引先を集めて、民法改正の中身を詳細に解説するというものだ。
弁護士の元には、こうしたセミナーの依頼が地方の経済団体や大学などから相次いでおり、その準備に追われていたのだ。
まさに民法セミナーの〝花盛り〟ともいうべき状況がやって来そうな様相だが、それには理由がある。
民法の改正をめぐっては、最終案に至る過程で議論が紆余曲折、昨年3月に公表された「中間試案」からも大きく変わっており、簡単には理解できないからだ。
そのため、冒頭の弁護士も資料と格闘しながら、一言一句、変更点などをチェックしていたというわけだ。
では、どうしてそんなに議論が混乱したのか。
そもそも日本の民法はルールを重視し、それに基づいて契約の有効性を判断する「大陸法」がベースとなっており、ルールがない部分については判例を積み重ねる形で対応してきた。