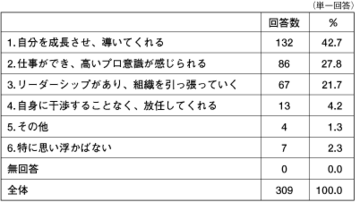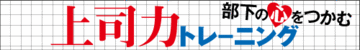これまで、部下とのコミュニケーション・ギャップが生まれる背景について、おもに上司世代が抱えている問題点を中心にお話ししてきました。次いで部下側の問題点を掘り下げていく前に、彼らがいかに上司世代と異なる会社観、仕事観を持っているかについて、見ていきましょう。
フットワークの軽さがウリの上司世代
バブル期入社といわれる上司世代が就職活動をしたのは、史上空前の売り手市場だった90年前後。大卒就職率は80%を超え、会社を選ぶ基準も、「給料が良くて名の知れたところ」というブランド志向でした。
大半が希望の会社に入ることができたため、会社に対するロイヤリティも高いのです。当時は、年功序列、終身雇用が一般的ですから、よほどのミスマッチがなければ入社後すぐに、将来約束されているポストや高額の給与を投げ打って、転職を考えるようなことはありませんでした。
「どうにかなるさ」「やればできる」が上司世代の基本的な仕事観。どの会社からも引っ張りだこだったこの世代は、「自分は特別な存在だ」といった自信があります。“この仕事がしたい”というこだわりを持たずに入社したぶん、どんな仕事にも興味をもって当たる柔軟性がありました。
しかし、92年にバブルがはじけ、就職率は下落の一途をたどります。2003年に過去最低の55%を記録したところでようやく頭打ちとなり、2005年には59.7%まで復調。リクルートワークス研究所によると、2008年卒業予定の大学生・大学院生に対する民間企業の求人総数(推計)は、ついにバブル期を上回り過去最大の93万3000人、大卒の求人倍率は2.14倍となり、16年ぶりに2倍を超えています。
とはいっても、ここ最近の厳選採用の流れは簡単には変化しそうにありません。企業は採用の質を重視し、優秀な学生のみを獲得しようとしています。採用市場において競争優位性を持っている大手人気企業は特にそうです。つまり、ある人は何社も内定が出るにもかかわらず、ある人はゼロという「就職格差」が起こっているのです。