
前川孝雄
上司から「部下が離れる」5つの罠、優秀で責任感の強い人ほど要注意
上司が部下を指導する際に、「ハラスメントになるのでは?」と悩み、言動を抑制するケースが増えています。企業も管理職層にアンガーマネジメント研修を実施するなど、対策に懸命です。しかし、それらはハラスメント事案を抑える効果はあっても、部下と上司の良い関係を築くための根本的解決にはならないと筆者は考えます。なぜなら、そこには「事なかれ主義」があるからです。地雷を踏みたくないと思えば、上司は部下に関わることを避け、部下の気持ちや成長に無関心になりかねません。

「人事評価に納得できません」を防ぐ、上司の“聞く力”を高める6ステップ
上司に必要なスキルの一つに、「評価納得を得ること」があります。節目ごとに部下に仕事と成果を振り返らせ、上司からのフィードバックに納得を得てもらい、次の成長に向かわせることです。「評価納得」は、部下との評価面談の際に醸成します。部下の意見や気持ちにじっくりと耳を傾けながら、本人の内省を促していくことが鍵となります。その際、重要になるのが、上司の傾聴力です。今回は、部下の考えを引き出す「傾聴の6つのステップ」について解説しましょう。

上司は、部下の「仕事の幸せ」に無関心すぎる!仕事に夢中になってもらう方法とは
上司は、個々のチームメンバーが仕事を「大切な自分事」と受け止め、率先して進めようとする状態を整えるべきです。これによって、自律的に働く個人とチームが成り立ちます。反対に、上司も部下も、仕事を「やらなければならない苦役」と受け止めると、互いの役割や関係も辛く感じることでしょう。そこで、どうすれば仕事を「没頭して熱中する喜びや楽しみ」と感じることができるのか。ハンガリー出身の心理学者ミハイ・チクセントミハイによる、「フロー理論」を紹介しましょう。

部下は褒める…けど「褒め過ぎ」も注意!“最優秀賞”受賞者が辞めていった意外な理由
上司の皆さんの中には、「組織の足並みが揃わない」「チームとして一つにまとまらない」と悩んでいる人もいるでしょう。かつてスタンダードだった「日本型組織」、つまり男性正社員中心の組織から、現代は年齢や性別、国籍や文化の違い、育児や介護の有無、雇用形態の違いなど、異なる立場や価値観を持つメンバーで構成される職場に変化しています。共に認め合い活躍できる組織を「意識的」につくっていく必要があるのです。そのためには、チームで部下それぞれの持ち味が活きる役割を明確にし、互いに協力し合える環境をつくることが重要です。

上司の「会社の方針だから」に部下はげんなり…部下のやる気が湧く伝え方とは
上司が部下のやる気を湧き上がらせるには、人の心の構造を理解しておくことが必要です。動機づけには、「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」があるとされています。前者は「会社から評価され昇進したい」「より高い給料が欲しい」「命令に従わないと不利になる」といったもので、これまでは外発的動機づけを多用しがちでした。しかし時代は変わり、若者を中心に「会社の命令は絶対」「従っておけば安心」とは考えないようになっています。終身雇用と年功序列が崩れつつある今、外発的動機づけが効きにくくなっているのです。

「君のため」と意見を押し付ける上司が反面教師、“心理的安全性”の大切さ
部下との信頼関係づくりで留意したいのが、「心理的安全性」です。部下が力を発揮して働くためには、職場が安心・安全な場所であることが重要です。「本音や弱みを見せても非難されず、上司やメンバーに受け入れられている」と感じられることが大切だからです。そのためには、上司が率先して自己開示し合える場をつくり、相互に自分の気持ちや考えを伝え合うステップを踏みましょう。ただし、部下のプライバシーへの過渡な踏み込みは控え、自らオープンに語りつつ、部下の自然な自己開示に耳を傾けましょう。

デジタル化が加速しビジネス環境が大きく変わる中、中堅・ベテラン社員はこれまで培った知識や過去の成功体験にとらわれず、時にはそれらを捨て去って新たなスキルを得ることが重要といわれる。しかし重要なのは「捨て去る」ことではなく、残すべきものと潔く捨てるものを取捨選択することだ。何を捨て去るべきなのか。また、中高年がキャリアのために学ぶ上で重要なポイントとは何か。
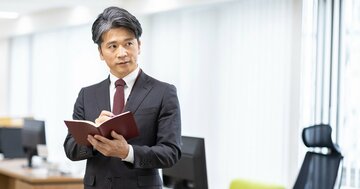
働き方の変化、ビジネスモデルの転換など、コロナ禍をきっかけに企業は大きく変わろうとしている。旧態依然とした価値観から抜け出せないミドル世代は会社にとって重荷になっていく……。環境が大きく変わる中で、ミドル世代の社員はこれからのキャリアをどう考え、行動していくべきなのか。

終身雇用の崩壊で、60歳を超えて働き続けることが当たり前になってきました。60代以降のキャリアを充実したものにするためには、「会社依存から脱却」し、キャリア自律を目指すことが重要です。そのために、40~50代のビジネスパーソンはどんなことを考え、行動すべきなのでしょうか。

最終回
年上部下と上司、どちらが上座に座るべき?職場の士気を高める飲み会のルール
年下上司が意外と頭を悩ませる職場の飲み会。コミュニケーションを図って、メンバーの士気を高めたいが、どうしても年上部下に気を使ってしまう。上座に座ってもらうべきか、どんな話題を振ればいいのか……? 連載最終回は、職場を元気にする飲み会のルールを紹介する。

第4回
無視、反抗……。年上部下の困った行動を止めたい!相手のプライドを傷つけず、上手に叱る方法とは。
年上部下の目に余る行動に、「一度、ガツンと言わなければ……」と思いながらも遠慮や面倒をさける気持ちから、つい尻込みしてしまう年下上司は少なくないはず。実際に、思い切って注意しても聞き流されたり、反抗的な態度を取られたりすることも。多くの年下上司が頭を抱える、年上部下の上手な叱り方とは?

第3回
褒めたのに「言葉に真心がない」と言われて鬱。年上の部下をヘタに褒めてはいけない!?
部下を褒めて伸ばすのは上司の役割。でも、相手が年上部下となると少々勝手が違ってくる。下手な褒め方をすると、「上から目線だ」「何か他に意図があるのか?」と逆に関係がおかしくなることも。連載第3回は、年上部下に気持ちよく仕事をしてもらうための褒め方のルールを紹介する。
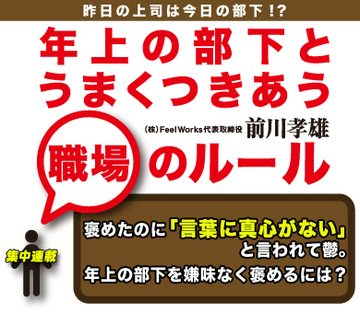
第2回
年下の上司を「○○君!」と呼ぶ60代の部下、当人同士は納得していても周囲の反応は……。
自分をどう呼んでもらうか、「呼び方」の問題にはじまり、指示命令の出し方やミスをどう指摘するかなど、年上部下とのコミュニケーションには多くの戸惑いがある。どんな言い方、接し方をすれば、年上部下のプライドを傷つけず、仕事をうまく回せるのか……。連載第2回は、年上部下との関係を良くするコミュニケーションのルールを紹介する。

第1回
客先で「オマエ」と呼ばれ、ブチギレ寸前!!年上の部下の扱いに手を焼く管理職が急増中
お世話になった先輩や、出世ラインから外れたベテラン社員が自分の部下に……。そんな状況が当たり前になりつつある今、「やりづらい」「扱いにくい」と年上部下とのつきあい方に悩む管理職が急増している。年上部下を抱える上司の苦悩と職場の惨状とは? 5日間の集中連載スタートです!

最終回
多くの企業で人事制度の男女格差が撤廃されつつあります。しかしそれらが効果的に運用されているケースは少なく、上司の力量によって大きな差が生まれています。今回は女性社員を生かす4つのポイントをご紹介します。

第15回
「泣かれたら困る」「辞められたらどうしよう」――。そう思い、上司はなかなか強く女性部下を叱れないものです。しかし、彼女たちは甘えで泣いているわけではなく、むしろ叱られたいと思っているようです。
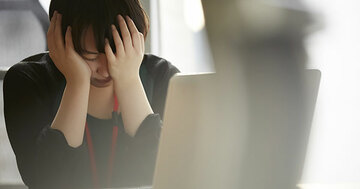
第14回
職場に出産や育児を支援する制度ができるのは喜ばしいですが、一方で立場の異なる女性社員同士の溝が深まってしまうケースがあります。典型的なのが「独身の女性社員」と「既婚・子どもありの女性社員」の対立です。

第13回
自分の目に入ることしか見えない女性部下は、上司から頼まれた仕事を断ってしまったり、正論ばかり吐く傾向にあります。彼女たちには、組織軸寄りの考え方を伝えると同時に踏み込んで徹底的に叱ることも必要です。

第12回
派遣として働いたことのある女性であれば、誰しもが経験している同僚男性社員からの誘い。しかし立場が弱い彼女たちは断りたくとも断りきれず、また周囲も介入しづらい問題のため、間に入ることが難しいようです。

第11回
女性部下は、上司が考える以上に上司の一挙手一投足を見ています。そして上司の言動から「不平等感」のニオイを嗅ぎ取ると、とたんにモチベーションを低下させ、コミュニケーションが難しくなることもあります。
