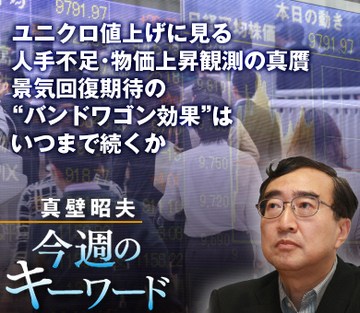高山は、ニューヨークの大学でファッションを学び、帰国したばかりの中丸美香を夏希常務から紹介される。『ハニーディップ』の商品企画メンバーとして新たに加わるという。2人は早速、千葉ショッピングセンター店に視察に行く。店頭でお客の行動を観察をしていた高山は、ある販促策を思いつく――。若き参謀、高山昇の奮闘ぶりを描く『経営参謀』が6月27日に発売になりました。本連載では、同書のプロローグと第1章を5回に分けてご紹介します。
助っ人登場
翌日、高山がインスタットビルに出勤すると、いつもの満面笑顔の夏希常務が高山の席にやってきた。
「高山くん、あなたの助っ人がひとり増えることになったわよ」
「はあ? ぼくの助っ人ですか」
夏希常務の後ろを見ると、小柄でそばかすの丸顔に、眼鏡をかけた女の子が立っていた。
「中丸美香さんよ。ニューヨークのファッション工科大学、FITに留学していて帰国したばかりなの」
ニューヨークにあるFIT(Fashion Institute of Technology)のことは、高山も聞いたことがあった。有名ブランドのデザイナーも数多く輩出している世界トップレベルのファッションに関する教育機関だ。
いいなあ、海外で勉強できて。 高山も以前から海外で学ぶことにあこがれを感じていた。
「高山です。よろしくお願いします」高山は軽く頭を下げた。
その様子をじっと見ていた中丸美香は高山の服装を見て、いきなり高い声で早口にしゃべり始めた。
「君さあ、ファッションのこと、あんまり知らないでしょ?」
「はあ?」
不躾な物言いに戸惑う高山に、夏希常務は「この子はね、しばらく英語圏で過ごしていたから、Youをそのまま直訳して、『君』って言っちゃうのよ。気にしなくていいから」と言った。
夏希常務よりも高い声を出して、中丸も「うふふ」と笑った。
「だって君のパンツ、いけてないもん。微妙に太いしさ。それに、そのダンガリーもねえ…」
言われて高山は気が付いた。今はいているチノパンは、前の会社の時に社内向けの在庫処分販売で買ったものだった。しかし、はく機会も少ないために傷みもせず、ずっと買い替えていなかった。結果、今風の細身のものではなかった。
「タック付きではないだけ、まだましかな。いひひ…」
中丸は、さらに高山をいじった。
「中丸さんには、『ハニーディップ』の商品企画をしてもらおうと思っているの。高山さん、これから中丸さんと一緒に売り場に行って、案内してきてくれる?」
「わかりました」
「君、よろしくね」
中丸は明るく屈託のない表情で、パンと高山の肩を叩いた。
「さあ、行こう」
さっさと早足で歩いていく中丸のあとにつき、高山もオフィスを出た。
「君さあ、新業態を成功させたことがあるんだってね?」
千葉ショッピングセンターに向かう電車の中で、中丸が話しかけてきた。
「ええ、すごく短期間で立ち上げたけど、幸いうまくいきました。市場調査のデータから、いろいろと分析していたら、ニーズが見えてきて」
ふーん、と聞いていた中丸は、「あたしもね、マーケティングのクラスをとったことがあるんだ。だから、そういう事例にはすごく興味があるの」と言った。
「ぼくは、マーケティングをきちっと学校で勉強したことはないけど…。中丸さん、自分でお金を貯めて留学したの?」
「半分は自分の貯金で、残りの半分は親に借りたの。毎年150万円ずつ返すんだ」
親に半分借りるのか、そういうやり方もあるな、留学に現実味を感じていなかった高山にとって、中丸の話は、あこがれを身近なものに感じさせた。
「田村社長はね、あたしの伯父にあたるの。夏希さんと同じ、姪っ子なんだ。歳はだいぶ離れているけどね、うふふ…」
なるほど、この子も一族なんだと、高山は知った。