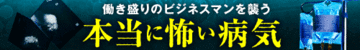アカデミー賞の主演女優賞を映画「アリスのままで」のジュリアン・ムーアさんが獲得した。役柄は50歳を迎えたばかりの言語学教授。若年性アルツハイマー症が進んでいく姿を演じ、その迫真の演技が評価された。
認知症の人が急増していくのは日本だけに限らない。多くの先進諸国で共通する社会的な課題である。普通の家庭を突然襲う「悲劇」と捉えて、映画のテーマにされてきた。
まず、作家の描く文芸作品から始まり、次いで妻や夫の介護体験記をベースにして製作されてきた。そして、社会保障施策として介護が表舞台に登場するとともに、認知症ケアの実態をストレートに描く記録映画が出現し始めた。それぞれ第1類型から第3類型へと位置づけられ、認知症ケアが向上して行く歩みと符合する。
 ある日、認知症になったら…
ある日、認知症になったら…
夫婦愛や家族愛のラブストーリーから、ケアのあり方を問う極めて実践的で研修教材と言えるような作品まで相当に幅広い。きれいごとの物語では済まされない厳しい現実を前に、その実情をありのままに突きつけ、その対応法を学び取ろうという方向に向かっているようだ。
認知症を軸に介護を主題とした内外の映画作品を振り返ってみる。
認知症本人の目線で語られる
「アリスのままで」
「アリスのままで」は、アカデミー賞のほかゴールデングローブ賞と英国アカデミー賞の各主演女優賞や多くの映画賞も得て、昨年の映画界の話題をさらった。これまでの「介護作品」と違うのは、家族や周辺からの目線でなく、認知症本人の目線で作られていることだろう。主役の大学教授が、日々の講義や暮らしの中で突然記憶が抜け落ちてしまう。その驚愕と不安な気持ちが正面から描かれている。
学生を前にした講義中に専門用語が出て来なくなって周章狼狽する。ジョギング中に自宅の方向が分らなくなってしまう。挨拶したばかりなのに初対面の言葉をかけてしまう。
認知症の初期に見られる記憶の抜け落ちである。それを自身で自覚し、「自分が壊れていく」と理解できる。記憶喪失がこの先どんどん広がっていく。その未来像におののく。深刻な事態を予測し、次第に本人の面立ちも変わっていく。その過程が実にリアルだ。
この数年、日本の認知症ケアで強く指摘されているのが「本人本位」。認知症本人の立場に立って接していかねば、という大きな流れの中で作られた作品である。
認知症の本人が自分の気持ちを表現した代表例は、オーストラリアのクリスティーン・ブライデンさんだろう。1995年、政府高官だったクリスティーンさんは46歳でアルツハイマー症と診断される。日本にもやってきてたびたび講演した。
認知症になるとどのようなことで困難な思いをしているか、どのようなケアをしてほしいかなど当事者ならではの発言をし、本も執筆している。
映画の中で主人公は認知症の症状を冷静に分析しスピーチする。
「わたしたちを役立たずだと思わないでください。わたしたちの目を見て、直接話しかけてください。わたしたちが間違ったことをしてもパニックにならないでください。わざとしていると受けとらないでください。なぜならわたしたちは間違いを犯してしまうからです。わたしたちは同じことを何度も言い、おかしなところにものを置き、迷子になるでしょう。でも必死になってその償いをし、認知の喪失を乗り越えようとするでしょう」
この言葉は、ブライアンさんが繰り返し語っていることと重なる。
2004年には京都市で開かれた「国際アルツハイマー病協会第20回国際会議・京都」で福岡市在住の認知症の男性が、日本人として初めて登壇し、日々の生活を語った。その後、各地で主に若年性認知症の人たちが介護関係のセミナーに出席して、自身の体験を披露するようになる。
2002年には、認知症ケアに早くから取り組んできた英国・スコットランドで認知症当事者のグループが世界で初めて登場し、政府や自治体の審議会に参加し政策に関与している。日本でも昨年10月に当事者組織の日本認知症ワーキンググループが発足した。