ダイヤモンド・オンラインplus

10月27日~28日に開催された「ad:tech tokyo 2011で、藤田康人・インテグレートCEOをモデレータに、ブランドマーケティングに実績を持つ、日本ロレアル、メルセデス・ベンツ日本、ジョンソンのマーケティング責任者が、自社事例を通じマーケティングの将来像を語った。
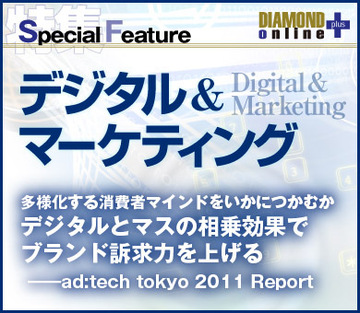
第10回
P-Growは、「魅力的な商材を持つが、それをWeb上でどのようにして売ればよいか」と悩む、主として中小のEC事業者向けの支援に力を入れている。ECサイトの企画制作と広告予算設定に関する考え方について聞いた。

10月27~28日に開催された「ad:tech tokyo 2011」に登壇し、大きな反響を得た世界第一線のマーケッターたちによる6つのキーノートカンファレンスレポートの第2回目。
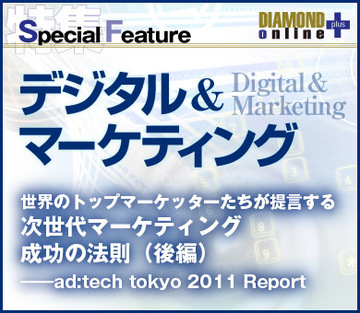
10月27日・28日に開催された世界的マーケティングカンファレンス「ad:tech tokyo 2011」には約7500人が参加し活況を呈した。2011以降のデジタルマーケティングはどこへ向かうのか。そのベクトルを示唆する6つのキーノートカンファレンスを中心にレポートする。
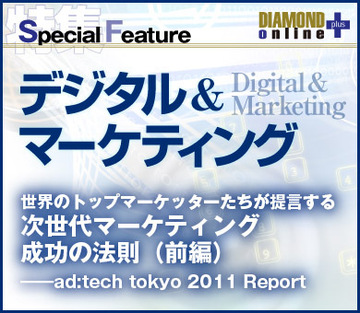
2011年10月7日に開催された「『若手社員の流儀』ワークショップ」。入社5年目までの若手社員を対象に、企業という組織で働くための“振る舞い”を学び、企業との長期的な関係構築を考えることを目的としたワークショップの内容を紹介する。

第9回
中国市場への窓口となり、出店企業を強力にサポートするのがSBIベリトランスだ。そのシステムと中国EC市場の現状を、同社事業開発部の黄 美香氏に聞いた。

東日本大震災は地方の医療過疎の深刻さを浮き彫りにした。また、津波で多くの医療情報が流されたことは、情報保存のあり方を見直すきっかけとなった。前回の被災地における訪問診療の現状レポートに引き続き、今回は震災から医療情報を守るための最新の取り組みを紹介する。

「グローバル人材の育成」は、多くの企業が問題意識を持ちながらも、なかなか対応できていないのが現状だ。さまざまなアンケート調査結果を基に、日本企業の現状と問題点を探った。
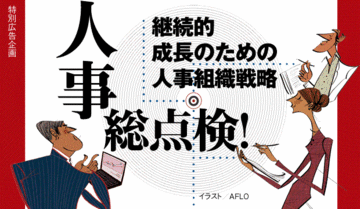
10月20日から 「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度がスタートした。高齢者向け住宅の選択肢は増えたが、自分らしく生きるための「終の棲家」はどのように見つければよいのか、介護ジャーナリストの小山朝子さんに聞いた。
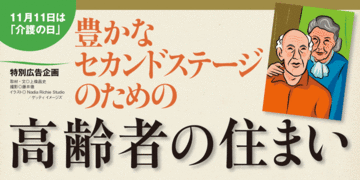
チタンを水溶化した「アクアチタン」。最新のナノテクノロジーにより生まれたこの新しい素材に、航空会社や衣料メーカーなどさまざまな企業が注目。新たな商品やサービスを展開している。その可能性についての研究成果を報告するシンポジウムが、開催された。

BS-TBSで毎週土曜日23時から放送している「グリーンの教え」に出演することになった日本HP小出伸一社長。司会の石川次郎さん、アシスタントの絵美里さんとの収録の様子を交えながら、小出社長のグリーンの教えを紹介しよう。

男性のみなさんは自分の香りを持っていますか? 自分の香りを知っていますか?最近加齢臭という言葉がかなり広がってきて、年齢を重ねることによるこの問題がいろいろなメディアでも取り上げられていますが・・・

金銭目的はもちろん、機密情報が盗まれたり、システムを機能不全にしたりする新たな脅威に対し、マカフィーはGTIなど独自のソリューションで予防効果を発揮。また、モバイル分野のセキュリティにも長けており、企業のセキュリティレベルの向上に貢献している。

不特定多数の企業や個人にウイルスを送り付ける「愉快犯」的な手口が悪質化し、企業活動に大ダメージを残すほどの「標的型」サイバー攻撃が増加している。いつどこで狙われるかわからない見えない敵に対し、どのように防げばいいのだろうか?
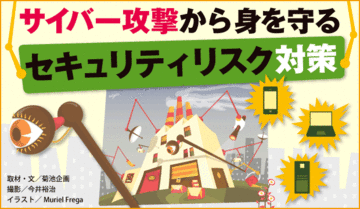
第6回
ECサイトでの定期購入に強い通販管理システム「たまごカートPlus」を提供するTEMONA代表取締役の佐川隼人氏に、リピーター顧客を増やす効果的な仕組みについて聞いた。

第7回
「ECドック」など独自のEC支援サービスで注目を集める「サイテキ」の石山龍二代表取締役に、コスト削減を実現する新サービスの内容について聞いた。

第8回
入札マーケットの規模は年間20兆円以上とも試算されているが、「うるる」では入札情報速報サービス「NJSS」を提供し、中小企業の入札参加支援を行っている。同社の秋元優喜氏にその特徴を聞いた。

伝動・運搬ベルトなど工業用のベルト製品などを製造するバンドー化学。ベルトメーカーのパイオニアとしての歩みと今後の展開について、代表取締役社長の谷 和義氏が語った。

スマートデバイスを業務革新に活用するアイディアがあっても、具体的にそれを実現する方法がわからない……というジレンマを抱える企業も多い。そこで紹介したいのがNRIネットコムが提供する「モバイル会議」サービスだ。
