ダイヤモンド・オンラインplus
強力なパートナーと組んで、 満を持して旭化成がAEDの普及に参入した。日本における救命救急医療発展の一翼を担いつつ、同社グループのいっそうの成長を目指す。

法人向けの幅広いソリューション提供で実績のある京セラコミュニケーションシステム。便利で安全なスマートデバイスの活用についても数多くの導入事例や顧客ニーズに基づき、幅広いソリューションを提案している。その代表例として音声通話とデータ通信をスマートフォンに統合するサービス「KWINS Phone」と、スマートでセキュアなドキュメント配信サービス「GreenOffice Publisher」に注目した。

個人情報保護の観点もあり、ビジネスユースでのモバイル活用の敷居は高い。しかし、スマートフォンがコンシューマー市場で浸透しながら、その機能を進化させている今、新しいモバイルコンピューティングに期待が集まっている。「スマートデバイス」のビジネス活用の課題について専門家に聞いた。

従来と比べられない大量のデータを分析し、業績を向上させようとする企業が増えている。多くの企業は典型的なデータ分析やレポート、大量データの蓄積にとどまり、経営効果を得る段階に達していない。そんななか、SAS Institute Japanは分析に特化し、数多ある情報から真の価値を生むソリューションを提供している。

分譲マンションの資産価値を左右するマンション管理。管理組合の抱える問題や運営のヒント、管理会社との付き合い方について、マンション管理に関する公益法人であるマンション管理センターに話を聞いた。
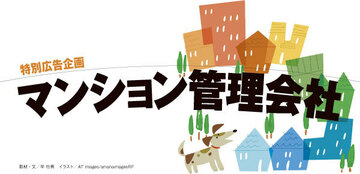
経産省の調査報告によれば、B2C型の電子商取引(EC)の国内市場規模は2010年時点で7兆8000億円を超えた。さらにスマートフォンやタブレット端末の普及が追い風になり、モバイルによるEC利用の規模拡大への期待も高まっている。今後のEC市場の堅調な規模拡大は、課金・決済手段の多様化にも支えられている。
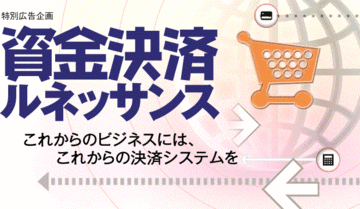
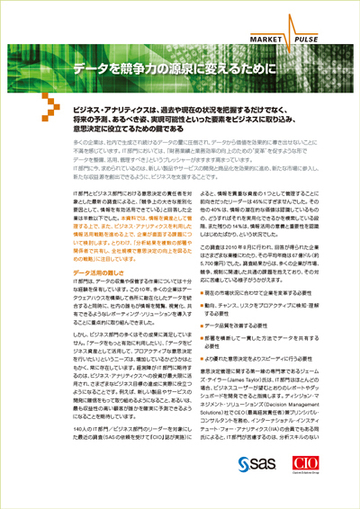
ビッグデータとは「膨大」で「多様」なデータを指すことが多い。そんなビッグデータの時代を生き残るためには、社内・社外の広範なデータをスピーディに結び付け、的確な経営判断につなげていく必要がある。
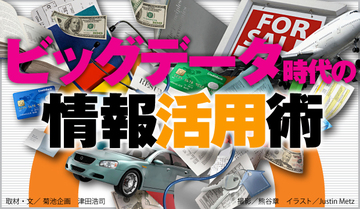
蝶屋シャツの遠州ヴィンテージクロスに待望の新作が追加されると言う。白地にブルーのロンドンストライプやギンガムチェックなどベーシックな柄モノばかりを7種厳選(商品名はSANSHIRO)。店頭に並ぶのは4月から。一見の価値はありそうだ。


ワインレーベル フォー シップスで購入したサウスウィックのスーツはダークブルーである。1990年代から最近まで、ビジネススーツはグレーが主流だった。しかしなぜか今、筆者の目にはダークブルーが新鮮に映り、ひと目ぼれでこれを選択したわけである。

国内市場が縮小し、グローバル化が進むなか、出張業務はビジネス成長に不可欠だ。出張業務の管理をアウトソーシングすることで、直接コストや間接コストはどのように削減できるのか。

震災復興、経済対策が強く求められる昨今だが、財源は乏しく明るい材料は少ない。2012年の政策、そして住宅市場への影響をどう見るか。住宅情報サイトを運営するホームアドバイザーの井端純一社長に聞いた。

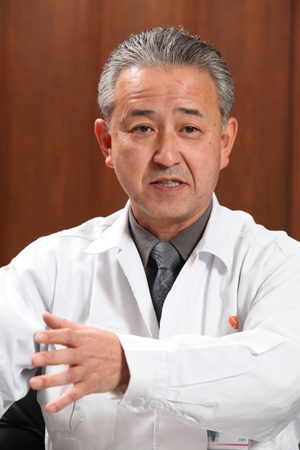
BS-TBSで毎週土曜日23時から放送している「グリーンの教え」。昨年のクリスマスイブの夜にゲストとして登場したのは、車の板金修理店を全国でFC展開するカーコンビニ倶楽部社長の林成治氏だ。林社長が語る″グリーンの教え〟とは?

ビジネススーツは約3年ごとに買い替えるのがエシカルなスタイルだ。3年間は同じ服を着続けるわけだから、流行に対して免疫を保ち、しかも飽きのこないスーツを選ばねばならない。いい替えれば、流行に過敏なデザイナーズスーツを選ぶより、伝統的スタイルで通すのがお勧めである。

地球環境問題が深刻化していることに加え、東日本大震災の影響を受け、企業活動を取り巻く社会の制約条件が大きく変化してきている。変化を先読みし、次なる一手を打つにはどうしたらいいのか。東北大学大学院環境科学研究科の石田秀輝教授に聞いた。
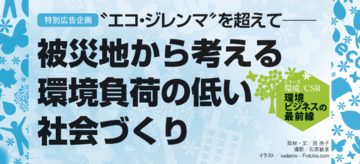
最近働くスタイルの中で、一番肩身の狭いアイテムの一つが…ネクタイ。クールビスが定番化したこともあり、寒くなってきても上手に、また自分らしくカッコよくネクタイをしている人が少なくなってきているように感じます。

「保有せずに利用する」クラウドサービスとともに、TCOを削減しながら万が一の際もITのサービスレベルを維持できるデータセンターへの関心が高まっている。企業経営者としてはこれらの違いをどう理解し、どう活用すべきなのだろうか。
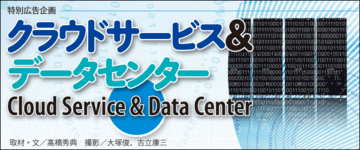
2011年、辛亥革命から100年を迎えた台湾。日本のお隣であり、歴史・文化、美食や交流でも感動を禁じえないパートナーシップ豊かな「台湾の旅」へ誘おう。
