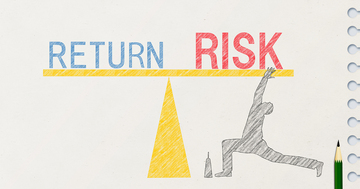ウェルスナビ
関連するキーワード
みずほフィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ JT マネーフォワード関連特集
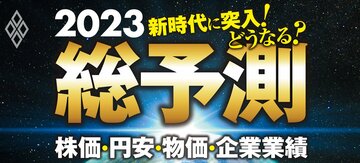
関連ニュース
#20
「お年玉株」440銘柄【後編】、日銀政策修正に動揺せず!攻めの売上高急拡大株&守りの高配当株ランキング
ダイヤモンド編集部,篭島裕亮
株価は短期的には需給や材料で動くが、中長期では業績の伸びに比例する。世界景気が不透明なときこそ、目先の値動きに一喜一憂するのではなく、中長期の業績から銘柄を選ぶべきだろう。そこで今回はアナリストの予想を活用して、中長期で期待できる4種類の「お年玉株」候補を選抜。後編では「2期先の売上高拡大株」と「来期増益予想の高配当株」という2種類のランキングをお届けする。

#5
売上高「急成長中」グロース株ランキング【80社】7位GMOフィナンシャルゲート、1位は?
ダイヤモンド編集部,篭島裕亮
株式投資の醍醐味の一つに、将来性抜群の小型成長株の発掘がある。そこで最新決算を踏まえて、直近3期の年平均売上高成長率や、直近四半期の売上高成長率などから、外部要因に関係なく成長が狙える将来の10倍株候補をリスト化。昨年後半から株価が調整していた企業が多いが、米国のインフレが一服した場合、再びこれらのグロース株が脚光を浴びる可能性が高い。この好機を見逃さないようにしよう。

ロボアドバイザーでの資産運用に反対する4つの理由
山崎 元
資産運用の世界で徐々に普及が進んでいるロボアドバイザーは個人投資家にとって役に立つのだろうか?筆者は現段階の実用性に対して否定的だ。その四つの理由をお伝えしたい。

第6回
ミドル起業がはやる理由、遅れてきた「76世代」がブームを底上げ
ダイヤモンド編集部
今、30~40代の中年層によるベンチャー起業が流行している。テクノロジーがレガシー産業にも浸透してくる中で、ミドル層が持つ社会人スキルと業界経験が必要とされているからだ。

第32回
ウェルスナビ柴山CEOに謝罪しつつ小幡教授が指摘「ウェルスナビを使わなくても、グローバルな分散投資はできる」?
柴山和久
在籍時期は異なるものの財務省の先輩後輩にあたる、小幡績さんと柴山和久さん。行動経済学を専門とする小幡さんが、柴山さんに謝罪するというそのワケとは? 小幡さんは謝りつつも、ウェルスナビのお客さんはどういう人たちなのか、オフ会はやらないのか、どんな基準で投資対象を選んでいるのかなど、ウェルスナビのサービスについて自由にあれこれ聞いていきます。面白対談の前編をどうぞ!

第31回
「人間は自主的に貯蓄できない」マネーフォワードのユーザーから学びたい資産づくりの極意
柴山和久
親世代と比べて給与は不安定なのに、スマホ代など新たなコストは膨らむ…でもSNSなどで派手な消費行動を披露する――貯蓄できない環境がそろっている現代において、どうすれば資産をつくれるのか? 日本におけるFintechベンチャーの先駆け的存在であるマネーフォワードの設立メンバーで取締役兼Fintech研究所長の瀧俊雄さんと、資産運用のロボアドバイザーサービスを展開するウェルスナビを創業した柴山和久さんの特別対談・後編。「起業するつもりはなかった」というお二人は、どんな問題意識に突き動かされてFintechベンチャーを立ち上げたのでしょうか。

第30回
「75歳まで働きたい」と思える仕事をしているかどうかで生涯の金融資産は決まる?
柴山和久
なぜ起業を目指していたわけでない2人が、フィンテック・スタートアップを興すに至ったのか? 自動家計簿サービスなどを展開するマネーフォワード取締役兼Fintech研究所長の瀧俊雄さんと、資産運用のロボアドバイザーサービスを展開するウェルスナビ代表取締役CEOの柴山和久さんが、マネーフォワード設立の秘話や、「どう生きるか」と「どう資産運用をするか」のバランスについて議論します。

第28回
日本に投資が根づかない理由は「金融リテラシーの低さ」ではない
柴山和久
経済学者・安田洋祐さんをして、「従来のファイナンス本と比べて、積立の解説が圧倒的にわかりやすい」との感想をいただいた、柴山和久さん著『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』。安田さんが特に印象に残ったというポイントを挙げてもらった後は、日本に投資が根づかない本当の理由について、徹底的に議論します。

第26回
会社探しの最大のポイント「上りのエスカレーター=レベニュー・プール」の見つけ方とは?
柴山和久
人事業界で知らない人はいないサイバーエージェント取締役の曽山哲人さんが語る、「会社選びの3つのポイント」とは? 『元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた これからの投資の思考法』著者の柴山和久さんによる対談シリーズにお迎えし、AbemaTV 制作の舞台裏や、会社選びのポイントと資産運用のポイントの共通点などが明らかに!

第22回
ウェルスナビ柴山CEOに聞く「リバランスはどんなとき、どのぐらいの頻度で行うのがベストなのか?」
柴山和久
世界標準の「長期・積立・分散」投資は日本であまり知られていません。“正しく”行うための6つのステップを踏まえ、今回は特に、投資後に最適な資産配分を維持するための「リバランス」における注意点について紹介します。