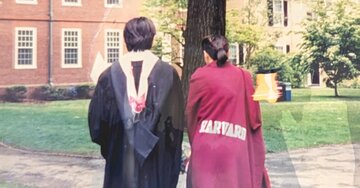2025年7月、早くも2027年3月卒業の学生の就職活動がスタートしている。近年、就職活動はますます早期化・長期化の様相を呈している。そんな中で、17年連続売上No.1を更新し続けている『絶対内定2027』シリーズは、不安な就職活動におけるお守りのような一冊だ。激変する就職活動にどう取り組んでいけばよいのか、本書の共著者であり、キャリアデザインスクール・我究館館長の杉村貴子氏に、就活生とその親が絶対に心得ておくべきポイントを聞いた。本稿では、就活生の親が絶対やってはいけないことを中心に、就活生への接し方のヒントを聞いた。(取材・文:奥田由意、撮影:池田宏、企画:ダイヤモンド社書籍編集局)
 撮影/池田宏
撮影/池田宏
就活生を潰す親の特徴2つ
就職活動は、子どもにとって人生で最初の「親離れ」の練習であり、保護者にとっても「子離れ」の練習です。これまで学生だった我が子が、社会人として自立していく第一歩です。
しかし、保護者の関わり方次第では、子どもの成長を阻害してしまう可能性があります。特に注意していただきたいのが「無関心」と「過干渉」という2つのパターンです。
【ダメなタイプ①】無関心
――「就活は自分でやるもの」という突き放し
我究館の説明会に来る学生の中には、本人は真剣に悩んで入塾を希望しているのに、保護者から「なぜ塾に行くのか」「就職活動なんて自分でやるもの」「自分たちの時代は自力でやっていた」と突き放されてしまうケースもよく見受けられます。
確かに保護者の世代は就職活動がもっとシンプルでした。我究館ができた35年前は、「資料請求→書類提出→筆記試験→面接」のように、就職活動は直線的なプロセスでした。スケジュールも経団連のルールに沿って、7月が内定解禁などのように明確でした。
しかし現在は、インターンシップからの選考など、複数の選考過程が並行して走っていたり、通年採用に近いかたちになっていたりするなど、採用が早期化、長期化し、そのプロセスも複雑化しています。業界どころか企業ごとに選考スケジュールが異なり、情報が錯綜しています。選考方法も、動画面接、AI面接、グループディスカッション等と多様化しているのです。
このように就職活動の状況が保護者が学生だった時代とは様変わりした現在、「一人で頑張るもの」として子どもを突き放してしまうのは、あまりにも厳しいものがあります。
保護者ができる3つのこと
無関心になるのではなく、保護者には3つの側面から、子どもを支えることができます。
1つ目は、情報面でのサポートです。圧倒的に社会人経験の長い親は多くの情報量を持っています。子どもが企業を比較し自分で判断できるように、人脈や知見を活かして、会社や業界について情報提供することです。
「●●という業界(会社)、今注目されているらしいよ」「知り合いの〇〇さんから、お話聞いてみる?」というように、押し付けるのではなくヒントやきっかけを与える形で、子どもが判断できるようサポートできるでしょう。
2つ目は、心身の健康を支えることです。就職活動では緊張と相当なストレスを受け続けるため、どんなにポジティブな学生でも心身の不調を感じやすくなります。不安定な時期であることを受けとめ、無理なく日常生活の基盤を支えてあげてください。
同居されている場合は、食事や睡眠など規則正しい生活をうながしたり、遠方にいらっしゃる場合には、それとなく励ましたり、応援しているというメッセージを伝えるだけでも、子どもは安心するはずです。できるだけ良いコンディションで就職活動に集中できるよう、生活リズムや心の状態にさりげなく目を配ってあげてください。
3つ目は、環境や経済面でのサポートです。我究館に来られる多くの学生が、自分の就職活動で親に迷惑をかけたくないと言います。しかし、長期間におよぶ熾烈な就職活動に安心して挑戦するためには、環境と費用面でのサポートは欠かせません。Wi-Fiの完備や地方の学生であれば交通費や宿泊費等の援助など、挑戦できる環境づくりは、親ができる重要な支援です。
そしてもうひとつ、補足するならば、子どもの話を「ジャッジせずに聴く」姿勢です。
子どもの話を聞いていると、ついつい心配になって「それでいいの?」「もっと〇〇した方がいい」と口を出したくなるものですが、子どもが本音を話せるよう、否定せずに耳を傾けてあげてください。その姿勢に安心することで、本人も本音を話せるようになるものです。