
千石正一
最終回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。最終回の干支は「申(猿)」。「サルの脳みそを食べていた中国人」「サルは馬の守り役だった」等、サルにまつわるエピソードを紹介。

第11回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第11回目の干支は「卯(兎)」。「なぜ1羽2羽と数えるのか」「スペイン国名の語源はウサギだった」等、ウサギにまつわるエピソードを紹介。

第10回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第10回目の干支は「戌(犬)」。「犬を不浄とするイスラム教」「犬鍋が好物だった周恩来首相」等、犬食文化にまつわるエピソードを紹介。

第9回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第9回目の干支は「寅(虎)」。「高価な薬として密売される虎」「餃子の肉はもともと虎肉だった?!」等、虎にまつわる知られざるエピソードを紹介。
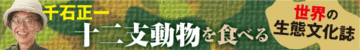
第8回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第8回目の干支は「辰(竜)」。「竜の正体はワニ?!」「dragonという名を持つトカゲ」「マンモスの肉を食べた現代人」等、竜の謎と正体に迫る!

第7回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第7回目の干支は「酉(鶏)」。「生卵を食べるのは日本人だけ」「ボクシングのバンタム級はニワトリの名前だった」等、ニワトリの謎と歴史に迫る!

第6回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第6回目の干支は「丑(牛)」。現在では代表的な家畜であるウシ。しかしその家畜化の歴史は、先史時代にまでさかのぼる。

第5回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第5回目の干支は「未(羊)」。中国では「美」は大きいヒツジの意味。「メイ」という発音からして美はヒツジと関係している。

第4回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第4回目の干支は「巳(蛇)」。広州や香港では、土用の丑の日の鰻の如く、秋にはヘビ食のポスターをありこち見かけるようになる。

第3回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第3回目の干支は「子(鼠)」。北は北極から、南は南極まで――全世界を制覇したネズミ。その繁栄の歴史は“人類と共に”生きた歴史でもあった。

第2回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第2回目の干支は「亥(猪)」。亥年は、本当は豚年だった!? 人間が、イノシシをブタへ“変化”させた歴史に迫る!

第1回
TVでおなじみの千石先生が、動物学者らしい視点で干支を語る。第1回目の干支は「午(馬)」。イギリス人はなぜ馬肉を食べないのか?その歴史的背景に迫る!
