
嶋田 毅
第24回
今回の落とし穴は、ニーズ無視の規制の罠です。為政者などは、人間が本質的に持つニーズである飲酒やギャンブルなどを「悪徳」とみなして規制しようとすることがありますが、それはかえって好ましくない結果をもたらしかねません。
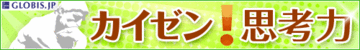
第23回
今回の落とし穴は、「合成の誤謬」です。これは、個々の単位で見たときには合理的な行動であっても、世の中の人々全員が同じような行動をとってしまうと、全体としてはさらに悪い状況がもたらされてしまうというものです。
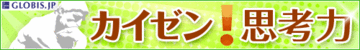
第22回
私たちの見る世界は「一部の選ばれし者」の世界であることが少なくありません。「大企業の社長」「有名タレント」は、「異常値の世界」の人々です。したがって、それだけを見て、集団間の差異として一般化してしまうのは大きな過ちです。
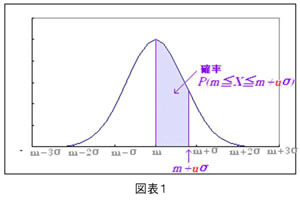
第21回
今回の落とし穴は、「手続きルールの悪用」です。これは、議論そのもので負けそうな時に、プロセスや手続きの妥当性を理由に、結論に同意しないというものです。往々にしてスピードを削いだりすることにつながります。
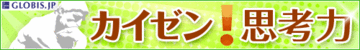
第20回
今回の落とし穴は、生存バイアスの罠です。これは、脱落あるいは淘汰されていったサンプルが存在することを忘れてしまい、一部の「成功者」のサンプルのみに着目して間違った判断をしてしまうというものです。
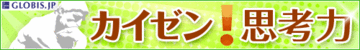
第19回
今回のテーマは、「移動平均」の落とし穴です。移動平均の数字だけを見て、実態を見誤ってしまうというものです。数字やチャートは人を騙しやすいツールです。伝える側に悪意があると、その傾向はさらに高まります。
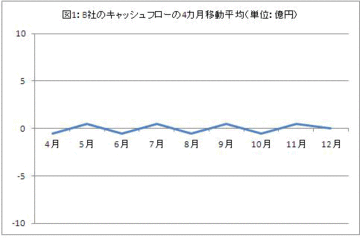
第18回
今回の落とし穴は、“Apple to Orange”です。本来、単純に比較してはいけないものをそのまま比較してしまい、間違った推論をしてしまうことです。何か数字を比較するときには「比較して意味があるか」に強く注意する必要があります。
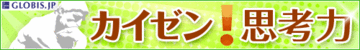
第17回
ビジネスは、「程度」や「限度」が大きな意味を持ちます。そこを曖昧にしたままルールを運用していると、“誤った数学的帰納法的発想”が持ち込まれ、ドミノ倒しのように、なし崩し的にルールは骨抜きになってしまいます。
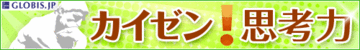
第16回
日本人は、自分の専門性等をむやみにひけらかすことを好まない、奥ゆかしい人が多い傾向にあります。なので、実際に実力や専門知識があるにもかかわらず、聞き手に本当の専門家であることが伝わらない場合が少なくありません。
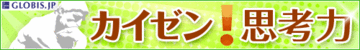
第15回
今回取り上げるのは、何かをしてくれた相手にはお返しをしなくてはならないという心理「返報性の心理」です。ここでのポイントは、「何かをしてくれたらお返しをしますよ」ではなく、まず何か相手に便益を与え、相手に貸しを作ることです。
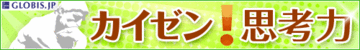
第14回
今回取り上げるのは、「どっちもどっち」論法です。本来、両者の非にかなりのアンバランスがあるにもかかわらず、お互いに責められるべき点があったということを根拠に、両成敗としてしまう落とし穴です。
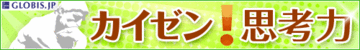
第13回
論証しなくてはいけない事柄が、その論証の根拠となってしまうという、不完全な論理展開がなされることがあります。それが「循環論法」です。そうならないためには、頭の中だけで考えるのではなく、理由づけをチャートで表すことが有効です。
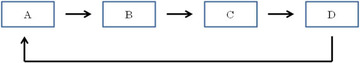
第12回
あらゆる条件について高いレベルで満たすことを求めてしまうが故に、かえって意思決定ができなかったり、スピードを殺いでしまったりすることがあります。スピードが求められる現代のビジネス環境において、強く留意すべき落とし穴です。
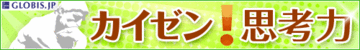
第11回
今回取り上げるのは、他にも選択肢や可能性があるにもかかわらず、「AもしくはBしか選択肢や可能性はない」と考えてしまう落とし穴です。交渉の場で、相手にとってより有利な選択肢を相手から奪うテクニックとして使われることがあります。
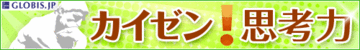
第10回
あなたは部下に対して、「自律的に行動してくれ」と話す一方で、「なぜ私に相談してくれなかったんだ」と言っていることはありませんか?こうした矛盾したメッセージは、受け手を混乱させてしまうため、常に自問する必要があります。
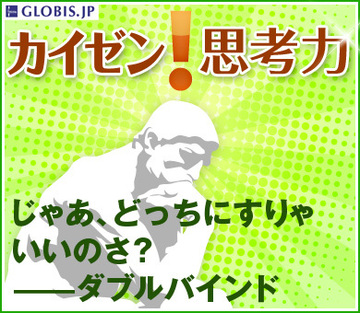
第9回
自分の専門領域については非常に詳しく、問題点が見えたり、解決策のアイデアは湧くものの、視野が狭く、それ以外の要素については見逃してしまうことがあります。それが「専門偏向」です。俗にいえば「専門バカ」という言葉に近いものです。
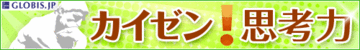
第8回
男性が浮気の言い訳として、「動物のオスのDNAには、より多くの子孫を残すというプログラムがインプットされている。これは自然の摂理なんだ」と述べることがあります。しかし、これは論理展開として正しいのでしょうか。

第7回
人間は、よほど悪い印象がない限り、過去に触れた情報を新しい情報よりも好ましく感じるという錯覚に陥ります。しかしそれでも、重要な意思決定を下すような場合には、より客観的な視点で判断することが必要です。
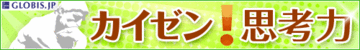
第6回
仮に5万人に1人がウイルスのキャリアという感染症があるとしましょう。そして精度99.9%といわれる検査を受け、「陽性」反応がでたら、「間違いなく感染した」と思うかもしれません。しかし、それは早計な可能性があります。
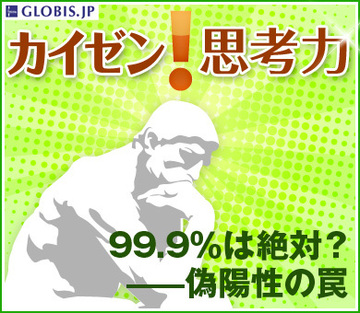
第5回
議論の途中で用語の定義が変わることはしばしばあります。意図的に意味をすり替える人もいれば、無意識にこれをやってしまう人もいます。用語の定義は論理思考のベースともいえますから、すぐに確認することが大切です。
