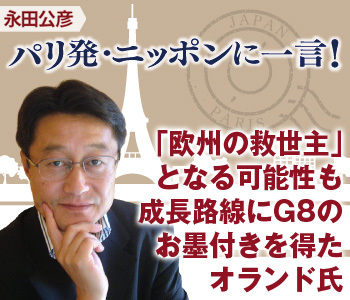永田公彦
第25回
株式会社ワーク・ライフバランスの創業メンバー大塚万紀子氏と、Nagata Global Partners代表パートナーでパリ第9大学非常勤講師も務める永田公彦氏の対談を全3回でお送りする。一人ひとりの働き方や生き方は、今後どう変わっていくのか?より充実したものにするには何が必要なのか?働く人(生活者)と働いてもらいたい人(経営者)、海外から見える日本人社会の文化という視点から意見が交わされた。第1回は、仕事の充足と生活の充足の関係性などについてお伝えする。

第24回
CHO(チーフ・ハピネス・オフィサー)の数が2年で50倍に…欧州、特にフランスでは、「幸福経営」の研究や導入の動きが、この数年急速に広がっています。これは、「従業員の幸せが企業や組織に繁栄をもたらす」という考えに基づいた、シリコンバレーに端を発し、最近は日本でも拡大の兆しが見える経営モデルです。

第23回
前回のコラムで「裁量労働制」は、長時間労働の拡大を助長する悪法となる可能性が高いとお伝えしました。一方、高度プロフェッショナル制度(高プロ)は、チャンスと見ています。本稿で示す「煙たがられ一目置かれる人だけを対象とし、彼らを活かせる職場のみで使われる」ならば、労使双方にメリットがあるからです。

第22回
フランスでは、裁量労働制で働く人が、一般労働者より長く働いています。また、この裁量労働制で働く人の数が15年で3倍も増え、長時間労働化に歯止めがかかりません。

第21回
働き方改革による法整備でも、日本の悪しき労働慣行が大きく減るとは思えません。理由は、この100年、働き方改革についての議論や対策の際に、「文化」という根本的な視点・論点が欠けてきたからです。

第20回
「フランス政府は、パリを、ブレグジット後の欧州最大の金融ハブにしたい」。エドゥアール・フィリップ仏首相の発言です。この動きを、金融機関の誘致(ロンドンと世界から)と、その事業環境の整備(税制・労働法改革)の両面からお伝えします。

第19回
「今、なんと言った(怒)!旅行に行けない子どもたちもたくさんいるんだ!」…筆者は幼少の頃、父親から強烈な平手打ちを食らいました。ここフランスで夏を迎えるたびに思い起こします。国民の間の「バカンス格差」に思いを巡らさざるをえないからです。

第18回
50%未満と国際的に極めて低い日本の年次有給休暇(年休)取得率。日本人が休まない「岩盤自主規制」に風穴を開けるためにすべきことの1つ、それは、「皆が、長く、安く、気軽に、バカンスを楽しめる社会にする」ことです。

第17回
「申し訳ございません。課長は、お休みを頂戴しています」…多くの外国人が理解しがたい日本の文化です。休みを取らない“岩盤自主規制”に風穴を開けるためにすべきことの1つ、それは、「休みとるために謝るのをやめること」です。

第16回
50%未満と、国際的に見て極めて低い日本の年次有給休暇取得率。これは一種の国民的な悪習であり、長年変わらない「岩盤自主規制」です。ここに風穴を開けるためになすべきことの1つ、それは、「取りたければ取ればいい」という風潮を徹底することです。

第15回
日本の正規雇用と非正規雇用の労働者間格差是正には、日本人社会の文化特性を考慮する必要があります。今回は「肩書を通して人を見る」「組織への献身度で人の価値を測る」という2つの文化に着目します。

第14回
正規雇用労働者が9割を占めるフランスに対し、日本では非正規雇用労働者の割合がついに4割を超え、格差問題が深刻化しています。有効な格差是正策を講ずるためには、その背後にある日本人社会の文化特性を考慮する必要があります。

第13回
「このままでは日本は、ますます経済が悪化し、国際的なプレゼンスも低下する。だから、もっと働け!」というのは大間違い。国や企業が強くなるには、逆に「みんなが、もっと働かなくなり、精神的に豊かになる」必要があるのではないでしょうか。

第12回・後編
日本人独特の文化価値観が労働偏重につながって生み出した「国民総残業社会」。今日、そのしわ寄せは特に女性に重くのしかかっています。前編に引き続き、真に「女性が輝く日本」になるための道筋を探ります。

第12回・前編
「女性が輝く日本へ」と題し、安倍政権のもとで女性が活躍できる社会づくりが始動しています。ところが実際には、輝く女性よりも疲れた女性が増えることが憂慮されます。その背景には日本人独特の文化価値観がつくりだす労働偏重社会があります。

第11回
世界各地のバー、レストラン、酒屋、スーパーマーケット等で広く見られる代表的な酒というと、ビール、ワイン、ウィスキーです。果たして、日本酒はこうした「世界の酒」の一角を占めることができるのか?専門家の意見も交えて考察します。

第10回
フランスでも昨年9月以来、中国の海洋進出と尖閣問題も含めた日米の防衛戦略に関し、専門家の発言が増えています。17世期以来の伝統を誇り西洋におけるシノロジー(中国学)の中心地となっているフランスの専門家たちは、尖閣問題と日中開戦リスクをどう分析しているのでしょうか。
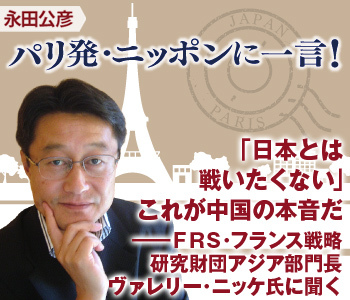
第9回
「女性の社会進出が日本の経済成長のカギ」(IMF報告書)などと言われながらも、なかなか男性優位の社会は崩れません。それは、国の政策議論や企業の人事制度議論の中では語られない、日本人社会独特の理由があるからです。

第8回
日本では、結婚当初こそ名前で呼び合っても、子どもができると「父さん・母さん」と、家庭内での役割の進化や年齢に応じ互いの呼び方も変わる夫婦が多くいます。なぜでしょう? その背景には、予想以上に奥が深く複雑な、日本人社会の文化的特質が絡み合っています。

第7回
先のG8先進国首脳会議では「財政の健全化と経済の成長の両方を追求」との見解が世界に示されました。厳しい緊縮財政に軸足を置いたメルケル路線に対し、緩やかな緊縮財政と経済成長を訴え続けたオランド氏の路線に、世界のお墨付きが加わったと言えます。