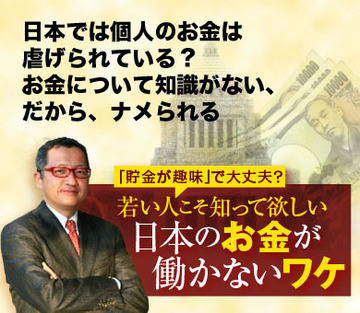上阪 徹
第1回
第1回外資系トップの英語勉強法勉強の極意。それは好きなものをあきらめて集中すること
世界で認められた外資系トップは、どうやって英語をものにし、グローバルな仕事を行っているのだろうか。その秘訣を10人の外資系企業トップに取材した。経営のプロフェッショナルが語るグローバルコミュニケーション。

最終回
若い世代ほど損をする日本のお金のインチキな構造は何も変わっていない
1400兆円といわれる日本の個人金融資産の8割は50歳以上の世代が持っていると類推される。一方で、これから日本に生まれてくる子どもは、生まれた瞬間に900兆円の借金を背負うことになる。このままでは、日本は国際社会の中で、没落の一途を辿りかねない。
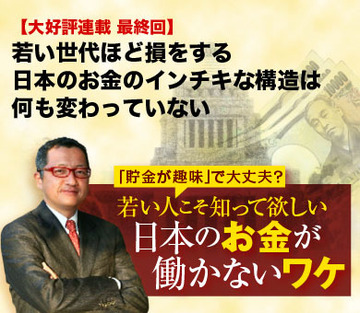
第5回
若い人にツケが回るなぜ、日本のお金の流れは変わらないのか!
これまで、日本のお金のいびつな構造の問題点とその歴史的な背景を見てきた。そして、日本にも、お金の流れを変えようという動きはあったことを述べた。その先鞭をつけたマネックスの創業、それに続くオンライン証券の登場によって、日本の金融市場は変わったのだろうか。
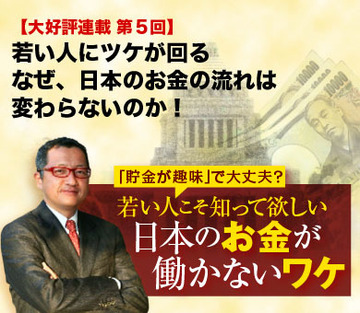
第4回
日本にもあった時代遅れの金融システムへの危機感
みんなが銀行や郵便局への預貯金に励む日本では、金融の仕組みが極端な間接金融偏重になっている。このいびつな構造は、実は戦後、国策でつくられたのではないか、というのが前回の話だった。では、こうしたいびつな構造に、誰も警鐘を鳴らさなかったのだろうか?実は、日本にも危機感はあった。
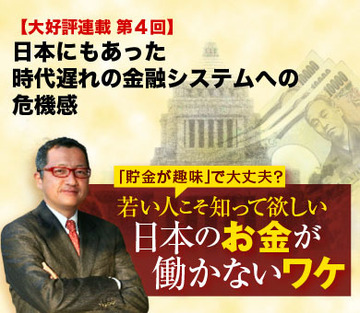
第3回
なぜ、みんなが預貯金に向かうのか?国につくられた“預貯金礼賛”
現在、日本の個人金融資産は、預貯金の占める割合が極めて大きいが、戦前は銀行融資を中心とした「間接金融」と、株式や債券などへの投資を中心とした「直接金融」が並存していた。預貯金第一、間接金融偏重の金融は、巧みな国策による誘導によるものだったのではないだろうか?
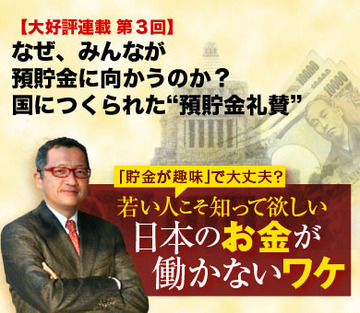
第2回
銀行や郵便局に預けたお金は国債の購入や公共事業に流れている
銀行にとって、預金者から預かったお金は、預金者からの借金ということになります。郵便貯金も同じです。この預貯金で、銀行や郵便局が国債を買っているということは、預金者である私たちは、間接的に国債を買っている、つまり、国にお金を貸していることになります。そのお金は、どのように使われているのでしょうか?
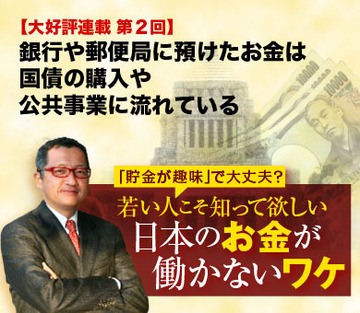
第1回
日本では個人のお金は虐げられている?お金について知識がない、だから、ナメられる
1400兆円の個人金融資産の7割以上を60歳以上の世代が持ち、一方でこれから日本に生まれてくる子どもは、生まれた瞬間に国家の借金900兆円を背負うことになります。それは、あまりに不公平ではないでしょうか?