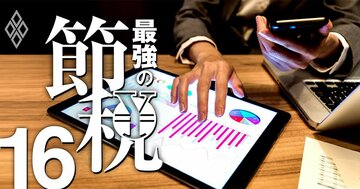小林義崇
【国税OBが明かすお金】イメージとはまったく違う富裕層の実態
経済的に恵まれない母子家庭に育ち、高校・大学は奨学金を借りて卒業した。そのため、1000万円に迫る“奨学金という名の借金”を背負うことになった。そこで、郷里に母を残して上京、東京国税局の国税専門官となった。配属を希望したのは、相続税調査部門。「どうすればお金に悩まされずに済むのだろう?」と考え「富裕層のことを知れば、なにかしらの答えを得られるのではないか?」と思い至ったからだった。国税職員のなかでも富裕層が相手となる相続税を担当するのは、たった1割ほど。情報が表に出てくることはほとんどない。10年ほど携わった相続税調査で、日本トップクラスの“富裕層のリアル”に触れた『元国税専門官がこっそり教える あなたの隣の億万長者』(ダイヤモンド社)の著者が、富裕層に学んだ一生お金に困らない29の習慣を初公開する!

住宅ローンの償還期間や床面積、築年数などにより、節税効果の高い税金の特例を受けられなくなるケースがある。ちょっとした条件の見落としが、100万円単位で税額に影響する可能性もあるため、事前の確認が不可欠だ。

4月19日、相続税に関する注目すべき最高裁判決が下りました。訴訟の結果は国税当局側の勝利となり、訴えを起こした納税者は3億円を超える追徴課税を抱えることが確定しました。今回は、この判決が今後及ぼす影響について、元国税職員の視点から検証します。

コロナ禍も相まって、投資を始める人が増えてきました。手始めとしてiDeCoやNISAを勉強し始めた人もいるでしょう。老後資金を貯めながら節税できるのが、iDeCoの魅力です。ただし、iDeCoのしくみを知らないと、かえって損をしてしまうかもしれません。今回は、iDeCoに加入する前に知っておきたい注意点を解説します。

2021年も年末が近づいてきました。「ふるさと納税」の話題が気になる季節です。寄付をした自治体からの返礼品が魅力的なふるさと納税ですが、実は見落としやすい落とし穴があります。ふるさと納税で損をしないための注意点を解説します。

年末調整のシーズンですが、昨年から書式が複雑になっていることに気づいたでしょうか?これだけ年末調整が複雑になってしまうと、懸念されるのが、「正しく書ける人」と「正しく書けない人」との間に、税負担の差が生じる懸念があります。しっかりポイントを押さえてください。

第3回
親が亡くなる前に、口座凍結に備えて預金を引き出すと、相続税調査で目をつけられる可能性があります。その理由は何なのでしょうか。相続前の預金引き出しの注意点や、口座が凍結後に預金を払い戻してもらう方法を解説します。

第2回
相続税調査では、一見、相続税と関係しそうにないことも質問されます。その一つが、「故人の趣味」です。どのような意図でこのような質問がなされ、故人の趣味が相続税にどう関係するのでしょうか。

第1回
国税庁が発表した文書によると、税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)に向けた計画が進められている。税務調査にAI・データ分析が活用される構想も示されているが、未来の相続税調査はどうなるのだろうか。

住宅ローンの償還期間や床面積、築年数などにより、節税効果の高い税金の特例を受けられなくなるケースがある。ちょっとした条件の見落としが、100万円単位で税額に影響する可能性もあるため、事前の確認が不可欠だ。

#16
便利なクラウド会計ソフトが登場したことで、帳簿作成や確定申告をスムーズに行えるようになった。しかし、意図せずに処理を誤ってしまうリスクもあるという。クラウド会計ソフトで注意すべきポイントを解説する。