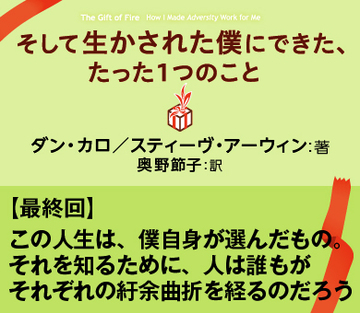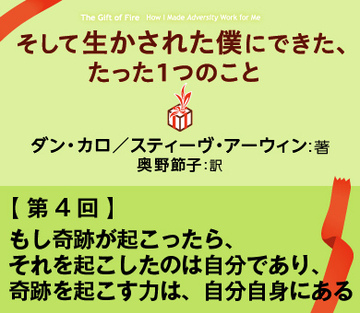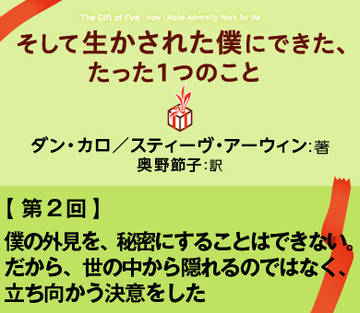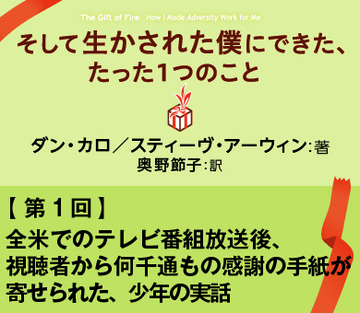「怪物」と呼ばれて
二人の兄は地元の学校へ通っていました。両親は僕も同じ学校へ入れるものと思っていましたが、学校の責任者は許可してくれませんでした。
僕の外見が他の子と違うというだけで、学習障害があるか、かなりのサポートを要すると決めつけていたのです。
両親は憤慨し、抗議のために兄をその学校から退学させたほどです。
両親は、僕を私立のテリータウン・アカデミーに入学させました。
そこは、もろ手を挙げて歓迎してくれました。
でも、クラスメートたちはそうではなかったのです。
幼稚園での経験は、最初から悲惨なものでした。
クラスメートの視線が僕の背中に突き刺さり、この時、僕は初めて敵意というものを身にしみて感じたのです。
初日以来、幼稚園へ行くのを考えるたびに、身がすくんでしまいました。
でも、両親には話せませんでした。子どもたちの自分に対するまなざしを恥ずかしく思い、それを両親に悟られたくはなかったのです。
結局、すべてを胸の中に押し込んで、誰にも打ち明けませんでした。
教室でいかにつらい思いをしようと、それは、休み時間に園庭で受ける拷問に比べれば、何でもありませんでした。
園庭に出ていくと、僕はたくさんの子どもたちに囲まれ、辛らつな言葉を浴びせられました。
「醜い怪物を見ろよ!」
「おい、フランケンシュタイン!」
「地獄に戻れ、火傷(やけど)少年! お前と一緒なんて、まっぴらだ!」
来る日も来る日も、同じ悪夢の繰り返しでした。
迎えに来た母に、「幼稚園はどうだった?」と尋ねられると、僕はただ肩をすくめて、「まあまあ」とつぶやきました。そして、家に着くなり自分の部屋にひきこもって、何時間も、靴ひもを結ぶ練習をしたのです。
新しい親指がすりむけてしまうか、夕食の時間だと呼ばれるまで、ずっと練習していました。それでも、できるようにはなりませんでした。
やがて、僕は園庭に出るのをやめました。代わりに、休み時間のベルが鳴るやいなや、フェンスの柵の隙間から外へ出て、テリータウン・アカデミーの周りを歩くことにしたのです。
この幼稚園でいちばんの人気者は、キーランという少年でした。
キーランは、学年でいちばん背が高く、ハンサムで、おおらかな笑顔の持ち主でした。さらに、スポーツ万能で、走るのがとても速かったのです。
彼の周りには、いつもたくさんの子が集まっていました。威張ることも、他の子に無理強いするようなこともありませんでした。感じがよく、一緒にいると楽しいだろうと思えました。
いじめられている僕を助けてくれたことこそありませんでしたが、少なくとも僕をいじめたことは一度もありませんでした。
キーランと遊んでいる子たちを眺めながら、仲間に入れたらどんなに楽しいだろうと、よく思っていたのです。
でも、実際にそうしたら、どうなるかは、よくわかっていました。たとえ一人ぼっちでも、あざけりを受けるよりはましなはずです。
幼稚園でも、家でも、自分の気持ちについては黙ったまま、積もり積もった心の痛みを隠し続けていました。
それは耐え難いもので、まさに惨めそのものの状況でした。
そんな時、突然、心が完全に開かれ、自分を超えるパワーを手にしたと感じたのです。それは、あまりにも強力なものでした。