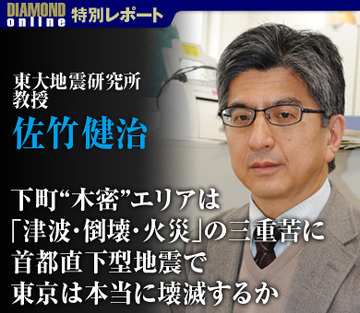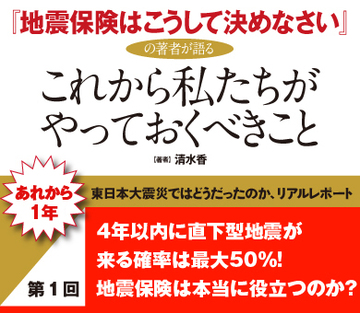第2章
6
翌日、首都移転チームは定時の30分前には全員がそろっていた。
チームを辞めて元の総務省に戻ったはずの千葉の姿もあったが、誰もなにも言わなかった。
この部屋はすでに片付けられているが、ここと緊急対策室以外の部屋は地震のときのままだ。
緊急対策室はどこの省庁も混乱が続いていた。特に国交省の混乱はひどくなっていた。
都内の交通、建物、インフラの被害状況がすべて国交省に送られてくるのだ。それを官邸を含め、各省庁に伝えなければならない。
それらは、改めて東京直下型地震が与えた被害がいかに様々な分野に及んでいたかを直視させるものだった。
同時に、政府の災害に対する脆弱性が露呈された形だった。
森嶋たちの首都移転チームにも人員派遣の要請があったが、意外にも村津はそのすべてを断わっているという話が聞こえてきている。
時間ちょうどに遠山と共に現れた村津は、部屋の正面に立った。
「このチームが結成されてすでに1週間がすぎた。先日の地震以来、政府を含め霞が関には混乱が続いている。しかし諸君はこの混乱に惑わされることなく、与えられた職務を粛々と続けてほしい」
誰もが拍子抜けする言葉だった。そもそも、与えられた職務とは何なのだ。
千葉が手を上げた。
「各省庁の緊急対策室は、猫の手も借りたい状況です。我々でも戦力になります。手伝いに行かせてください」
「人手不足はすぐに解消される。諸君はこの状況をよく見ておくんだ。我々の仕事の必要性を理解するほうが遥かに重要だ」
「もう首都移転の必要性はないでしょう。危惧されていた地震は、すでに起こりました。東京は安全です」
「地震ばかりが移転の理由じゃない。日本の抱えている多くの問題は、きみたちにも分かっているはずだ」
「その解決が首都移転だとは思えません。逆に、経済的な負担で圧迫されるだけです」
「その通りです。それに東京から首都を移すなど、1200万の都民が許すはずがありません」
「一度たち消えたプロジェクトが、すんなり復活するとは思えません。まず、国会審議が先ではないですか」
様々な声が飛び交い始めた。今まで押さえていた疑問と思いが一気に噴き出したのだ。