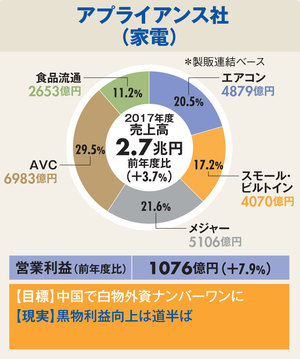
前項で紹介したように、先進的な取り組みも多いAP社。だが“巨艦”ならではの葛藤も大きい。
本間哲朗社長が就任する15年まで、家電部門は製造と販売が完全に分離され、それぞれ別個の営業計画を持つ組織として存在していた。全体を把握できるのは社長のみ。この体制は松下幸之助氏が1933年に事業部制を始めたときからなんと80年間続いた。はやり廃りの激しい家電市場においては信じ難い非効率な組織である。
本間社長の下でこれが統一され、事業全体の状況を把握できるようになったのは、つい最近のこと。100年前から存在する祖業であり“ド本丸”だからこそ残る、パナソニックの家電事業の特殊性を象徴するエピソードではある。
同様のことが、製品開発面にもいえる。アジャイル型開発の仕組みや外部と連携する仕組みを取り入れているのに、そこで得た尖った知見は、大量生産がベースの“本丸”にはなかなか届かない。
中国支社では、IoT対応の冷蔵庫などを現地で独自に開発して人気を博している。IoTの潮流は白物家電市場にも押し寄せている。そんな今、本来パナソニックが日本市場に投入しても全くおかしくないこれらの製品は、「市場調査を何度やっても絶対に売れないという結果が出ている」(本間社長)という理由で日の目を見ない。
新しいことを追う頭や目に、重い胴体がなかなかついていかない。AP社の自家撞着はパナソニックに共通する悩みの象徴でもあった。



