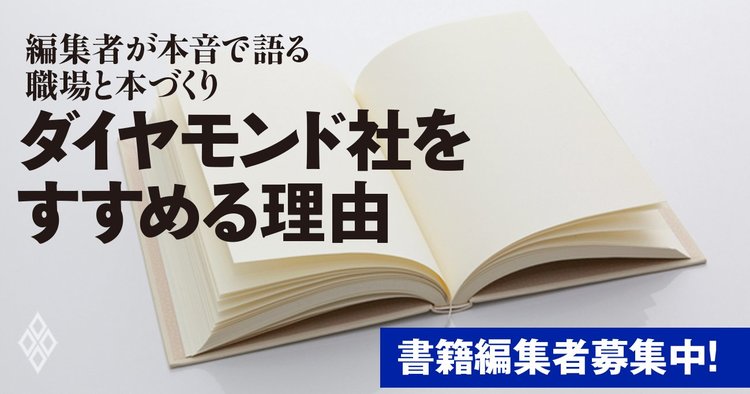
ダイヤモンド社の書籍編集局では、いま中途採用で編集者を募集しています(詳しい募集要項はダイヤモンド社の採用情報ページおよび「マイナビ転職」をご覧ください)。
そこで、現場の編集者たちに、職場の雰囲気、仕事内容、一緒に働きたい人物像などについてインタビューしました。ホンネ炸裂のトークをお読みいただき、我こそは!と思われた編集者の皆さまは、ぜひともご応募ください。応募〆切は「2022年6月6日(月)」です。
本記事では、入社からしばらくは売れる本が出せずに苦労した編集者・今野良介が、あるきっかけで連続重版の道を切り拓いたエピソードなどをご紹介します。
(→他メンバーのインタビュー記事および座談会記事も是非お読み下さい!)
「自由放任」だが
「当たり前の基準」が高い職場
──中途入社してどのくらい経ちましたか?
今野良介(以下、今野) 2015年2月入社なので約7年2ヶ月です。
 書籍編集局第1編集部
書籍編集局第1編集部今野良介(こんの・りょうすけ)
大学卒業後、他の出版社を経て2015年入社(入社時31歳)。担当書籍は『読みたいことを、書けばいい。』『0メートルの旅』『会計の地図』『お金のむこうに人がいる』『会って、話すこと。』『タイム・スリップ芥川賞』『システムを「外注」するときに読む本』『落とされない小論文』『1秒でつかむ』『子どもが幸せになることば』など。
──当時、なぜダイヤモンド社に転職しようと考えたんですか?
今野 僕は前職でもビジネス系の書籍をつくっていたんですが、そのジャンルでダイヤモンド社はすごく存在感があったんです。優秀な編集者もいっぱい集まっていたし、当時はビジネス書界のレアル・マドリードみたいだなと思っていました。いつか挑戦したいと思っていて、たまたまその頃、結果も出始めたので、チャレンジしてみようと決めたんです。
あとは、やっぱりベストセラーを出したい気持ちが強かった。ダイヤモンド社の編集者って、「読者の最大値をいかにつかむか」を考え抜いて本をつくっているイメージがありました。編集者の意欲というか、山っ気が強い。そういう人たちの中に身を置けば、売れる本づくりが学べるだろうし、何より自分が楽しいだろうと思いました。
それから、金銭面もありましたね。結婚して子どももできたので、先々のことを考えると、やりたい仕事をしながら経済的にも安定する環境は大きな魅力でした。
──入社前にダイヤモンド社に対して不安に思ったことはありますか?
今野 けっこうよく書籍編集者を募集していたので、部署の人材流動性が高いのかなと、入る前は不安でした。ほんとうにレアル・マドリードだったら、結果が出せないと即ハネられるじゃないですか(笑)。それと同じじゃなかろうかと。結果に対するプレッシャーを勝手に妄想して、それが過剰に肥大化してましたね。実際は、書籍事業が好調なので単純な業容拡大だったみたいです。最初の2年くらい売れる本が出なかった僕もクビにならず無事でしたから、応募を検討している方はご安心ください。ほんとうに。
──実際に入社してみて、書籍編集部門はどんな点が印象的でしたか?
今野 やっぱり皆が結果を出していることです。ベストセラーが当たり前のように次々と出る環境には本当にビックリしました。当時、リブセンスの村上太一さんという人が「当たり前の基準を上げろ」と言ってたんですけど、他社からやってきた身からすると「当たり前の基準が高すぎるだろ」と。でも、その分、自然と自分の目標も高くなるので、それは良いことだと思っています。
──上司のマネジメントについてはどう感じましたか?
今野 転職者が多いからかもしれませんが、個々の編集者のやり方を尊重する上司が多いです。自由放任で、縛りが少ない。「こういう本をつくりなさい」と指示されることは、ほぼないです。編集者がやりたい企画に対して、「どうすれば、より質を高めて売れるようにできるか?」を一緒に上司が考えてくれるイメージです。
──自由放任ということですが、上司から編集上のアドバイスはあるんですか?
今野 もちろんあります。ダイヤモンド社では、編集長も副編集長もプレイング・マネジャーなので、つくってきた本の経験に基づいてアドバイスしてくれます。「なぜ、この企画を考えたのか?」「なぜ、このコピーにして、なぜこのタイトルなのか?」「そもそもなぜ、この著者を選んだのか?」など、こちらから聞けば、いつでも何でも教えてもらえます。過去の話ではなく、いま現役バリバリでやっている先輩編集者たちに直接聞ける点は、とてもありがたい。面白いのは、人によってアドバイスの視点がまったく異なることです。たとえばある上司は、コンセプトや市場ニーズより先に「お前は本当にこの著者を愛しているのか?」という話から始める。ところが、別の上司はすごく理詰めで編集スタイルがまったく違う。そういった多様性も魅力ですね。
「自分起点」の企画立案が
売れる本づくりへの転機
──では、ダイヤモンド社に入って最も良かったことは何ですか?
今野 難しいな(笑)。単純なことをいえば、名刺一枚で「あ、ダイヤモンド社ですか」って色々な方が会ってくださることですね。編集実績のない若手でも、何者でもないわたしでも、会いたい人に会えるチャンスがあるというのは、それだけで大きなメリットだと思います。つまり色々なことに挑戦しやすい。先輩たちが築き上げたこのブランド力にはどんどん乗っていこうと思っています。
あとは、企画の出発点が変わったのが良かったですね。以前は、「市場で求められる企画が何か?」を考え、それに合う本をつくろうとしていました。いわゆるマーケットインの発想です。今は、自分が読みたいテーマや、自分が面白いと感じた人がいたら、それをいかに世に広めるかという観点から企画を立てるようになりました。つまり発想が「自分起点」に変わったわけです。
──そのように変えたのはなぜですか?
今野 先ほども言いましたが、僕は入社して2年以上も結果が思わしくない状態が続いたんです。自分としては良い本をつくったと思っているのに、結果につながらない。本気で苦しくて、社内で息をするのもツラい状況でした。別に本が売れなくても咎められるわけではないし、周りの環境は変わらないのですが、それが一層ツラい(笑)。完全に自分の問題なんですが。とにかく、売れる本づくりについてずっと悩んでいました。
転機は、2017年6月に出した『システムを「外注」するときに読む本』です。これは、システム開発を「頼む側」の勘所をストーリー形式で370ページもかけて解説するという、ちょっと異常な本なんですが、自分がシステム発注者だったら読みたい形式はこれだと思って、2〜3年かけて好きなようにつくりました。すると良い結果が出たんです。となれば、そっちのやり方のほうが圧倒的に楽しいじゃないかと。
──それ以降、担当書籍が13冊連続重版したんですよね。2019年6月に出た『読みたいことを、書けばいい。』が16万部、 近刊『お金のむこうに人がいる』も現在3万部超と好調です。企画の出発点のシフトがここまで功を奏すると思っていましたか?
今野 いや、全く想像していませんでした。発想を変えたのは、最後の「開き直り」でしたから。市場ニーズに合わせて本をつくってもなかなか結果が出なかった。だったら自分が読みたい本に仕上げてみようと。「読みたい本を、つくればいい。」という姿勢です。あくまで現時点での話ですが、それが僕の編集者としての仕事観です。そこからスタートすれば、何より制作過程が楽しいし、つくったあとの売るフェーズでもモチベーションが上がります。もちろん、市場ニーズを追求して成功している編集者もたくさんいますし、それができる編集者はほんとうにすごいと思いますが、僕の場合は、そういう転機がありました。

「売れなかったら自分のせい」
と編集者に思わせる営業への信頼感
──編集と営業の関係性についても教えて下さい。
今野 本が売れなかったときに、「自分の力不足だったんだな」と編集サイドが思えるような関係性ですね。編集者って、本が売れないと、つい「営業がこうしてくれれば売れたはずなのに」と考えられる逃げ道がある仕事だと思うんです。でもうちの場合、営業がデータを実に精緻に見ていて、売れ始めた本を売り伸ばす力がすごい。だから「営業のせいで売れなかった」が言いにくい(笑)。その意味で、ちゃんと売れる力を持った本がつくれるかが編集者には問われます。
──営業に責任転嫁はできないと?
今野 そうですね。そこはダイヤモンド社に入ってよかったことでもあり、厳しいところでもあります。ただ、だからと言って編集と営業の関係がドライなわけではなく、連携はとても良好で、相互信頼も厚いです。
たとえば、ダイヤモンド社の場合、新刊は火曜日配本で週末までの動きを見て増刷を決めるんですが、そのときも紀伊國屋PubLine、インテージ、トリプルウィン、amazon等々のデータを隈なく調べ、どこでどう売れているかをしっかり見極めたうえで営業が判断します。過去のデータに基づいた分析をもとに、「その本の売れる可能性がどこまであるか」を見出してくれる。そのうえで、どんな書店で展開すべきか、売れる時期はいつかといった情報を集め、それを書店さんの棚に反映してくれる。本を売るためのベクトルが、編集と営業で一致しているんだと思います。これは、編集者としてとてもありがたいことです。
──最近は刊行ジャンルも多岐にわたっていますが、それも刺激になりますか?
今野 当然、刺激になります。たとえば女性実用書とか児童書ってダイヤモンド社ではほとんど出していませんでしたが、そこを攻める編集者が入ってきて、ベストセラーが次々に生まれています。「新しい人がくることでジャンルが広がる」という良い循環がある。それは明らかにプラス要素です。だったら自分も「昔からやりたかったこれをやってみよう」とか「以前は企画が通らなかったけどダイヤでならできるんじゃないか」という野望も湧いてくる。新ジャンルへの参入や、著者のデビュー作に非常に積極的な営業の存在も、心強いです。
つくり込んだ企画書を
ていねいに議論する編集会議
──編集会議での企画の検討についても教えて下さい。

今野 うちの特徴は、最初からかなり詳細に内容を詰めた企画を編集会議に出すことだと思います。僕を含め、中途で入った人の多くが「ここまでつくり込むのか」と驚いています。でもそれは、「詳細な企画書じゃないと通らない」というプレッシャーがあるということではなく、どうしてもやりたい企画が通せると思うからこそ、各編集者が細部まで熱のこもった企画書を書いているということです。通らないかもしれないと思えば、ふわっとした段階で出して感触を探ろうとする。でもうちは基本的に「やりたい企画はやらせてみよう」という文化なので、コンセプトをしっかり練って、自分なりにイメージが固まってから企画会議に出すことが多いのではないかと思っています。
そして、もう一つの特徴は、会議で一つの企画を検討する時間が非常に長いことです。最初は驚きましたが、いまは存分に活用させてもらっています。本の企画って最初の方向性がいちばん大事だと思います。著者選定にしても、コンセプトにしても読者対象にしても、いちど決めてスタートしたら、原稿をもらってから軌道修正するのはすごく難しい。だから、最初の段階でしっかり揉んでもらえるのはすごくありがたいです。
──これまでの本も自分起点でしたか? そして、これからはどんな本を出したいと思っていますか?
今野 お陰さまで『読みたいことを、書けばいい。』は代表作になりましたけど、その前に出した『1秒でつかむ』や『子どもが幸せになることば』『0メートルの旅』、『会計の地図』、そして近刊の『お金のむこうに人がいる』『タイム・スリップ芥川賞』なども、自分がつくりたくてつくった本だと100%言い切れます。これからもそういう本を出していきたいと考えています。
直近では、「嘘」をテーマにした本と、小学生教育の本をつくっています。今、もっとも興味があるのが嘘と自分の子どものことなので、同じく自分起点ですね。どちらも新しい視点を提示する本になりそうで、他社からも出ていない内容なので、ベンチャー的な楽しみがあります。
ベンチャー精神あふれる人よ来たれ!
──では最後に、どんな人に入社してほしいか教えて下さい。

今野 自分がやりたいことや守りたいことを、強い意志をもって本づくりにつなげられる人。そして、フラットに話ができる人ですね。対等な目線で話ができるって、すごく重要です。うちの書籍編集局は上下関係を感じることが本当に少ない会社で、もちろん組織としてのポジションはありますけど、妙なしがらみはない。だから生身の自分で勝負したいと思っている人に来てほしいと思います。そういう人なら存分に羽ばたける場所じゃないかと。周りの人を見ていても、そう感じます。
それから、先ほどの話じゃないですけど、ベンチャー企業に行きたいなら、うちはおもしろいと思います。編集も「ものづくり」ですから、自分が良いと思ったものがどれだけ社会に受け入れられるかを証明したい気持ちがあるならば、絶対楽しいと思います。ダイヤモンド社にはそれを実現できる環境があります。「ベンチャー精神あふれる人よ来たれ!」です。
(終わり)
※具体的な募集要項はダイヤモンド社の採用情報ページをご覧ください。また「マイナビ転職」にも詳しい情報が掲載されています。
※本記事以外にも、書籍編集部メンバーのインタビュー記事や座談会記事がお読み頂けます(記事一覧はこちら)。いずれも、職場の雰囲気や仕事内容を本音炸裂で語っています!





