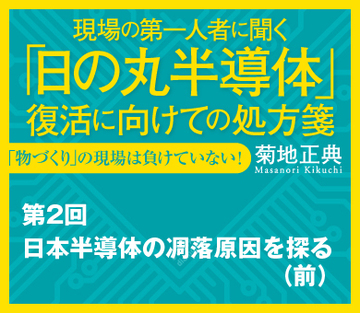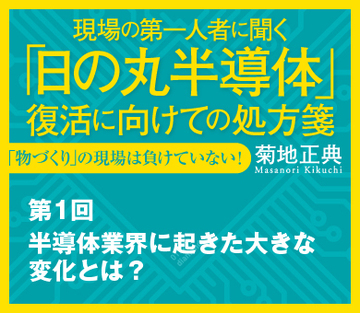日本の半導体企業の苦境が続いている。エルピーダメモリの会社更生法申請につづき、ルネサス エレクトロニクスは1万人超の人員削減を発表した。その凋落の原因については、すでに学会やジャーナリストなど各方面から分析がなされているが、今回は、40年にわたり半導体研究・開発に携わってきた、産業サイドの第一人者とも言える菊地正典氏の分析と提言を紹介する。
〈4〉 半導体部門の悲哀
──総合電機メーカーにとっては「新興・一事業部門・異端児」
半導体業界では過去40年近くに渡り「シリコンサイクル」と呼ばれる、ほぼ4年ごとの好不況の周期的な景気変動を経験してきました。いっぽう市場そのものとしては中長期的に見れば高い成長率を維持していますので、半導体企業にとっては「投資のタイミング」が死活問題になりかねないほど重要になります。すなわち、「不況時に設備投資を断行し、生産能力を上げておき、景気の上昇に合わせて一挙に生産数を上げる」ことで高い市場シェアを握ることができる産業構造なのです。
しかし、日本の大手半導体メーカーは日立にしろ、NEC、富士通にせよ、「総合電機メーカーの1つの事業部門」に過ぎないため、アグレッシブな投資戦略が取れませんでした。全社の中で半導体事業は、重電、通信、コンピュータ、あるいは原子力といった、それまで会社の屋台骨を支えてきた既成事業部門に対し「新興勢力的な立場」に置かれていました。
また半導体はエンド・ユーザーに直接わたる最終製品ではなく、あくまでも電子機器の部品に過ぎないという意識も強かったと思われます。そのため半導体事業部門と社内ユーザーでもある他事業部門の間には、新製品開発や汎用品の供給に関して、実務的あるいは心理的な対立や葛藤が起きることも、じつは稀ではなかったのです。
他部門から見れば、半導体は好況時には非常に売れる反面、不況時の落ち込みもまた大きく、いわば金食い虫の「異端児」と受け取られていたとも言えます。このような状況下では、不況時にあえて何百億円以上という大型投資をするだけの勇気をもつ経営トップは皆無だったのです。
その点、海外の半導体専業メーカーの場合、会社トップは半導体ビジネスの特徴を当然、よく理解し、大胆かつ適切な手を打てたのです。