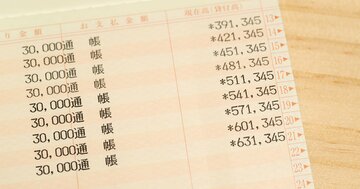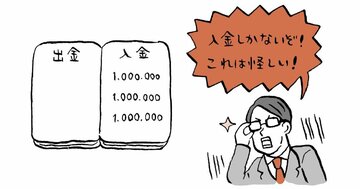『週刊ダイヤモンド』1月16日号の第一特集は「夫婦の相続」です。約40年ぶりの民法大改正、税制改正による増税、そして超高齢社会の到来や家族観の変容など、相続を取り巻く環境は激変しています。従来の制度や価値観では解決が難しい事例も増えていますが、これからは、自分のことだけでなく、「夫婦」単位で相続を考えるのが、家族円満のためにも、節税のためにもお得といえそうです。(ダイヤモンド編集部 野村聖子)
80代後半から90代での死亡が最多
残された妻の老後は長い
 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
人間は生きている限り、現金や住む家などが必要だ。誰もがその死に際して、必ず何かしら「遺産」を残す。だから、家族のことであれ、自分のことであれ、いつか相続の当事者となる日が来るのは、今も昔も変わらない。
しかし、日本はかつてない超高齢社会に突入し、相続の現場ではこれまでにはなかった問題が起こり始めている。
いまや亡くなる人の多くが80代から90代だ。一般的な男女の夫婦では、夫の死後、妻が10年以上生きることも決して珍しいことではなくなった。
そのため、これまでは子どもに引き継ぐことを主に考えればよかった相続が、妻の長い老後も見据えたものに変わらざるを得なくなったのである。