非正規はへつらわないと
正規になれない圧力
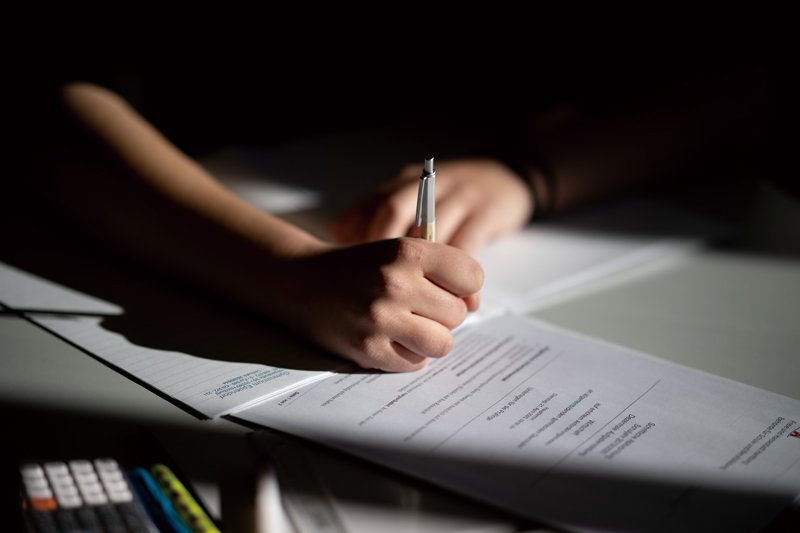 Photo:picture alliance/gettyimages
Photo:picture alliance/gettyimages
学校の労働問題に詳しい労組関係者E 若者の視線で言えば、非正規雇用の教員が増えており、組合がその受け皿にどれだけなっているのかというのも大事ではないですか。今の私立学校では、卒業後にストレートで専任(正規職員)になれる道は細くて、4割が非正規雇用。正規雇用というニンジンをぶら下げられながら働き、合理的な理由もなく雇い止めされて学校を転々としています。
教師C うちの組合は、ハラスメントがあってもすぐに辞めないように相談を受けたり、職能を身に付けて正規の登用試験に受かるようにサポートしたりしている。そうした経験を経た教師は、非正規の人たちに対する良いまなざしを持っていますから、一緒に非正規の問題に取り組んでくれる。そういう戦略でやっています。
教師B 若い非正規教師は、常にへつらっていないと正規になれないなっていう圧力を感じていると思います。校長の推薦があれば正規になりやすいですから。
教師C 教師のブラック問題の構造って、この座談会で出てきた昇給の査定だとか、非正規から正規になれるか否かとか、そういうところでしっぽ振り競争をするような構造が出来上がっている。特に非正規教師はしっぽを振らないとご飯を食えないから、いやが応でもなびいて、無理して働かざるを得ません。
労働組合はそれに対して力を発揮できているかというと、うまくできていない感じがします。
労組関係者E 正規だと年功処遇で安定しているけれど、非正規は同じ仕事をしているのに年収で200万円ぐらいしかもらえなかったりする。若い世代が切実なのはそういうところにあります。ここの受け皿になるのが労働組合を再生するきっかけにもなるんじゃないでしょうか。







