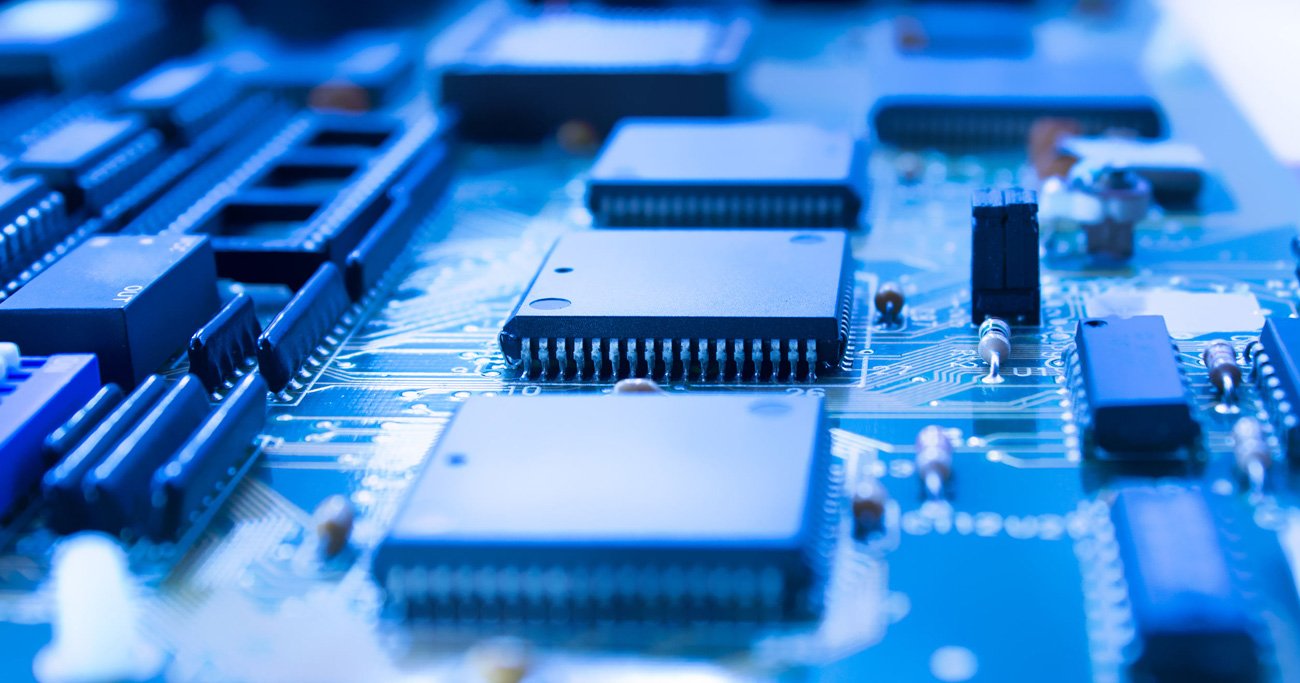 Photo:123RF
Photo:123RF
半導体大手メーカー米インテルが、台湾積体電路製造(TSMC)の次世代製造技術を採用する見通しだ。これは半導体業界にとってTSMCがインテルに代わって盟主の地位に立ちつつあることを意味する。世界経済全体、さらには中国と米国、台湾を含めた世界的な安全保障の問題にも重要な影響を与えることになる。(法政大学大学院教授 真壁昭夫)
インテルがTSMCの技術を採用
半導体業界の「盟主」交代
半導体大手メーカー米インテルが、台湾積体電路製造(TSMC)の次世代製造技術を採用する見通しと報じられた。これまでインテルが重視してきた自社生産に加え、外部への生産委託に乗り出さざるを得なくなったということだろう。
かつて、インテルは米国の半導体産業のトップ企業だった。世界の半導体業界の行く末を決めるような企業だったのである。そのインテルがTSMCの最先端技術を用いることは、世界の半導体業界にとってTSMCがインテルに代わって盟主の地位に立ちつつあることを意味する。世界の半導体業界の勢力図だけではなく、世界経済全体、さらには中国と米国、台湾を含めた世界的な安全保障の問題にも重要な影響を与えることになる。
やや長めの目線で考えると、高度な暗号技術などの実現を目指して、米中は量子技術の開発を強化するだろう。量子技術に対応したチップ生産に関しても、両国がTSMCをより重視する展開は十分想定できる。IT先端分野で米中対立の先鋭化が想定される中、わが国企業は台湾や米中から必要とされる微細な素材などの創出力に磨きをかけなければならない。それが国際世論におけるわが国の発言力や、経済的な存在感の維持に不可欠だ。







