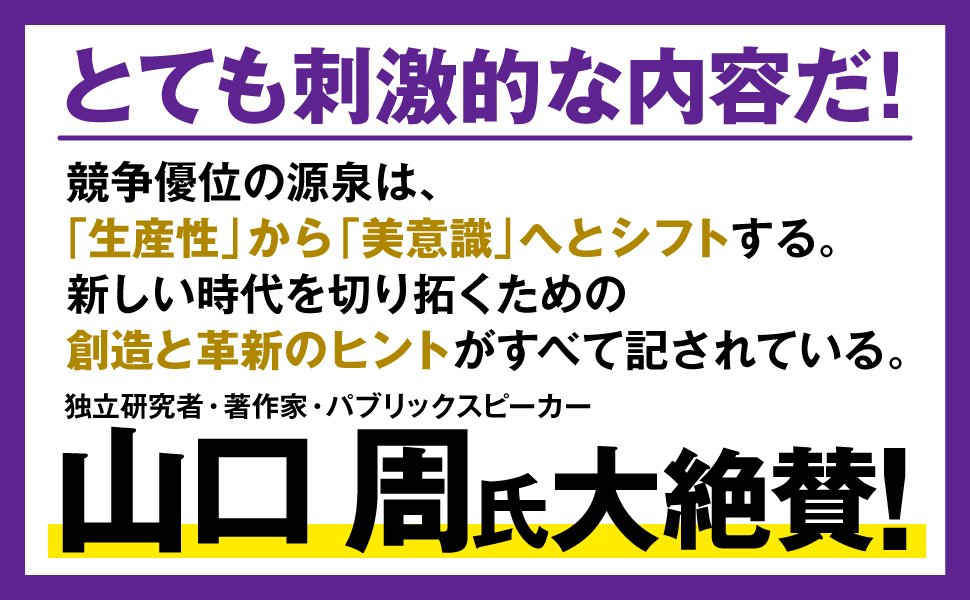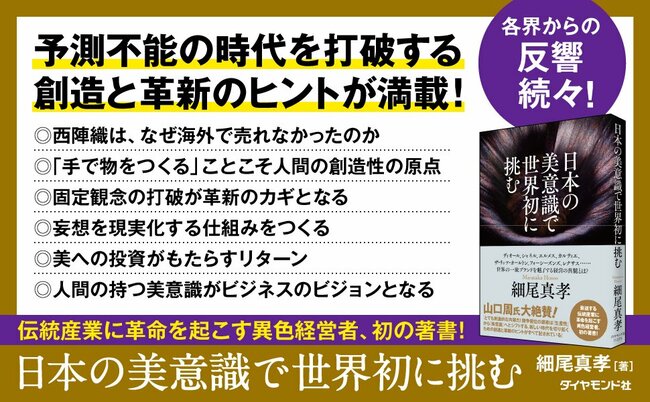西陣織の帯が、クリスチャン・ディオールの
インテリアに変化
 秋元氏と細尾氏
秋元氏と細尾氏
秋元 話は戻るけど、西陣織を海外に展開することで、自分も何かかかわれるかなという思いはあったの?
細尾 そうですね。やっぱり創造的なことをしたいというのはありました。家業の西陣織は、自分の中ではコンサバティブ(保守的)でクリエイティブ産業には入っていなかったんです。でも海外に展開することで、西陣織がクリエイティブ産業として展開できるんじゃないかと。
秋元 伝統工芸に限らず一般的な話として、古くから続く企業や日本社会そのものにあるコンサバティブな社会の仕組みって、なかなか打破できないじゃない。成長しない時期が長く続いていても、旧体制というか、古い仕組みがそのまま温存されてしまう。細尾君の場合、家の中に自分が乗り越えなきゃいけない相手がいるわけで、そこはどうだったの?
細尾 最初は、放蕩息子が戻ってきて会社はもう終わったな、みたいな雰囲気でしたね(笑)
秋元 そうなんだ。それで海外の人たち点に対しては、どのへんで最初の引っかかりがあったの? たとえば、物のクオリティに感動したとか、ブランディングが当たったとか、プレゼンの仕方が良かったとか…。
細尾 西陣織が伝統的に持っていた「素材」と「技術」が、一つのきっかけになりましたね。
秋元 やっぱり物の力なんだ。
細尾 そうなんです。ただ偶然というか、2008年12月に、パリの装飾美術館で日仏交流150周年を記念した展覧会「kansei-Japan Design Exhibition」という「日本の感性価値展」があり、国から依頼を受けて、琳派柄の帯二本を出品したんです。あくまで展覧会ですので、ビジネス目的の展示会・見本市とは違い「いろんな方に西陣織を見ていただけたらいいな」という軽い気持ちでした。展覧会は非常に好評で、翌年ニューヨークで巡回展が行われまして、それが終わった直後にメールが来たんです。「その帯の技術と素材を使ったテキスタイルの開発を依頼したい」と。それがピーター・マリノという世界で5本の指に入るほどの建築家でした。クリスチャン・ディオールのプロジェクトで、今、旗艦店のリニューアルを手掛けていると。
秋元 やっぱりクリエイターのクリエイティビティをはじめに理解するのって、別のクリエイターなんだよね。
細尾 そうですね。しかも海外という。
秋元 そうそう。
細尾 それで、ピーター・マリノ氏からまず送られてきた絵が、和柄ではなくて鉄の溶けたような柄だったんです。これまで私たちは「和柄でないといけない」と思い込み、西陣織を使ったクッションなんかを作って展示会などに出品してきました。でも求められたのは、和柄でも物でもなかったんです。
秋元 それはすごいね。
細尾 「日本は和柄」という固定観念を持っていて、それが勝負ポイントだと思っていたところが、海外のニーズは全然違いました。1年をかけて150cm幅が折れる織機から開発して、世界中のクリスチャン・ディオールの店舗で、壁、椅子、ソファーなどに西陣織が使われました。現在は、シャネル、エルメス、カルティエなどの店舗へも広がっています。
つづく