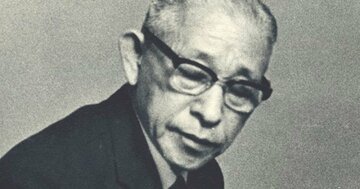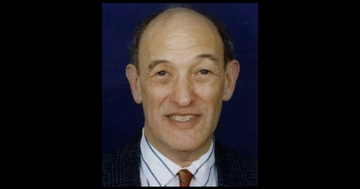1位は松下幸之助
日本を家電王国へと牽引した「経営の神様」
【松下幸之助(まつした・こうのすけ】
1894年、和歌山県生まれ。16歳で大阪電灯(現・関西電力)に入社、簡単に電球を取り外すことができる電球ソケットを在職中に考案。1918年、松下電気器具製作所(のちに松下電器産業に改称、現・パナソニック)を創業。1946年、PHP研究所設立。1979年、松下政経塾設立。1989年没。
カラーテレビ、クーラー、冷蔵庫、洗濯機…、人々が「ようやく豊かになった」と実感できたのはこうした家電製品が普及したことが大きい。家電は戦後日本の復興の象徴だったのだ。そして日本を世界に誇る家電王国にまで牽引した立役者が、松下幸之助である。
僕が松下さんと最初に会ったのは、1980年、ちょうどバブル経済が始まる前のことだ。僕は松下さんにおもに2つのことを聞いた。
ひとつは、役員や関連会社の社長、あるいは後継者を抜てきするのに、その人物のどこを見て決めるのかということ。なぜならその数年前に、松下さんは後継者として山下俊彦氏を抜てきしていた。山下さんは26人中25番目の取締役であり、大抜てきだ。僕は、何を決め手にこうした思い切った人事をしたのか、ぜひ聞いてみたいと思っていた。
「頭の良さですか?」と聞くと、まったく関係ないと。私は尋常小学校を4年で中退し、中学の受験にも失敗している。それでも会社を経営することができたと言う。
「では健康ですか?」と聞くと、それも関係ない。「自分は20歳のときに肺病を患い、いまだに治っていない。そのため陣頭には立てず、みんなの後ろからついていく」と。
「では誠実さですか?」と聞くと、それも関係ないという。社員が誠実になるか不真面目になるかは、経営者次第であり、社員が誠実ではないのは経営者の責任であるという。
頭の良さも、健康も、誠実さも関係ない。では、何を基準に選んでいるのですかと聞くと、「難しい問題にぶつかったとき、悲観するのではなく、それをむしろおもしろがってどんどん立ち向かっていける。何事も前向きに取り組める人間。そういう人間を、私は抜てきします」と言った。それを聞いて僕は、その通りだと、とても感動した。人間の生き方というのを教えてもらった気がした。
もうひとつは、経営者としてもっとも重要な役割は何か、と聞いた。すると、「全社員がどうすればモチベーションを持てるか、やる気を出せるか、これが経営者のもっとも重要な役割だ」と言った。彼のこうした考えは、その後の日本的経営の礎となった。
松下さんの日本的経営というのは、実は日本で共産主義が広がらなかった理由のひとつでもある。(経済学者の)マルクスは、資本主義というのは、いかに従業員を安く使うか。「(従業員の)労働力の商品化」といった表現をしているけれど、このように使われると従業員はいつかは爆発してしまう。だから資本主義社会では革命が起こる。こういったことを言っている。
だけど松下さんの日本的経営は、たとえば、20代や30代までは経営者に使われるが、その後は、係長、課長、部長、役員、社長と、使う側になっていく。こうした役職を従業員に与える。だからマルクスの資本論は日本ではまったく通用しない。そのためにみんながやる気を出して、奇跡といわれる高度経済成長を遂げた。
でも今は、こうした日本的経営がむしろ日本をダメにした要因にもなっている。従業員は偉くなるために経営層から気に入られようと、ベンチャー精神を持たなくなった。代表的な例がインターネットだ。1990年代にアメリカでIT革命が起こった時、日本企業は上の言うことを聞くばかりで導入できず、世界の潮流に乗り遅れてしまった。
また、僕は40〜50代の頃は多くの大企業に取材したが、社内で大きな仕事をやり遂げた人というのは、出世しても多くが「常務止まり」であることがわかった。大仕事をするにはどうしても社内で敵が生まれる。でも社長に選ばれるのは、社内に敵を生まないような温厚な人だ。戦わない人が経営者になるということは、守りの経営となる。
ベンチャー精神の欠如と守りの経営――。この30年間、日本経済は成長ができなかった。松下さんであればどうしていただろうか。
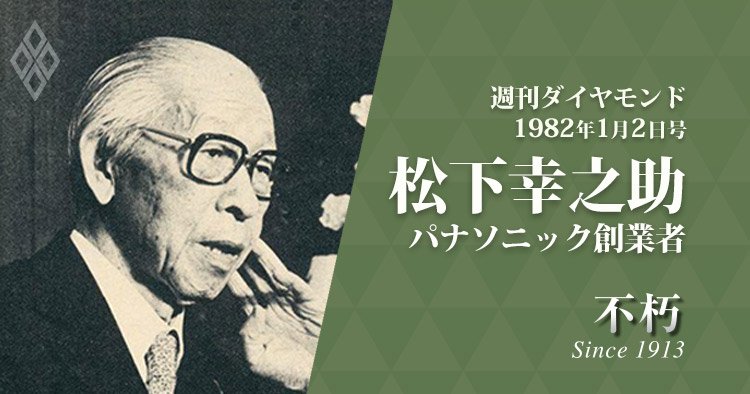 【深掘りしたい人はこちらも読んでみよう!】
【深掘りしたい人はこちらも読んでみよう!】週刊ダイヤモンド(1982年1月2日号)の松下幸之助氏へのインタビュー
松下さんは1979年、人生の終盤に「松下政経塾」を立ち上げた。当時、田中角栄の金脈問題が大スキャンダルとなり、政治と経済は大混乱に陥っていた。このままでは日本はダメになる、しっかりとしたリーダーをつくらなければいけない――。こうした思いが松下政経塾へとつながったのだ。
松下さんが直接、私に電話をよこしたことがあった。松下政経塾の立ち上げに当たっていろいろと話を聞かせてほしいという。当時、松下さんは80代、「経営の神様」といわれるほどの日本を代表する経営者だ。その松下さんが、40代でほとんど無名に近い状態の僕の話を、2度にわたって合計3時間以上もじっくりと聞いていたのだ。
「今の政治の何が問題なのか」「田中角栄さんや中曽根康弘さんについてどう思うか」などなど、具体的に聞かれて、僕は若気の至りで勢いのままに語ったが、松下さんはつねに熱心に耳を傾けてくれた。そしていろいろなことを話してくれた。大きな声ではなく、落ち着いた静かな声だ。ひとつひとつの話が、苦労した経験からの深い洞察に裏付けられた説得力のある話で、学ぶことが非常に多かった。今でもその時の光景を鮮明に思い出す。
優れた経営者の共通点からみる
リーダーに必要な資質
盛田昭夫さんもそうだったが、松下さんも人の話を聞くのが非常にうまかった。「聞き上手」というのは、裏を返せば、好奇心が強いということであり、また、謙虚に学ぶ姿勢を持っているということだ。これまでいろいろな経営者や政治家の取材をしてきたが、優れたリーダーには聞き上手な人が多かった。好奇心が旺盛で、誰からも謙虚に学び取ろうとしていた。その反対に、傲慢(ごうまん)な経営者の会社は、業績を悪化させていた。
「すでに世の中に存在するものを質を高めて売る」松下幸之助と、「まだ世の中にないものを商品化して販売ルートも開発する」盛田昭夫。まったく別のタイプであり、日本を代表する経営者2人が、ともに「聞き上手」であったというのはおもしろい一致である。この資質がリーダーにとっていかに重要なポイントであるかを表していると思う。