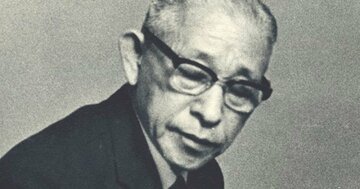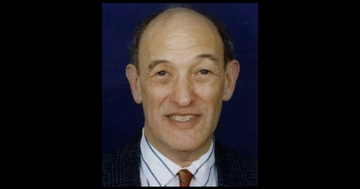0→1で製品をつくり、
0→1で販売ルートを開拓した
ところが松下電器の担当者は、厳しい価格を要求してきた。価格を上げてもらおうと交渉するが、「赤字か黒字かはそちらの問題です。私たちはこの値段でなければ買いません」の一点張り。
しかしここでも稲森さんはあきらめなかった。日本における松下電器の信用力は非常に高い。松下電器が買えば、他社も買うはずだ。そう考え、徹底的に業務の合理化・効率化を進め、松下電器に販売した。
稲盛さんの予想は的中した。日本中の会社が京都セラミックの製品を買いに来るようになったのだ。彼は人脈や癒着による商取引に一石を投じ、技術力と製品力で勝負した。海外へ渡り、ゼロから販売ルートを開拓した。ソニーの盛田昭夫さんのように、製品も販路も開発したのだ。
彼がすごいのはそれだけではない。それまでの企業は、とにかくもうかればいいという考えが多かった。しかし稲盛さんは、企業というのは損得だけではない。ユーザーあってのメーカーだ、社会あってのメーカーだ。ユーザーと社会に信頼されなければメーカーはやっていけない。「利他の心」が大切だ。こう言っている。まさに今の時代、そしてこれからの時代に適した経営精神だ。「稲盛教」と呼ばれるほど熱狂的なファンが多い。
1980年に彼と会ったときは、京都セラミックはすでに社員数3000人の大企業となっていた。「私は実は極めて臆病で、それまでの人生は挫折の連続でした。私の場合、この臆病と挫折とが肥やしになったと思います」と語っていたことが印象的だ。
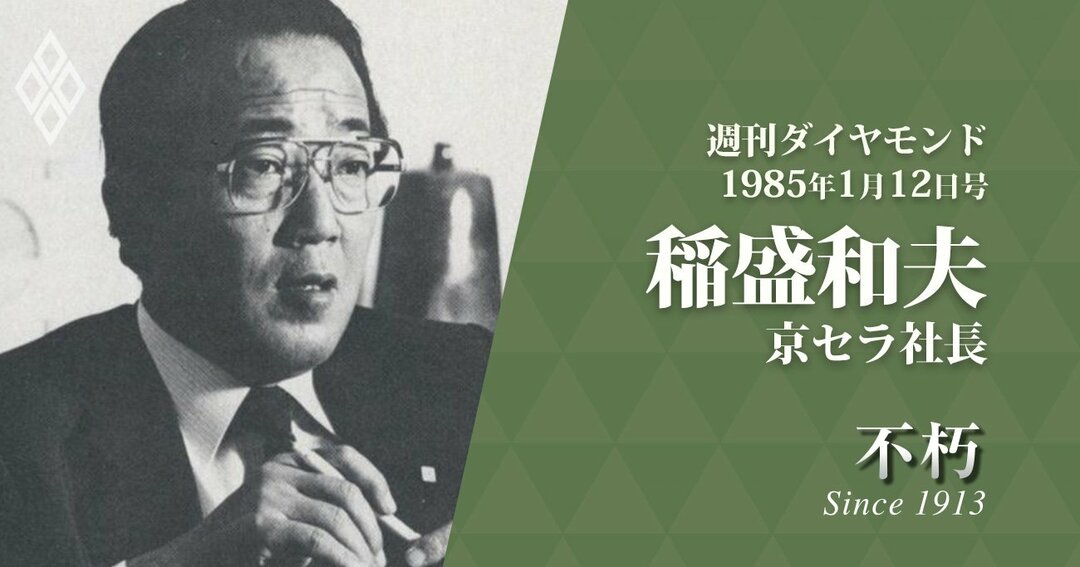 【深掘りしたい人はこちらも読んでみよう!】
【深掘りしたい人はこちらも読んでみよう!】週刊ダイヤモンド(1985年1月12日号)の稲盛和夫氏へのインタビュー
僕はこれまで、非常に多くの政界人や財界人と会ってきたが、彼らに共通することは、どんなときでもマイナス思考にならないことだ。臆病でも挫折しても、つねに前向きに考える。稲森さんもまたそうだった。
「世の中に失敗というものはない。チャレンジをあきらめたとき、それを失敗というのだ」――。
稲盛和夫さんの言葉である。
3位は中内功
ダイエーを創業、消費者主体の流通へと革命を起こす
【中内功(なかうち・いさお)】※「功」は正しくはつくりが「刀」
1922年、大阪府生まれ。1957年、「主婦の店ダイエー薬局」(ダイエー1号店)出店。消費者主体型の流通システムの構築など、日本の流通に革命を起こす。1964年、テレビの値引き販売をめぐって「ダイエー・松下戦争」が勃発。30年にわたり、松下電器産業(パナソニック)と対立する。2005年没。
中内功さんとは何度も会ったことあるが、1999年だったかな、彼は私にこう言った。
「私は商売人ではありません」――。
中内さんは、終戦後フィリピンから帰国し、父親の商売を継いで薬局を始めた。誰もが生活必需品だけは心配しなくて済む、そのような社会の仕組みをつくりたいと、「主婦の店ダイエー」を始めた。
それまで物を売るお店というのは、松下電器の商品を売る店、三菱電機の商品を売る店など、メーカーがつくった商品を、メーカーから許可をもらって「売らせてもらって」いた。小売店は、メーカーから直接、物を仕入れるため、主体性はメーカー側にあった。しかし彼はその常識を覆した。あらゆるメーカーの商品を売り始めたのだ。
商業というのは、いい商品をいかに安く仕入れ、いかに安くお客さんに売るか。定価の維持を強いるメーカー勢力の圧力に屈せず、ユーザー第一主義を貫き、価格破壊を起こした。世間の支持を集め、メーカーから小売店の主体性を取り戻し、流通革命を実現させたのだ。スーパーマーケット(「超える+市場」の意)を全国展開していった。
しかしこのことが、巨大企業・松下電器産業(パナソニック)との30年に及ぶ対立の引き金となる。1964年、松下電器の製品を希望小売価格からの値下げ許容範囲だった15%を上回る、20%の値引きでダイエーが販売。松下電器は仕入れ先の締め付けを行い、ダイエーへの商品供給ルートの停止で対抗する。
中内功の理念と、松下幸之助の「もうけるには高く売ることだ」という理念は、真っ向からぶつかった。ダイエーは松下電器を、独占禁止法違反の疑いで裁判所に告訴、両社の争いは激化していく。
さらに、1965年、花王石鹸がダイエーへの出荷を停止したため、花王を公正取引委員会に提訴する(1975年に和解)。このように中内さんは、消費者のために自身の理念を貫き、メーカー勢と徹底的に戦った。
松下さんは、1975年に中内さんを京都に招いて諭したが、中内さんが説得に応じることはなかったという。松下さんの没後、松下電器が折れる形でようやく両社は和解し、松下電器の商品もダイエーで売られるようになった。
中内さんはその後も流通の近代化を図ろうと、神戸に流通科学大学という大学まで設立し、理事長に就任している。1991年には経団連副会長に就任。それまで財界においては格下と見られていた流通業からの初めての抜擢となった。
バブル崩壊や家電量販店の台頭、そして消費者の意識が「安さ」から「品質」へと変わったことなどからダイエーの経営は傾き始め、1995年に起こった阪神・淡路大震災が追い打ちをかける。2001年、中内さんは経営悪化の責任を取って代表取締役を退任した。
「商売人は金もうけがうまい。我々は金もうけが下手だ」「理念ばかりを言っていましたから」。これが、彼が自身を「商売人ではない」と言った理由のようだ。「では革命家だったということか?」と聞くと、うなずいた。
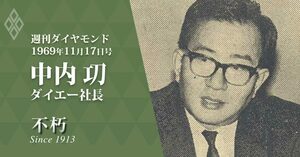 【深掘りしたい人はこちらも読んでみよう!】
【深掘りしたい人はこちらも読んでみよう!】週刊ダイヤモンド(1969年11月17日号)の中内功氏へのインタビュー
中内さんは、阪神・淡路大震災が発生すると、政府より早く食料品や生活用品を調達し、便乗値上げなどに対して物価の安定に貢献した。本当に偉いことだと思う。
ダイエーグループも震災で甚大な被害を受けたが、「スーパーはライフラインである」という哲学のもと、「街の明かりを消したらあかん」「暗闇は人に絶望をもたらす、店を閉めるな」「店の明かりをつければ、それだけで被災者たちは力が出る」と、ローソンなどダイエーグループ各店の照明を24時間点灯し続け、被災地を勇気づけた。彼のこうした理念は、イオン傘下となったダイエーにも引き継がれているはずだ。