メール、企画書、プレゼン資料、そしてオウンドメディアにSNS運用まで。この10年ほどの間、ビジネスパーソンにとっての「書く」機会は格段に増えています。書くことが苦手な人にとっては受難の時代ですが、その救世主となるような“教科書”が今年発売され、大きな話題を集めました。シリーズ世界累計900万部の超ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トッププロのライターである古賀史健氏が3年の年月をかけて書き上げた、『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』(ダイヤモンド社)です。
本稿では、その全10章99項目の中から、「うまく文章が書けない」「なかなか伝わらない」「書いても読まれない」人が第一に学ぶべきポイントを、抜粋・再構成して紹介していきます。今回は、書く人の基礎をつくる「能動的な読書法」について。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
世界を読むための「能動的」読書
いい文章を書く人は、たとえ多読家でなくとも日常的な読書習慣を持っています。一冊の本を読むように、人を読み、世界を読む。日常のすべてに対して、取材者の姿勢で対峙する。日頃から観察眼を鍛えているわけです。
こうした観察眼のベースをつくってくれるのは、やはり読書です。映画鑑賞や音楽鑑賞もいいけれど、本のほうが断然「読み」やすい。なぜでしょうか。
映画、音楽、そして演劇は、2時間なら2時間のなかでひとつの作品が完結する、「時間の芸術」です。ひとたび上映・上演されてしまえばもう、ノンストップで時間が流れ、作品世界が流れていきます。観客に立ち止まって考える余裕は与えられず、当然劇場に「一時停止」ボタンはありません。音や映像のシャワーを浴びっぱなしのまま時間が過ぎていきます。
一方で本は、いくらでも立ち止まって考えることができるメディアです。時間配分の主導権を持つのは、読者。どんな場所で、どのようなペースでどう読もうと、すべては読者の自由です。そんな自由さを持つ「本」というメディアを入口にして、「能動的な読み方」の基本を身につけましょう。ただ読むだけ(鑑賞するだけ)ではなく、こちらから問いかけるようにして読んでいくのです。今回は、その具体を2つ紹介していきたいと思います。
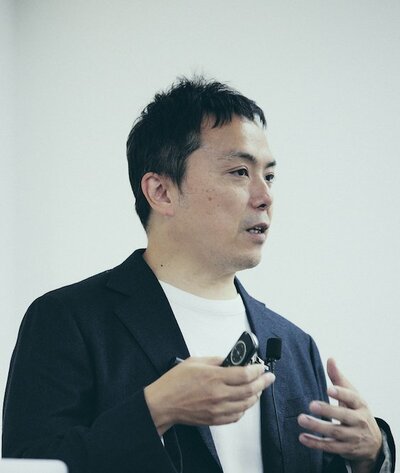 古賀史健(こが・ふみたけ)
古賀史健(こが・ふみたけ)1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著、以上ダイヤモンド社)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著、ほぼ日)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著、ポプラ社)、『ミライの授業』(瀧本哲史著、講談社)、『ゼロ』(堀江貴文著、ダイヤモンド社)など。編著書の累計部数は1300万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。2021年7月よりライターのための学校「バトンズ・ライティング・カレッジ」を開校。(写真:兼下昌典)
太宰治に独占インタビュー
するつもりで、太宰を読む
なにかの講演会に参加したときの冒頭、主催者からこんなアナウンスがあったとしましょう。
「講演会の終了後、質疑応答の時間を設けたいと思います。みなさま全員にマイクを回しますので、ひとり3問程度の質問をご準備なさってください」
おそろしい講演会ですね。おそらくあなたは、普段以上の真剣さをもって講演を聞くでしょう。登壇者のことばをひと言も聞き漏らさないよう、耳を澄ますでしょう。間違っても居眠りなどできません。「終了後、質問しないといけない」というルールが課されるだけで、受動ではいられなくなるのです。
だったら日々の読書においても、これをやればいい。つまり、「読了後、作者に質問しないといけない」と考えればいい。
作者が故人であろうと、ことばの通じない外国人であろうと、ぜったいに会えないような大作家であろうと、そんなことは関係ありません。太宰治を読むときも、ヘミングウェイを読むときも、あるいは手塚治虫の漫画を読むときでも、こころにとめておくことばは同じです。
「この人に会ったら、なにを聞こう?」
あなたはなぜ、この本を書こうと思ったのか。冒頭の一文はなにを意味しているのか。どうしてこの表現を使ったのか。このエピソードは、あの事件をモチーフにしているのではないか。裁判シーンのリアリティがすばらしかったが、どんな取材をどれだけ重ねていったのか。……そんなふうに、読み終えたら「独占インタビュー」が待っているつもりで、たくさんの質問を考えながら読んでいきましょう。
読書とは、作者との対話です。対話だからこそ本は、100人いれば100通りの読み方が生まれます。質問を考えながら読むことは、自分だけの「読み」をおこなう手立てなのです。
耳を鍛えたければ、
同じ曲を5回聴こう!
自分の小遣いでレコード──当時はまだCDではありませんでした──を買うようになった中学生時代、ぼくは音楽ファンのお兄さん・お姉さん方が口にするベーシスト評やドラマー評がよくわかりませんでした。ビートルズならビートルズを聴いていても、つい追いかけてしまうのはヴォーカルとそのメロディばかり。ギターの音ならまだしも、ベースやドラムの「よさ」を聴き分けるなんて、至難の業に思えました。
小説や映画でいうとこれは、主人公(ヴォーカル)とあらすじ(メロディ)ばかりを追いかけて、細部にまったく目が届いていない状態だと言えます。
そこであるとき、同じ曲を続けて5回聴く、という実験に着手しました。
まずはヴォーカルを中心に、ふつうに聴く。次にギターの音だけに意識を集中して聴く。続いてベースの音だけを聴き、さらにはドラムの音だけを聴く。それぞれの音が、スピーカーのどのあたりから、どんなふうに鳴らされているのか、意識を集中させる。当然、その他の楽器はノイズとして処理されるわけです。
こうして各楽器の音を理解したうえで、今度は「ぜんぶ」を聴く。ヴォーカル、ギター、ベース、ドラムのすべてに耳を開いて、聴く。
こんな──いわば能動的な──聴き方を何度か続けるうち、はじめて聴く曲であってもドラムやベースの音が、ヴォーカルと同じように耳に入ってくるようになりました。聴いた瞬間、「このバンドは、ドラマーがすばらしい」「なんてかっこいいベースラインだ!」と気づけるようになったのです。
サッカー日本代表戦を、
相手サポーターの目で観る
小説や映画、あるいは漫画やスポーツでも、同じことができるはずです。
たとえば映画『ロッキー』を、ヒロインであるエイドリアンの成長物語として観る。映画『ゴッドファーザー』を、夫・マイケルに翻弄される女性、ケイの悲劇として観る。サッカーの日本代表戦を、相手国サポーターの目で観る。『カラマーゾフの兄弟』を、長兄ドミートリイを主人公とする物語として読む。おそらくどれも、むずかしいはずです。少しでも気を抜くとロッキーを中心に観たり、日本代表を応援したりしてしまいます。
しかしこれをくり返すことで、見落としていた細部に気がついたり、矛盾を発見したりと、多角的に、俯瞰的に読む訓練になるはずです。
いい本は、何度読んでもおもしろい。だけど、せっかく再読するのなら、以前とは違った読み方を心懸けましょう。とくに古典として生き残っている作品群は、さまざまな読み方を受け入れるだけの懐の深さを持っています。いくつもの読まれ方を待っているのです。
(続く)



