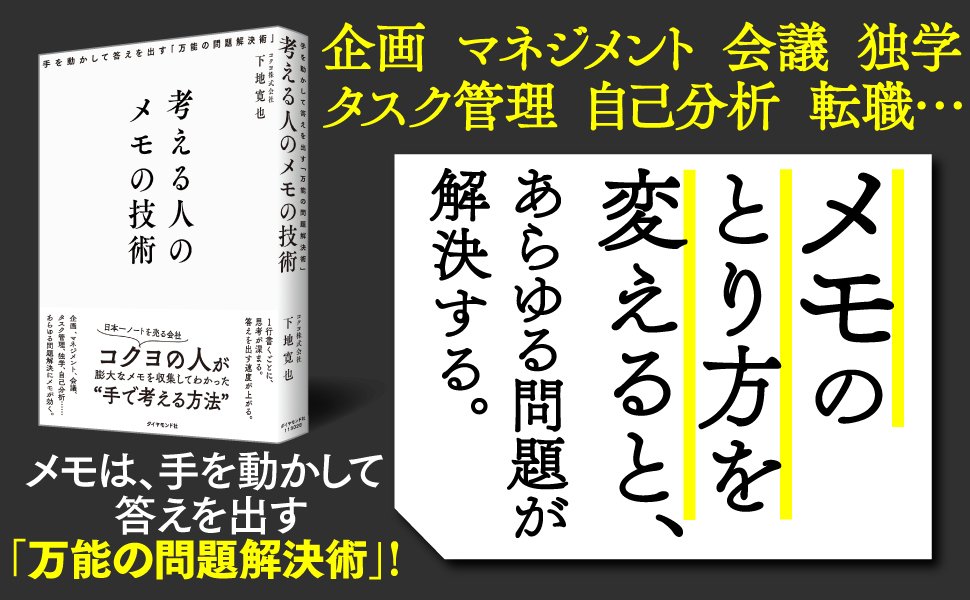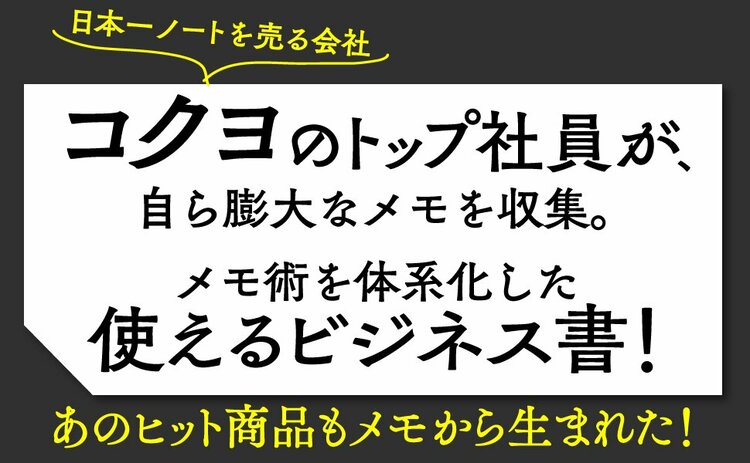答えのない時代に、メモが最強の武器になるーー。
そう言い切るのは日本一ノートを売る会社コクヨで働く下地寛也氏だ。トップ社員である彼自身が、コクヨ社内はもちろん、社外でも最前線で働くクリエイターやビジネスパーソンにインタビューを重ねてきた。そこから見えてきたことは、
◆トップクラスの人達は、メモを取り続けていること
◆そして、頭の中で考えるのではなく、書きながら考えていること
だった。
この連載では、『考える人のメモの技術』の著者である下地氏が、実際に集めたメモをベースに、あらゆる問題解決に効くメモ術を紹介していく。
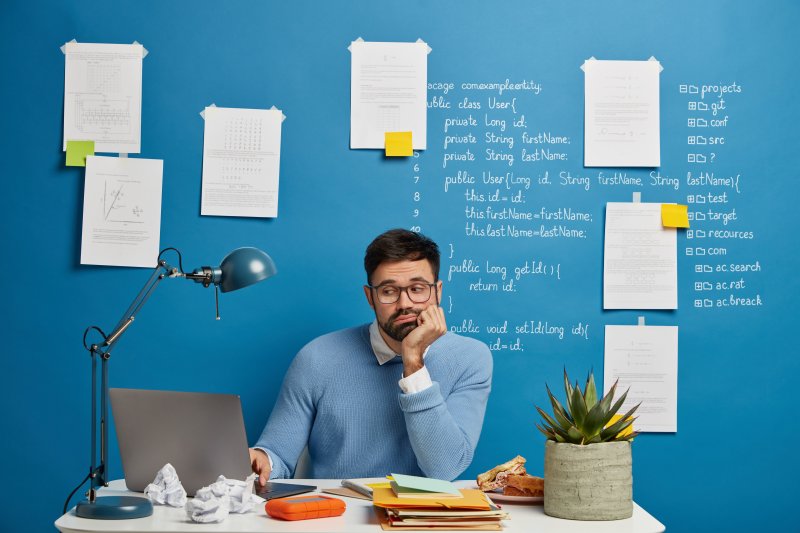 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
メモが習慣にならない人の3つの特徴
メモを上手くとりたいけど、長続きしないと思っている人も多いのではないでしょうか。メモが続かない人の特徴は、大きく3つあります。
① 全部メモタイプ
とにかく目にした情報は全部書こうとするタイプです。
安心感を得たいのでしょう。ノートには文字が埋まっていて、そのときの状況を完璧に再現できます。ただ、何がポイントかは上手く説明できません。
② 尻切れトンボタイプ
はじめはしっかりメモしますが、段々と内容が曖昧になり、次第にメモの手が止まるタイプです。
刺激がある情報に触れると、「あれも大切、これも大切」とメモします。結果、中途半端なメモができ、それが活用されることもありません。
③ 一言メモタイプ
普段からあまりメモをとらないタイプです。必要ならスマホで調べればいいと思っています。
「本当に心に響いた一言だけメモすればいいや」と考えていたりします。ところが、あとから「何か良い話を聞いた気がするがなんだっけ?」となり、検索に時間を使ってしまいます。
メモした5%が使えればいいと考える
では、どうすればいいのか。
結論から言うと、自分の情報感度に引っかかったものをメモするけれど、実際にメモした情報の5%が使えればいいやという気持ちで書きましょう。
どのメモを使うのかは事前にわからないけど、自分らしい情報、面白いなと思う情報を選んでおけば、そのうち数%が実際に使える場面に出くわして、アウトプットのヒントになるわけです。
まずは、感じたことを言葉で書いてみる
ただ、実際に使わなかった95%の情報にも意味があります。それは自分の情報感度を磨き続け、情報の血肉化につながっていくからです。
つまり、どの情報が使えるかではなく、自分の情報を選択する感度が働いているかを意識しましょう。そうして、得た情報を自分の知識のストックとして寝かして熟成するのを待つわけです。
「今までは、この方法しか知らなかった。でも今回メモした方法も使えそう。いつか試してみよう」
という感じ。
自分の知識のストックが豊かになり、アウトプットに使える武器が増えていく感じを楽しみましょう。その感覚を持つことで、メモが随分と楽しくなっていきます。
『考える人のメモの技術』では、今日から使えるメモの技術をたくさん紹介しています。ぜひチェックしてみてください。
(本原稿は、下地寛也著『考える人のメモの技術』から一部抜粋・改変したものです)