22年9月、「嘔吐恐怖症」にはじめて寄り添った『「吐くのがこわい」がなくなる本』が発売されました。そして、偶然にも本書のイラストレーターであるイマイマキさんは、この症状の当事者でした。本記事では、著者の山口健太さんとイマイさんの対談を全3回でお届けします。(構成:吉田瑞希)
第1回:パニック症、吐く恐怖に悩みつづけた人気イラストレーターを救った「とある一文」
第2回:「何気ないひと言」を引き金にしないため、あなたに知ってほしい「ある恐怖症」のこと
「嘔吐恐怖症」の本はなぜ生まれた?
イマイマキ(以下、イマイ):山口さんはどうして「嘔吐恐怖症」のテーマで本を書こうと思ったんでしょうか。
山口健太(以下、山口):私が本書を書こうと思った理由はいくつかありまして、まず一つは、たくさんの当事者の悩みを聞いてきて、そこで皆さんが理解されないつらさをお話されるんですよね。だから、世の中にこのテーマをもう少し広く知ってほしい、届けたいと思ったのが一番の理由です。
また、嘔吐恐怖症の本はこれまで、論文が載っている専門性の高いものしかありませんでした。それは、一般の方からするとすごくハードルが高いので、わかりやすく改善、克服のためのヒントが書いてある本があるといいなと考えました。
大切なのは
「考え方や捉え方」を変えること
山口:もう一つ理由があって、嘔吐恐怖症を克服するための方法で、暴露療法があるんです。吐くことに関する文字やイラスト、写真などを実際に見て慣れることで改善を目指す方法です。
嘔吐恐怖症の改善や治療の検索をすると、一番にその暴露療法が出てくるんですよ。なので、「嘔吐恐怖症の克服=暴露療法」という考えにとらわれている人も多いのですが、私はどちらかと言うと、考え方や症状との向き合い方、日常の過ごし方が非常に大事だと思うんですよね。
先ほどイマイさんが、本をたまたま読んでいたら、とある一文に出会って、そこから考え方が変わって、少しずつ行動範囲が広がったとお話ししてくださったんですけど、私は、その考え方や捉え方の部分のほうがすごく重要だと思ってるので、そういうところにフォーカスして、大事にしてほしいと思っています。
本書にも暴露療法のための章があるんですが、本のなかでも書いているとおり、自分ができるところから、無理はしないで体調がいいときだけやるとか、それに対する向き合い方を変えてほしいです。いきなり恐怖場面にすぐに向き合うのは難しいし、できないと思うので、そういうふうに思わなくてもいいんだよと伝えたいです。
当事者として
イラストにこめた思い
山口:今回、テーマ的にイラストを描くのがすごく大変だったんじゃないかと思っていて、イマイさんが当事者として、どういうことを踏まえて描いてくださったのかをお伺いしたいです。
イマイ:自分では、自分の絵は自分のコントロール下にあるので大丈夫というつもりでいたんですが、色をつけていくうちに、嘔吐してるシーンだと思うと、自然とダメージがきてしまうときがありました。なので、読者の方には無理なく慣れてほしいと思って、絵は本当にマイルドな表現で描きましたね。
山口:よりマイルドに意識して描いてくださったんですね。
イマイ:そうですね、イラストのパートの前後にある文字と写真の中間ぐらいのポップな感じで。
山口:ありがとうございます。本当にポップな感じが出ていて、ちょうどいいですよね。
表紙のイラストについても、当事者経験をお持ちでなければ、こういうイラストは描けないんじゃないかと思いました。
イマイ:編集者の方からは具合が悪いイラストという案もいただいたんですけど、私、具合が悪いときに本屋さんに行っても、文字がどんどん入ってきて具合が悪くなっちゃったりもしてたんですよね。
文字がばーってあるだけで文字に酔ってしまうというか、そういうときに具合が悪い人のイラストを見たら腰が引けてしまうのかなと思ったので、表紙では安心感を出したかったのがあります。
山口:イラストが送られてきたときに、安心感があってすごくいいなと直感的に思ったので、本当によかったです。
イマイ:ありがとうございます。
難しいテーマだからこそ
価値がある
山口:正直、嘔吐恐怖症はテーマが難しいですよ。でも、だからこそ価値があると思っているんです。
たとえば、テレビでも吐くことは扱いづらいじゃないですか。それによってクレームがきたりってことも。だから、そのなかで書籍って、すごく難しい部分はあると思ったんですけど、表紙のイラストの清涼感もあって、とても手に取りやすさが出てると思います。
イマイ:私も見本をいただきまして、赤とか青とか黄色がすごく使ってあったりすると、自分が疲れてしまう面があったんですけど、本当にシンプルで、すっと入ってくるデザインだと感じました。すごく目立たせることもできたと思うんですけど。
山口:難しいですよね、そこは。
イマイ:色とりどりの本を見ていくなかで、それで結構、頭がいっぱいってことがありますので、安心できる表紙にデザインしていただいたなと思いました。
山口:企画書の段階では、まさにすごく深刻な悩みを扱っているものだったんですが、それが最終的にこのような形で手に取っても負担がなくまとまったのは、すごくよかったです。
「克服」の意味とは?
山口:私は嘔吐恐怖症を克服することに関して、挫折感を感じてる方が多くいるのかなと思っていて、本書はそういう方に読んでほしいと思います。特に、第2章の内容ですね。
当事者の方は暴露療法をしなきゃと思っている人が多くて、でもそれにはすごく生理的な拒否反応が出てしまい、「そんなのは無理」「じゃあ克服は無理」と挫折してしまう方が多いように感じるのですが、イマイさんはどう思われますか?
イマイ:横で人が吐いていても、自分がけろりとしてれば克服ということじゃないというか、もし具合が悪くなったら、自分の安心できる方法が取れることが、いい状態になっていることだよっていうのを持ってもらえればいいのかなと思います。
山口:確かに、それはすごくありますね。克服ってイメージすると、もしかしたら多くの人は「なんの影響も受けない自分」みたいな感じなのかな。だけど、一番大事なのは自分の日常生活をどうよく過ごすかで、気持ち悪くなることとか吐くことに対して、人生が左右されにくくなることを目指すのが本当に大切だと思うんです。
イマイ:恐怖症になっている状態は、もし、こうなってしまったらどうしようってときに、過去の記憶をすごく参照するというか、過去の自分のデータから、あのときこうだったからと思いがちなので、ぜひこの本の内容もそのデータのなかに入れてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。
脳が、何だか悪い記憶のほうばかり思い出して、あのときこれで吐いちゃったから、またそうなるんじゃないかとか、そっちのデータばかり参照しちゃうんですが、本書の内容のような、こういう考え方もあるというのを入れてもらって、そちらを意識してもらえればと思います。
本書は以下に当てはまる方向けの1冊です。
・「吐くのがこわい」「気持ち悪くなるのがこわい」と日常で感じることが多い人
・人が吐く場面や吐瀉物などに尋常ではない恐怖感を抱く人
・嘔吐恐怖症のカミングアウトをしたいが、どうすべきか迷っている人

一般社団法人日本会食恐怖症克服支援協会代表理事、カウンセラー、講師
2017年5月に同協会を設立(アドバイザー:田島治杏林大学名誉教授、はるの・こころみクリニック院長)
自身が社会不安障害の一つの「会食恐怖症」に悩んだ経験を持ち、薬を使わず自力で克服する。その経験から16年12月より会食恐怖症の方への支援活動、カウンセリングをはじめる。その中で関連症状の「嘔吐恐怖症」の克服メソッドを研究。これまで1000人以上の相談に乗り改善に導いてきた。主催コミュニティ「おうと恐怖症克服ラボ」では、会員向けに克服のための情報を発信している。著書に『会食恐怖症を卒業するために私たちがやってきたこと』(内外出版社)、『食べない子が変わる魔法の言葉』(辰巳出版)などがある。
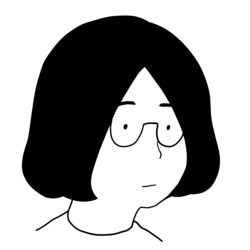
漫画家、イラストレーター。
連載に「あのこが好きだった本」「私の青空」がある。
ツイッター:koguma_kanoko




