余命ものの代表的な作品は、作家自身も余命宣告をされて本が出版される前に亡くなった小坂流加『余命10年』(文芸社文庫NEO)、人の何十倍もの早さで年老いる難病を発症した女性とカメラマンの男性の恋愛を描く宇山佳佑『桜のような僕の恋人』(集英社文庫)、月の光を浴びると体が淡く光る難病「発光病」を患った余命わずかなヒロインと主人公の男性の恋愛を描いた佐野徹夜『君は月夜に光り輝く』(メディアワークス文庫)などだ。主要人物が病気という設定ではないが、離別の予感が物語開始時点から明らかなものとしては、女子高生が太平洋戦争中にタイムスリップして特攻隊員の男性と恋をする汐見夏衛『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(スターツ出版文庫)などがある。
中高生の三大ニーズに引きつけて、型の人気の理由を考えてみよう。
1 正負両方に感情を揺さぶる
余命ものでは、クライマックスに死別の悲しみや秘めた想いを爆発させる「エモい」展開になる。また、終盤の悲哀を際立たせるためにも、主役を張るふたりが相思相愛になり、「この人のことを絶対に失いたくない」と作中人物にも読者にも思わせる展開が用意される。
2 思春期の自意識、反抗心、本音に訴える
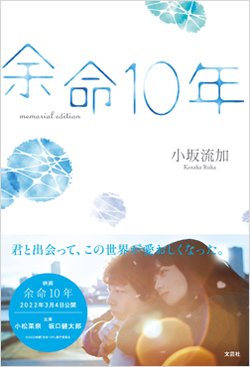 小坂流加『余命10年』(文芸社文庫NEO)
小坂流加『余命10年』(文芸社文庫NEO)
「余命」設定とは、半面では若者の焦燥感と無力さ、不安の象徴であり、もう半面では建前を取り払って本音を剥き出しにして行動したいという願望の象徴である。若者には早く何かをしたい、手に入れたい、何者かになりたいという焦りはあるが、まだ具体的に何かできるわけではない。今ここではない場所に容易に行けるわけでもない。人間関係においても、物理的な行動範囲においても、家族や学校、友人から大きな制約を受け、狭い世界に生きている。そういう近視眼的な思春期の人間が、自らの心情と重ね合わせやすい設定が「余命もの」なのである。
デスゲームものもそうであるように、余命ものにおいても、死を間近にした人間は、普段言い訳にしているさまざまな理由を取り払って本心をぶちまけ、大胆な行動に打って出る。思春期の人間は、背中を押してもらえれば突っ走ってしまう情動と衝動の激しさも併せもつ。死を前にした人間の素直さ、思い切りのよさは、中高生の心情とシンクロする。
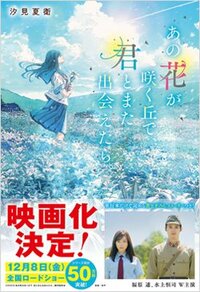 汐見夏衛『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(スターツ出版文庫)
汐見夏衛『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』(スターツ出版文庫)
ただし、何も考えていない主人公が行動するのではなく、登場人物たちの葛藤や逡巡、自意識を描くことも重要である。こうした作品では、死を前にしているにもかかわらず、主人公と想い人の間に気持ちのすれ違いが起こって後悔し、「好きだからこそ言えない」秘密や悩みを抱えるさまが描かれる。その一歩踏み出せない様子もまた、読者の似姿なのだ。もちろん、たいていの場合は死の直前か死後に、死んだ側の秘めた想いや行動がオープンにされ、異性と想いが通じ合っていたことが確認されて終わる。主人公たちにはなかなか他人に言えない本心があることが示され、しかし、最終的にはそれが明かされて感情がピークに達し、読者はカタルシスを得るのである。







