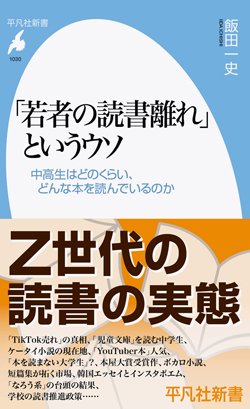3 読む前から得られる感情がわかり、読みやすい
生前には伝えきれなかった真情を吐露しあい、泣ける感動物語になることが読む前から想像できる。また、基本的にこのスタイルは連作形式を取ることが多い。一篇一篇は短いため、1回10分程度と時間が限られている朝読などでも読みやすい。
デスゲームは1999年刊行の『バトル・ロワイアル』から始まった、この四半世紀くらいの歴史しかない様式だが、余命もの/死者との再会は、それ以上の期間にわたって人気のある型だ。
たとえば2000年代には片山恭一『世界の中心で、愛をさけぶ』(2001年)や市川拓司『いま、会いにゆきます』(2003年)などが人気を博して「純愛ブーム」と呼ばれたが、『セカチュー』は余命もの(難病もの)、『いま会い』は死者との再会ものである。
さらに遡ると、1970年代の初期の集英社文庫コバルトシリーズ(のちのコバルト文庫)では難病を扱ったノンフィクション(実話)が刊行されており、1990年代には中高生女子の間で折原みとの小説『時の輝き』(1990年)が大人気作品になった。これは看護師志望の少女と不治の病を患った少年が登場する余命ものだった。
また、実話だが大島みち子・河野実『愛と死をみつめて』は1963年に刊行されて160万部を売り上げた、軟骨肉腫に侵されて亡くなった女性と大学生男子との往復書簡であり、ドラマ化、映画化されている。『愛と死をみつめて』は、いわゆるサナトリウム文学(死に至る病としての結核を患った人間を描いた小説)である堀辰雄『風立ちぬ』が、1950年代から60年代にかけて映画化、TVドラマ化されて人気を博した流れのなかにある。つまり「最近の若者は『人が病気で死んで悲しい』みたいな単純な物語が好き」なのではなく、昔から根強く需要があるのだ。
流行のタイトルは時代によって変遷していくが、この型自体は連綿と用いられ続けており、今後もおそらく利用されていくだろう。