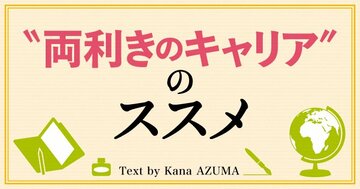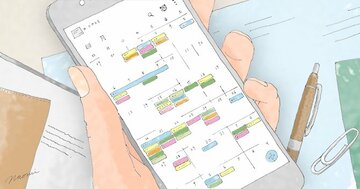いま、“パラレルキャリア”が注目されている理由
昨今、なぜ、パラレルキャリアが注目されているのでしょう? 世の中の変化のスピードが速くなり、かつて日本の経済成長の基盤であった伝統的な雇用システムが機能しなくなったこと、将来の不透明感が高まっていることなどが、その大きな要因の一つといえます。これまで、日本企業は終身雇用を前提として、ある意味、社員の人生を丸抱えしていました。研修も企業が面倒を見てくれ、敷かれたレールをきっちりと脇目も振らずに社内に向けていれば最も効率よく、昇進・昇格もできた時代でした。現在(いま)はどうでしょう。自身が勤めている会社がいつ倒産するかもわからない時代です。倒産しないまでも、経営統合やM&Aで実質的に別の会社になってしまうかもしれません。経営者が変わったら組織体制や運営ルールも変わります。個人は、いままでの仕事の進め方が通用しない大海にいきなり放り出される事態を想定して「浮き輪」を準備しておく必要があります。
若い世代は、1社で一生勤め上げることが現実的ではないという認識のもとで入社してきているケースが多いようです。社内にいて社内で提供される研修だけを受けていても、エンプロイアビリティを高めることは難しいと気づいています。不透明な経済環境の中で、社内だけで通じるスキルを身につけていても、「まさか」の事態に対応できないこと、それ故、社外でスキルを身につける必要性を感じています。視点を広げ、対応力を実践的に身につけられる機会が、パラレルキャリアだと認識している人も多くいるでしょう。
一方、日本的雇用が機能していた時代に就職したシニアは、リスクへの感度が若者よりも残念ながら劣っていると言わざるを得ません。リスク管理の観点は若手、シニア双方にとって必要ですが、それ以外にシニアにとってパラレルキャリアが必要な理由を2点あげます。1つ目は引退後のためです。これはドラッカーがパラレルキャリアを提唱したときに意識されていたものです。豊かな第二の人生を送るために、会社組織以外のネットワークを現役世代のうちから作っておくことは、地域コミュニティなどへの溶け込みやすさの点でも大切なことです。2つ目は引退までの現役期間が長期化する中で、充実した仕事人生を送るためです。60歳や65歳で引退どころか、70歳や75歳まで働くことが当たり前になろうという時代、企業内で通用するスキルや一つの専門スキルだけでは仕事人生をもはや乗り切れなくなっています。50歳以降もやりがいをもって仕事に臨めるようにするためにも、スキルアップという観点でのシニアのパラレルキャリアの重要性が従来にも増して高まってきています。「働かないおじさん」と揶揄(やゆ)されながら働くか、周囲から「働くおじさん」と認められ、自分自身もイキイキしながら働くことができるかのカギは、自らの意思によるパラレルキャリアの実践で準備・行動できるかどうかにかかっているといえます。