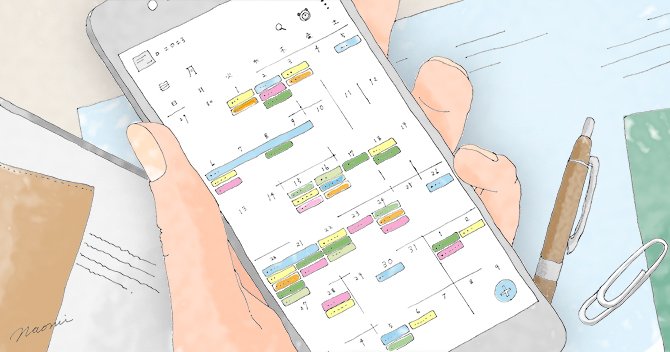
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第10回をお届けする。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
* 連載第1回 「生きづらさを抱える“やさしい若者”に、企業はどう向き合えばよいか」
* 連載第2回 ある社会人学生の“自由な学び”から、私が気づいたいくつかのこと
* 連載第3回 アントレプレナーの誇りと不安――なぜ、彼女はフリーランスになったのか
* 連載第4回 学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する
* 連載第5回 いまとこれから、大学と企業ができる“インクルージョン”は何か?
* 連載第6回 コロナ禍での韓国スタディツアーで、学生と教員の私が気づいたこと
* 連載第7回 孤独と向き合って自分を知った大学生と、これからの社会のありかた
* 連載第8回 ダイバーシティ&インクルージョンに必要な「エンパワメント」と「当事者性」
* 連載第9回 “コミュニケーションと相互理解の壁”を乗り越えて、組織が発展するために
学生たちが選んだ「普通とは何か?」というテーマ
多様な背景をもち、多様な考え方をする人たちと協働して課題解決に当たろうとするとき、「対話的態度」が欠かせない。「対話的態度」というのは、自分の主張を通して相手を説得しようとする態度ではなく、相手の考え方やその背景などの理解を試み、自分と相手との差異を肯定しながら折り合いをつけていこうとする態度である。
このような考えから、私たち(神戸大学)は「対話実践」を取り入れた授業を行っている。この授業では、まず、他者と対話することで考えを深めたい各自の関心を持ち寄り、その関心をもとにして対話にふさわしいテーマをつくる。複数のテーマが立ち上がったところで、「今日の授業で話し合いたいテーマ」を多数決で決め、「対話実践」をスタートさせる。教員たちも「対話実践」の参加者として、学生たちを指導することをやめ、自分の考えを率直に述べる。
先日の授業で、学生たちは「普通とは何か?」というテーマを選んだ。各人が「普通」の意味を述べ合い、徐々に「普通」にさまざまな顔があることが見えてくる。学生も教員も一緒になってひとつのことを深く考える時間を持つことで、毎回さまざまな気づきがもたらされるが、「普通とは何か?」についての対話実践は、学生たちの深い思考を表現する発言も多く、私自身にとっても格別に気づきの多い回(授業)であった。
例えば、ある学生から「『普通』の反意語は何だろうか?」という問いかけがあり、それに応じる別の学生の発言の中に「異常」「特別」といった言葉があった。しかし、「異常」の反意語は「正常」であり、「特別」の反意語は「通常」ではないかという意見も出された。こうして、「普通」という言葉は、「正常」や「通常」といった言葉に近いのではないか、という方向に話が展開した。どうやら、「普通」という言葉は、「慣れ親しんでいること」という意味で使うことが多く、したがって、「普通とは何か?」を問うことは、「慣れ親しんでいること」を疑ってみることを意味しているようだ、という理解が参加者間で共有された。
また、別の学生からは、自分たちが最近使う「普通」には、「普通においしい」など、ポジティブな意味での「とても」という意味があると指摘する発言もあった。「慣れ親しんでいること」を意味する「普通」が、ポジティブな「とても」という意味に転じると考えると、若者たちが使う「普通」という言葉からは、「慣れ親しんだことに肯定的な価値づけをしようとする心の動き」を読み取ることができるのではないか、と推測する学生の発言が続いた。
さらに別の学生は、親が押し付けてくる「普通の生き方」に対して反発する気持ちを表現していた。「普通」は自分たちの生き方を縛る言葉でもあることについても、参加者の間で共感が広がった。
私自身、このような対話の過程で、「普通」が現代を生きる若者たちにとってキーワードであることに気づいていった。若者たちは、慣れ親しんでいることが良いこと、快適なことであり、「普通」でないことを嫌い遠ざけようとする一方で、「普通」であることの束縛に対して感受性が高く、押し付けられる「普通」への拒否感が強いのではないか。ポジティブな「普通」とネガティブな「普通」の間で、若者たちは「自分にとっての普通」「自分らしい普通」を探しているのではないだろうか。









