「出し切り」を採用することで、ブックオフの棚には、周辺住民が売ったものがそのまま並ぶことになり、ブックオフ側の意図を超えた品ぞろえが生まれるのです。まさに、ただ「なんとなく」存在する商品で書棚が埋め尽くされるのです。
したがってその商品棚は(もちろんベストセラーなどが多く集まるという点では一致するかもしれませんが)地域によってばらつきが生まれます。例えば、アニメの街としても知られるブックオフ池袋サンシャイン60通り店では、アニメ関連の書籍が多く見られます。それは、いま語ってきた理由によって、池袋という街の特徴を、その書棚が反映しているからかもしれません。
これ以外にも、地域色が豊かなブックオフは数多く存在します。東京・中央線沿線のブックオフは、サブカルチャーや精神世界の本が数多くそろっています。ブックオフ東中野店は、以前、店頭に「精神世界大歓迎」という張り紙が貼ってありました。これを見たときはさすがに笑ってしまいましたが、アンダーグラウンドカルチャーの気風が色濃く残る中央線沿線らしい品ぞろえだともいえるでしょう。
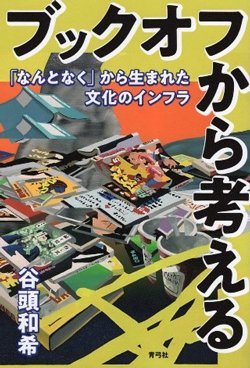 『ブックオフから考える 「なんとなく」から生まれた文化のインフラ』(青弓社)
『ブックオフから考える 「なんとなく」から生まれた文化のインフラ』(青弓社)谷頭和希 著
あるいは、日本でいちばん標高が高い富士山の麓にあるブックオフ富士吉田店には、富士山関連の本が多くそろっています。そのなかには富士山の写真集や、富士山噴火に関する科学的な知見を述べたものなどさまざまな本があります。その周辺に住む人々の蔵書に富士山に関する本が多く、それらが売りに出された結果、こうした本のバリエーションが生まれたのだと考えられます。
いずれにしても、ブックオフは、そうした「意図」が相対的に弱い書棚を持っています。ブックオフの書棚を決定する大きな要因は、そこでどのようなものが売られたのかということであり、その点でブックオフ側の意図は弱まります。すると、そこにある商品は何かしらの目的があって置かれているというよりも「ただそこに存在している」ということになります。こう考えていくと、ブックオフが持つ「なんとなく性」の一端がわかると思います。







