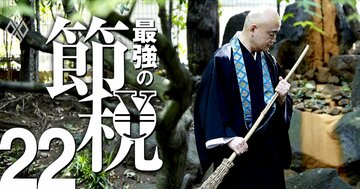さらに、日本の浄土真宗や日蓮系諸宗においては、篤信の在家者は、たとえみずから福徳を積まなくても、死後に浄土へ転生してすぐさま仏となると考えられている。
浄土真宗においては、在家者は極楽浄土にいる阿弥陀仏から信心をたまわった場合、たとえみずから福徳を積まなくても、死後に極楽浄土へ転生してすぐさま仏となると考えられているし、日蓮系諸宗においては、在家者は、信によって霊山浄土にいる久遠実成の釈迦牟尼仏から因果の功徳を譲り与えられた場合、たとえみずから福徳を積まなくても、死後に霊山浄土へ転生してすぐさま仏となると考えられているのである。
浄土真宗と日蓮系諸宗とから派生したいくつかの在家者団体は、こんにち、出家者を在家者の葬式に呼ばないまま、自分たちだけで在家者の葬式を行なっているが、このことは、浄土真宗と日蓮系諸宗との教理上、充分に頷けることである。
ただし、葬式仏教が在家者にとってまったく不必要となることもないに違いない。
世の中にいるのは葬式仏教が不必要である在家者ばかりではない。むしろ、「転生はない」と信じている筋金入りの唯物論者を例外として、そのほかの、「転生はあるかも」と漠然と思っていつつ、福徳を積んでおらず、あるいは浄土真宗と日蓮系諸宗とを信じていない在家者は、みずからあるいは亡者が善趣へ転生するために、聖者らしい出家者を葬式に呼んで布施を与えたいと願うことが多いのではあるまいか。
葬式仏教に疑問を持つ在家者も、在家者と異ならない、聖者らしくない出家者を葬式に呼んで布施を与えることに疑問を持つにすぎず、在家者と異なる、聖者らしい出家者ならぜひ葬式にお招きして布施を差し上げたいに違いないのである。
聖者らしい出家者は、出家者の世俗化が進んでいる現代の日本においては、なかなか見いだされなくなっている。しかし、近代までの日本においては、かならずしもそうではなかった。
内務官僚、政治家であった田子一民(1881~1963)は、東京帝国大学の学生であったころから、臨済宗妙心寺派の西山禾山(禾山玄鼓。1837~1917)に帰依していた。禾山は悟り体験を深めてのち、明治6年(1873)、臨済宗の蘊奥を窮めて印可を受け、同14年、火災によって全身大火傷を負い、以後、「焼け禾山」と異名を取った老師である。