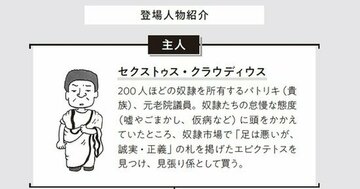相談もなしに広告が先行したのである。落語だったら笑えるが、当人として巻き込まれると笑えない。それくらい中野さんは気が早かった。私は泳げもしないのに、中世哲学の海に投げ出された。溺れて、それから少しずつ泳ぎ始めた。
その後、世間では中世哲学に対する関心が徐々に高まり、中世哲学関係の原稿依頼が続々と私に舞い込むようになった。私は途方もなく疲弊していった。
日本の大型書店では哲学書のコーナーは広々していても、中世哲学のコーナーは貧弱であったり、そもそもなかったりする。それも当然である。中世哲学はカトリック神学の牙城であり、カトリックの神学校では細々と教えられ続け、教科書が用いられ、継承されていた。日本でも外国でも中世哲学は基本的に日陰者なのである。
ところが、20世紀の後半に人々の注目が俄然向けられるようになった。中世哲学は、哲学の初学者が跨いで通るだけの存在だった。それが風向きが変わったのである。
ボヘンスキー『形式論理学の歴史』(英訳、1956年)、ベーナー『中世論理学』(1952年)、ベーナー『オッカム関連論文集』(1958年)など、1950年代に中世論理学が意味と指示をめぐる先駆的な理論を出していたことに注目が集まるようになった。中世で展開された論理思想は古臭いものではなかったのである。
そして、ジル・ドゥルーズが『差異と反復』(1968年)において、ドゥンス・スコトゥスの存在一義性の理論に光を与え、さらに注目が進んだ。ドゥルーズひとりが、中世哲学への扉を開けたわけではないが、その貢献度はとても高いのである。
ギリシア以来の西洋哲学が
こだわり続けた「存在」概念
中世哲学を語る場合、「存在とは何か」という問いを避けて通ることはできない。「存在」という概念の特殊西洋哲学的性格に気づいてこそ、哲学に入門することができると今になって私は感じる。私は、存在ということを普遍的で無味乾燥で自明な概念だとは決して思わない。東洋哲学においては存在が中心問題として盛んに論じられたことはないはずで、これはとても特殊なことなのだ。存在概念は日本において今でも黒船のままである。
「存在とは何か」という問いは、哲学に染まった考え方をしない人からは、どうしてそんなことが気になってしまうのかと、訝られるだけかもしれない。