相談もなしに広告が先行したのである。落語だったら笑えるが、当人として巻き込まれると笑えない。それくらい中野さんは気が早かった。私は泳げもしないのに、中世哲学の海に投げ出された。溺れて、それから少しずつ泳ぎ始めた。
その後、世間では中世哲学に対する関心が徐々に高まり、中世哲学関係の原稿依頼が続々と私に舞い込むようになった。私は途方もなく疲弊していった。
日本の大型書店では哲学書のコーナーは広々していても、中世哲学のコーナーは貧弱であったり、そもそもなかったりする。それも当然である。中世哲学はカトリック神学の牙城であり、カトリックの神学校では細々と教えられ続け、教科書が用いられ、継承されていた。日本でも外国でも中世哲学は基本的に日陰者なのである。
ところが、20世紀の後半に人々の注目が俄然向けられるようになった。中世哲学は、哲学の初学者が跨いで通るだけの存在だった。それが風向きが変わったのである。
ボヘンスキー『形式論理学の歴史』(英訳、1956年)、ベーナー『中世論理学』(1952年)、ベーナー『オッカム関連論文集』(1958年)など、1950年代に中世論理学が意味と指示をめぐる先駆的な理論を出していたことに注目が集まるようになった。中世で展開された論理思想は古臭いものではなかったのである。
そして、ジル・ドゥルーズが『差異と反復』(1968年)において、ドゥンス・スコトゥスの存在一義性の理論に光を与え、さらに注目が進んだ。ドゥルーズひとりが、中世哲学への扉を開けたわけではないが、その貢献度はとても高いのである。
ギリシア以来の西洋哲学が
こだわり続けた「存在」概念
中世哲学を語る場合、「存在とは何か」という問いを避けて通ることはできない。「存在」という概念の特殊西洋哲学的性格に気づいてこそ、哲学に入門することができると今になって私は感じる。私は、存在ということを普遍的で無味乾燥で自明な概念だとは決して思わない。東洋哲学においては存在が中心問題として盛んに論じられたことはないはずで、これはとても特殊なことなのだ。存在概念は日本において今でも黒船のままである。
「存在とは何か」という問いは、哲学に染まった考え方をしない人からは、どうしてそんなことが気になってしまうのかと、訝られるだけかもしれない。
確かに、幼稚園でも小学校中学校でも、「存在とは何か」を考えてみなさいという課題が出されることもないし、夕方の一家団欒のときに、家族の話題にのぼることもない。私も、子供の頃、哲学という不思議な学問に心惹かれていたとき、まさか「存在とは何か」を問う学問だとは夢にも思わなかった。私自身、田舎の実家に帰ったときに、「何を研究してるのか」と問われても、正直に「存在を研究している」と告白することはとてもできなかった。そんなことを告白された親はどんな顔をするのか、想像するだに恐ろしい。
「存在とは何か」という問いは、アリストテレスの中でも中心的問題だし、中世哲学においても盛んに論じられた。存在とは何か、ということが直接論じられるわけではないとしても、神の存在証明においては、存在と本質の関係が決定的に重要になるし、存在と本質の関係は、サルトル(1905~1980)の「存在(実存)は本質に先立つ」という言葉によっても、重要であることはすぐにわかる。
私は大学に入って、哲学を学ぶための前提知識としてアリストテレスの哲学があることを知り、アリストテレスの『形而上学』を読み始めたが、これは初学者にとって歯が立つ代物ではない。ギリシア語も学び始めたが、こちらはすぐに挫折した。
出隆『アリストテレス哲学入門』(岩波書店、1972年)という、アリストテレスのテキストから基本的なところを抜粋してまとめたアンソロジーの形式をとったよい入門書があり、運よく神保町でそれに出会い、購入し、それを何度も読んだ。いつかギリシア語で読んでみたいと強く思った。
存在を語るための基本的な用語、本質、ロゴス、実体、偶有性などは使えるようにはなったが、「わかった」という気にはなれなかった。言葉に出し、語り、文章にして、論じることは少しできるようになった。しかしわからないというのが正直な気持ちだった。
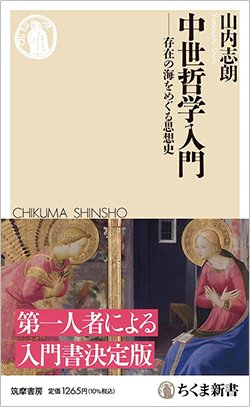 『中世哲学入門 存在の海をめぐる思想史』(ちくま新書)
『中世哲学入門 存在の海をめぐる思想史』(ちくま新書)山内志郎 著
今でも、このわからないという気持ちは残り続けており、それは消えることはない。この気持ち悪さを気持ち悪いと思いながら、不快さを感じながら考え続けることが哲学だと思う。
わからなさを伝えることも任務として成立すると思う。私もまたわからないまま存在について何本も論文を書き、たくさんの言葉を費やしてきた。しかし書き連ねられた言葉は風の音のような空っぽの響きばかりで、わかったという思いは漂わない。いや、わかるとかわからないとか言うことが、存在ということに立ち向かう場合に重要なことかもわかりはしない。存在をわかろうとすること自体、暴力的ではないかと思ったりする。







