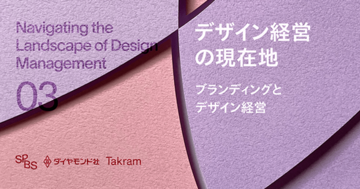事業会社に伝書バトみたいなデザイナーはいらない

──これからの事業会社のデザイナーにはどんな力が求められるでしょうか。
経営やビジネスとデザインを接続できるコミュニケーション力が非常に大事だと思っています。事業を引っ張ろうとすると、必ずぶち当たるのがビジネス言語とデザイン言語のギャップという壁です。「事業部の担当者が、昨日は黒がいいって言ったのに、今日は赤がいいって言いだした」とか、「話が全然通じない」みたいな話をよく聞きますが、実はデザイナー側が本質のキャッチアップができていない。ただ伝えるだけの伝書バトのような振る舞いをしてしまうデザイナーが上流に入ってもコミュニケーションコストが増えるだけで、プロダクト開発をリードしているとは言い難いです。
アウトプットも絵だけで示すのではなく、ビジネス側の人が共感できる言葉でちゃんと説明しないといけません。いいデザインは言葉がなくても伝わるはず、という気持ちは分かりますが、特に事業開発の上流フェーズで大事な部分を相手の想像力に任せると失敗します。僕自身、「これすら伝わらないのか」みたいな経験は死ぬほどあります。こればっかりは背中を見せていくしかない。僕自身がどこで失敗し、どう苦労し、どう解決したか、成功例も失敗例もできるだけ共有するようにしています。
──デザイナー向けにビジネススキル研修などを行う会社も増えていますね。
研修も大事ですが、それだけで変われるなら、あらゆる会社がとっくに変わってますよね。デザインツールの使い方を学んだからといっていいデザインができるわけじゃないのと同じで、重ね合わせる現場経験があってこその研修です。デザイナーの採用でも、「クライアントワークじゃなくて、事業会社でデザインをやりたいのはなぜなのか」は必ず問うようにしています。そこに意味を見いだせないと、ミクシィでバリューを発揮できないと思うので。
──横山さんが考えるCDOの条件があれば教えてください。
具体と抽象を行き来して本質を捉えるスキルは必須です。経営の言語を能動的にデザインに接続できないと、ビジネス側の想定内の仕事しかできなくなってしまいますから。「なんか現場がうまく回らない」「なんかプロダクトがイケてない」という状況があったとして、この「なんか」の構成要素を分解して具体的な工程や施策、職能に落とし込み、ものづくりや組織づくりに着地させられることが重要だと思います。
ただ、組織の風土やメンバー構成によって最適な接続方法は違いますから、「CDOらしい振る舞い」は一つではありません。事業開発や組織構築にデザインの専門性を生かそうとすれば、デザイン以外の部分をどうにかしないといけないケースも多いし、「それはビジネス側の問題です」って切り捨ててしまうと問題は永遠に解決しない。CDOという職名をお飾りにしないためにも、職名にとらわれ過ぎず、「経営を強くするために自分が入るんだ」という整理をやり切ることが大事だと思っています。