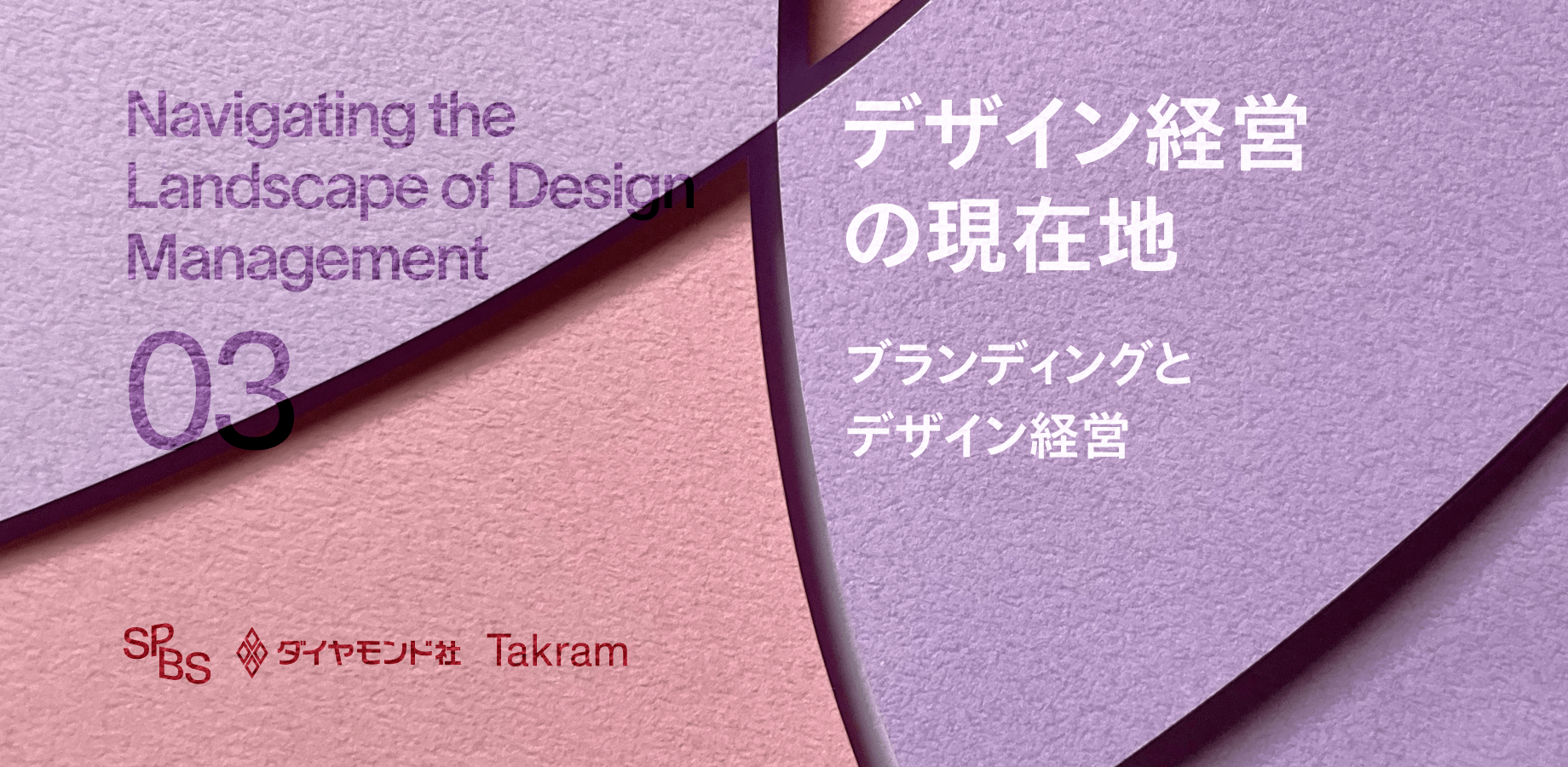
長く人々に愛され続けるブランドを生み育てるために、商品やコミュニケーション、あるいは組織をどうデザインすれば良いのだろうか。デザイン経営の在り方や方法論を解き明かすシリーズセッション「デザイン経営の現在地」(主催:SPBS THE SCHOOL、Takram、ダイヤモンド社)の第3回が11月7日、「ブランディング」をテーマに開催された。Takram代表の田川欣哉氏、一橋大学大学院経営管理研究科教授の鷲田祐一氏のコーディネートで、生活者に寄り添う価値提供を通じて独自のブランドを構築してきた2社の事例から、ブランディングに資するデザインを考える。(取材・構成/フリーライター 小林直美、ダイヤモンド社 音なぎ省一郎 撮影/まくらあさみ)
進化し続けるブランドの原点と今
今回のゲストスピーカーは、無印良品(MUJI)の商品開発と店舗運営を行う良品計画上席執行役員の嶋崎朝子氏、スープストックトーキョーなど多数の事業ブランドを運営するスマイルズ取締役社長兼CCO(チーフ・クリエイティブ・オフィサー)の野崎亙氏。まずは両名から、ブランドの根幹にあるコンセプトと現在の活動についてプレゼンテーションが行われた。
(1)「最良の生活者」のための素材をデザイン──良品計画・嶋崎朝子氏
無印良品(MUJI)といえば、全世界に1100店舗以上を展開し、衣料品、生活雑貨、食品、家電など幅広い商品7500アイテム以上を製造・販売する、言わずと知れたグローバルブランド。嶋崎氏は現在、衣類や食品以外のあらゆる商品の企画・開発および品質管理を担う「生活雑貨部」の責任者であり、過去にはスキンケア商品を一大カテゴリーに成長させた実績を持つヒットメーカーだ。
無印良品の原点は、1980年に40アイテムでスタートした西友のプライベートブランドであり、以来、「最良の生活者を探求する」というテーマの下、「素材の選択」「工程の点検」「包装の簡略化」というものづくりの三つの視点が守られている。コンセプトを継承する仕組みとして、同社に深い関わりを持つ4人のクリエイター(小池一子氏、原研哉氏、深澤直人氏、須藤玲子氏)から成る「アドバイザリーボード」が存在し、全体の方向性や商品構成などをジャッジする役割を果たしている。
「消費社会に対するアンチテーゼとしてスタートしているので、売り上げを最優先することはあり得ない。マーチャンダイザーもデザイナーも生活者視点でのものづくりをポリシーに、生活全般をカバーする素材としての商品群を生み出しています。現在は<土着化>をキーワードに、道の駅の活性化や棚田の保存など、地域の課題に取り組む動きを広げています」(嶋崎氏)
 嶋崎朝子氏
嶋崎朝子氏
(2)「自分ごと」を起点に、世の中の体温を上げる事業を創造──スマイルズ・野崎亙氏
99年に「食べるスープの専門店」として<Soup Stock Tokyo>の1号店をオープン。翌2000年に、同店を運営する三菱商事のコーポレートベンチャー0号として設立されたスマイルズ。現在は、2016年に分社した株式会社スープストックトーキョーが<100本のスプーン>を含めた飲食ブランドを運営し、スマイルズは、ニューサイクルコモンズ<PASS THE BATON>やネクタイ専門店<giraffe>を運営する。
23年に創業者の遠山正道氏から社長を継承した野崎氏は、これら自社ブランドのクリエイティブを統括しつつ、社外の企業、自治体、個人など多種多様な主体に伴走し、事業やブランドのプロデュースやコンサルティングを手掛けてきた。同社が大切にしているのが「世の中の体温をあげる」という理念と、「誰にも似てない」という指針だ。人の心を動かす価値を届けるために、事業においても組織運営においてもユニークネスを重視する。
「強調しておきたいのが、私たちの事業は社会性に端を発していない、ということです。常に『自分が欲しい商品』『自分が行きたい店』という、N=1の自分ごとが起点。好きで作ったものには熱くコミットできるし、必死に売るから売れる。すると意味は後から付いてくる。いわゆるマーケティングから生み出された商品は一つもありません」(野崎氏)
 野崎亙氏
野崎亙氏







