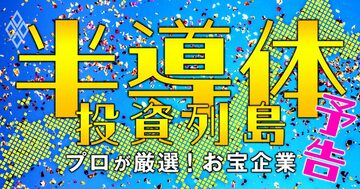“半導体立国”復活のカギは設計開発
スタートアップの育成にあり
そもそも半導体はかつて「産業の米」と呼ばれ、日本は「半導体立国」といわれるほどの強みを持っていました。特にメモリ半導体の分野が強かったのですが、日立のマイコン「Hシリーズ」や「SuperHシリーズ」、NECのマイクロプロセッサー「V30」など、1990年代初頭ぐらいまでは、ロジック半導体においても日本は世界の最先端の一角を担っていたのです。
では今後、日本が半導体産業で再びプレゼンスを確立するためには、どのような打ち手があるのでしょうか。
半導体産業は大きく設計(開発)と製造に分かれます。昔はこれを一気通貫で行うのが普通で、今でも日本のルネサスなどは一気通貫で半導体事業を行っています。しかし世界的には、これを分散するかたちが現在の主流になっています。製造工場を持たないファブレス企業として設計や開発に注力するところと、ファウンドリーとして製造プロセスだけを行うところに分かれているのです。
日本の場合、熊本へのTSMC誘致は製造側、ラピダスも開発を行うとはいえ事業の中心は製造側に寄っているように見えます。ただ、やはり産業の基礎は設計にあるのではないかと私は考えています。
たとえば自動車産業におけるトヨタ自動車の強さは、設計など上流部分にも強みを持っているがゆえのものといえます。日本における半導体産業の再興のためには、設計開発の面でも復活の道を探る必要があると思うのです。そこで提言したいのは、半導体スタートアップの育成強化です。
半導体を製造するには大量に資金が必要です。そのため、TSMC誘致でもラピダス設立でも、政府や大企業から多額の投資が行われているわけです。つまり創業間もない資金力のないスタートアップが半導体製造を手がけることは、ほぼ不可能といっていいでしょう。となると、必然的にファブレスとしてスタートすることになります。
こうした半導体スタートアップの設計部分での育成に力を入れ、日本全体では一気通貫で半導体産業を育てていくような方向性が望ましいのではないかと思います。今のところ、日本政府の施策もその方向で進んでいるように見えます。また、ソフトバンクグループの孫正義会長も、次世代のAI「人工汎用知能(AGI)」時代に必要となる、NVIDIA対抗にもなりうる半導体スタートアップ育成のために、1000億ドルを拠出すると噂されています。こうした動きを推進し続けることで再び、日本が半導体立国に返り咲くことを期待したいと考えます。
(クライス&カンパニー顧問/Tably代表 及川卓也、構成/ムコハタワカコ)