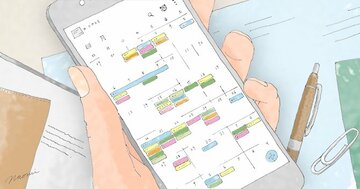学校の教育現場と一般企業の職場が抱える問題
子どもたちの奪われた力を取り戻す教育は、文字どおり、体当たりの実践を必要とする。子どもたちが「この場所に受け入れられている」という実感を持つために、教員たちは全身を使って子どもたちに応答する。子どもたちの活動の自由を保障する一方で、子どもたちにとって魅力的な授業を必死になって創り出す。その様子は、当連載の4回目『学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する』でも描写している。放課後に子どもたちが自宅に帰っていくと、教員たちの間に深い疲労感が漂う。それでも、会議や授業の準備などの業務は続き、時間がいくらあっても足りないというのが、放課後の学校現場の現状だ。
私が附属特別支援学校の校長だった5年間に、「働き方改革」が進んだ。会議の時間は大幅に短縮され、タイムカードの導入によって勤務時間の管理が行われるようになった。それでも、気力を振り絞って働く教員たちの疲労が緩和されたようには感じられない。必要とされる業務が大きく減少するわけではないし、むしろ、教員間でコミュニケーションを取るための時間が削られたことで、心理的なストレスが高まっているのではないかとさえ思う。
よい実践をしている教育現場や、社会福祉の現場の労働環境が厳しいというのは、よくある現実だ。教員たちは子どものためを思い、がんばって働く。それによって、意義深い実践が展開されるが、その一方で教員たちの疲弊は看過される。
私の研究仲間の林美輝さんが、『語り(ナラティヴ)を生きる』(晃洋書房)という本を出版した。この本の内容は、ある重度障害者の介助を経験した人たちの語りを中心に展開する。介助されている重度障害者は、森修さんという関西圏の障害者運動のリーダーで、自立生活を実践している人である。自立生活というのは、障害者が親にも施設にも依存することなく、介助者との関係を紡ぎながら成り立たせる生活のことである。森さんが多くの介助者と紡いでいたのが、「支援する・支援される」という一方的な関係性ではなく、お互いに何かを与え合う“相互的な関係性”だったというストーリーが展開する。
この本の中にあるひとつのエピソードが、私の心に響いた。ある介助者が、森さんから、「お前は能力主義や」と言われたというくだりである。森さんは、その介助者が「がんばって何でもできるようになる」という価値観に縛られていることを見抜き、「お前、多分、中途障害者になったら、自分を悲観して、自殺ぐらいする」と断じた。「お前死ぬって」と心配した森さんは、その介助者に「俺が心の介護したる」と申し出た、というエピソードである。
このエピソードは、私自身が抱えている「能力主義」に鋭く突き刺さったのだが、同時に、これをそのまま神戸大学附属特別支援学校の教員たちにも紹介したい気持ちにもなった。子どもたちのために身体を張ってがんばる教員たちの尊さは疑いえないものだが、子どもたちの元気を取り戻すために、教員たちが疲弊して追い込まれるというのは正しくない。
よい実践を実現しようとすると、教員の有能さが問われてしまう。教員たちは、成果を求めて自分を追い込んで仕事に励む。その姿は一面では美しいことなのだが、別の一面では、森さんからの「お前死ぬって」という言葉が重なる。子どもたちも教員たちも元気が出る学校は、いかにして可能だろうか――よい実践とよい労働環境との両立の方向性を示すことができなかったことは、神戸大学附属特別支援学校での私の心残りのひとつだ。