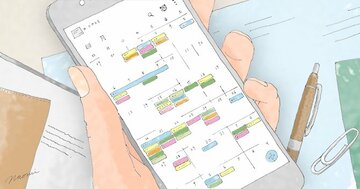学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第13回をお届けする。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
* 連載第1回 「生きづらさを抱える“やさしい若者”に、企業はどう向き合えばよいか」
* 連載第2回 ある社会人学生の“自由な学び”から、私が気づいたいくつかのこと
* 連載第3回 アントレプレナーの誇りと不安――なぜ、彼女はフリーランスになったのか
* 連載第4回 学校や企業内の「橋渡し」役が、これからのダイバーシティ社会を推進する
* 連載第5回 いまとこれから、大学と企業ができる“インクルージョン”は何か?
* 連載第6回 コロナ禍での韓国スタディツアーで、学生と教員の私が気づいたこと
* 連載第7回 孤独と向き合って自分を知った大学生と、これからの社会のありかた
* 連載第8回 ダイバーシティ&インクルージョンに必要な「エンパワメント」と「当事者性」
* 連載第9回 “コミュニケーションと相互理解の壁”を乗り越えて、組織が発展するために
* 連載第10回「あたりまえ」が「あたりまえではない」時代の、学生と大学と企業の姿勢
* 連載第11回「自由時間の充実」が仕事への活力を生み、個人と企業を成長させていく
* 連載第12回 “自律”と“能動”――いま、大学の教育と、企業の人材育成で必要なこと
5年前、学校長を兼務するように言われたときに
今回は、私が5年間、神戸大学附属特別支援学校の校長として勤めた経験をもとに、働くことと人を育てることについて述べようと思う。
特別支援学校は、すべての子どもの成長を支えるべく、全国に設置されている学校である。義務教育の間、子どもたちは、住まいの近くにある公立学校で学ぶことができたらいい。しかし、実際には、カリキュラムや教員の配置、物理的な空間や設備など、現在の教育条件では、一般の学校に通って学ぶことが困難だという子どもが一定数存在する。そうした子どもたちがしっかり学ぶことができる条件を整えた学校が、特別支援学校である。
神戸大学には、50年以上の歴史を誇る附属特別支援学校がある。私は、2019年から今年2024年3月までの5年間、その学校の校長を務めてきた。本稿執筆のいま現在は在任中だが、任期をまもなく終えるので、この学校で学んだこと、考えたことの一端を文章として表現しておきたい。
ちなみに、国立大学の附属学校は、従来、大学の教員が校長を担ってきた。大学と附属学校との連携を成り立たせ、附属学校での実習など、大学の教育と連動させたり、附属学校における研究活動を活性化させたりなど、附属学校の独自性を創出するのに適したかたちとして、兼任校長の仕組みが維持されてきた。しかし、大学教員が校長を兼務するということは、校長が附属学校に常駐できないことも意味する。校長の不在が多いというのは、日々の学校運営のリスクマネジメントなどの点でデメリットにもなる。近年では、附属学校のガバナンスを高めることを目的として、大学教員ではなく、附属学校の教員が校長を担う“校長専任化”の方向に進んでいる。
神戸大学の附属学校には、中等教育学校、小学校、幼稚園、特別支援学校の4校園がある。これらも、この春から専任校長の制度に移行する。つまり、教育学者や政治学者などが名を連ねてきた神戸大学教員としての附属特別支援学校長は、私が最後ということになる。
実は、5年前、学校長を兼務するように言われたとき、私には消極的な気持ちが強くあった。まず、私の個人的な経験の中で、学校にはあまり良くない思い出があり、特別支援学校をわざわざ設置しなければならないのは、すべての子どもを受け入れることができない学校の仕組みがあるからだと考えていたためだ。私は、特別支援学校での居心地の悪い勤務を想像していたのである。
ところが、実際に勤め始めると、人をとても大切にする学校の魅力に惹かれるようになっていった。また、パートタイムとはいえ、校長としての業務は予想以上に多岐にわたっており、居心地の悪さを感じる暇がないこともわかっていった。子どもたちの学びに関わる課題だけでなく、大学組織と学校組織との整合性、社会から孤立しがちな学校環境の問題、障害者雇用の現場としての悩み、保護者が抱える問題、教職員の職場環境や人事の問題など、あらゆる問題に日々直面した。いまにして思えば、そのひとつひとつが、私の大きな学びになる経験であった。私はこの5年間の経験に深く感謝しており、この職場を後にすることをたいへん寂しく感じている。