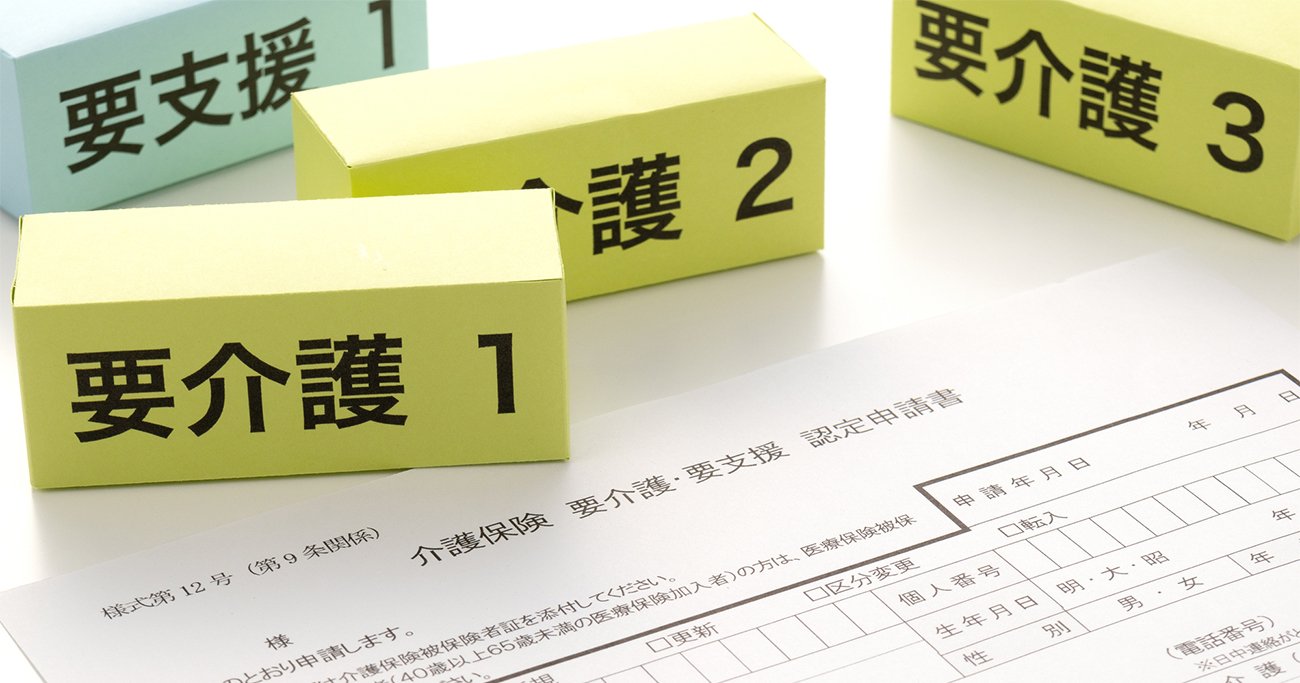 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
介護保険制度の施行から23年。度重なる改悪により、制度の問題点が露呈し、そのしわ寄せは介護現場に向いている。このような介護保険制度の決定的な問題を上野千鶴子と高口光子(正しくははしご高)が挙げる。本稿は上野千鶴子・高口光子著『「おひとりさまの老後」が危ない! 介護の転換期に立ち向かう』(集英社新書)の一部を抜粋・編集したものです。
政策決定者の人間への見方が
介護保険にはあらわれている
上野 介護保険改悪で、在宅も施設も同じように危機に来ています。施行から23年が経過して、このあとどうなるかということを一緒に考えていきましょうよ。
高口 はい。制度の背景には、それを作った人、または当時の時代の人間に対する見方、考え方があります。
私たちが、学者と呼ばれる人たちから教えてもらいたいのは、この制度を発想した人、作った人のその向こうにはどういう考え方があったのかってことです。生産性とか、経済優先とか、それはどういう人間観に由来するのか、もっとわかりやすく教えてほしい。それが、お年寄りが不納得を納得に変えてでも施設に来ることと共通している価値観かもしれないんですよね。
上野 本当にそのとおり。
高口 現場の私たち介護職だからこそ訴えられるものがあるんじゃないかと思うけど、それが何なのかよくわからないんですよ。現場の私たちが社会的に発言して、それが充実したケアにつながるとは思えないまま、今日まで来ました。私は介護を仕事としてきた者として、誰に何をどう言ったらいいのかを上野さんから教えてもらいたい。
上野 あなたが言った「政策決定者たちの人間に対する見方、考え方」が決定的だと思う。政策決定者たちに大きな影響力を持つ圧力団体は経営者団体とか医師会とかいっぱいあるのに、介護に関しては介護職の団体も利用者の団体もなきにひとしい。
私は23年間、介護の現場を研究してきて、はっきりわかったことがある。それは、年寄りはこの程度でいいんだと、したがって年寄りのお世話をする介護職の処遇もこの程度でいいんだと政策決定者が考えているということです。
高口 なるほど。監視カメラの問題もまったく同じですね。障害者や高齢者は、一方的にカメラで見られてもいい存在なんだっていう価値観。私は、これは真っ当な人間観と思えない。
私がやっている介護塾という講座で強調しているのは、介護職が認知症がある人を何もわからなくなってしまった存在と決めつけることなく、「思いも考えも意思もある人」として出会うということです。







