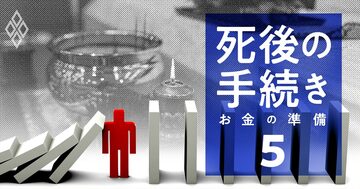人口約40万人の横須賀市では、引き取り手のない無縁遺骨は累計1800柱にのぼる。2002年ごろから増えていったという。
北見さんの分析によると、無縁遺骨が増加した要因は大きく2つあるという。
1つは戦後の核家族化で親族が同じ地域でかたまって住むということが少なくなり、親族は遠くに分散し、ひとり暮らしの世帯が増加。さらに少子高齢化により、家族の支え手が減り、火葬をしてくれる人がなかなか見つからなくなったこと。
もう1つの要因は2002年ごろに普及した携帯電話だという。携帯電話と固定電話の契約数の推移を見ると、携帯電話は1994年ごろから普及しはじめ、2004年頃には固定電話を抜き、今は完全に逆転し、携帯電話しか持たない人が多くなっている。
「引き取り手のない無縁遺骨が増えはじめた時期と携帯電話が普及するタイミングは実は一致していると思いました」と北見さん。
いつでもどこでも電話ができる携帯電話は便利だが、やっかいな代物でもあるという。例えば、ひとり暮らしの高齢者が路上で倒れ、通りがかりの人が救急車を呼び、救急病院に運ばれる。
ところが、その高齢者が持っていた携帯電話にはロックがかかっている。高齢者の身元は所持していた身分証明書でわかったが、連絡を取り合う家族や親しい友人は誰なのかなどは、暗証番号を入れ、携帯のロックを解除しない限りわからない。
電話帳に多くの人の固定電話が載っていた時代であれば、104番にかけ、名前と住所を言えば、すぐに電話番号は判明していた。だが、固定電話を持たず、携帯だけを持つ人が増え、電話帳で連絡先が探せる確率は30分の1くらいに減ったという。
「携帯電話は健康な時は便利ですが、その人が倒れたり、亡くなった時、危険なのです。暗証番号がわからず、ロックされ、携帯が遮断されてしまえば、無用の長物になり、遺骨の引き取り先を探し出すことはかなり難しくなる」と話す。
横須賀市役所は毎年、50人前後の無縁遺骨を預かり、住民票などをたどり、親族の連絡先を探すが、そのうち10件ぐらいは電話番号がわからず、手紙を送って知らせたが、回答はほとんどないという。