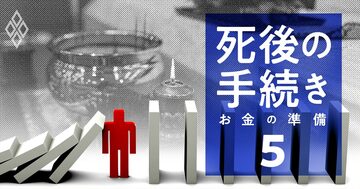写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
現在、全国の自治体が管理・保管する無縁遺骨は約6万柱にのぼる。そのうちの9割は身元が判明していても親族などからの引き取りがないという。無縁遺骨は保管に関する法令さえ存在しない。なぜ、引き取り手が現れないのか、無縁遺骨が増え続ける理由を探った。本稿は、森下香枝『ルポ 無縁遺骨』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。
身元が判明していても無縁納骨堂に
「1人暮らし」が増えると「無縁遺骨」も増加
神奈川県横須賀市の丘の、地形を利用してつくられた貯蔵庫の奥には、無縁者のための納骨堂がある。
進入禁止のロープの先にある入り口のシャッター前に「無縁」「霊」などの文字が彫られた地蔵菩薩が番人のように建っている。手をあわせて中に入ると、洞窟のようにヒンヤリとしていた。真っ暗なので懐中電灯で周囲を照らした。
コンクリートで固められた広い四角い部屋に置かれた簡素なステンレス製の棚にさまざまな骨つぼが所狭しと並んでいる。桐製の骨つぼや菊の刺繍が施されたシルバーの骨箱、紙袋に入ったままのものなどさまざまだ。
江戸時代から港町の浦賀(現・横須賀市)には、村が管理する無縁者のための納骨堂があった。平成に入り横須賀海軍墓地があった馬門山墓地にも、市が新たに合葬墓をつくった。
ここもやがて満杯になったため、2018年に浦賀と馬門山を閉じ、一部を新納骨堂へ移し、残りは供養したうえで残骨灰処分事業者が処分した。
かつては無縁納骨堂に納められるのは行旅死亡人とされる身元不明者がほとんどで、骨つぼなどには番号が振られていたという。
だが、現在は、担当したケースワーカー、預かった年月日、名前などが記された紙が貼られている。身元がわかっていても引き取り手がおらず、「無縁」となっている。
「今では9割以上、身元がわかっている人のお骨がここへやって来るんです」
詳しい場所は書かないという約束で横須賀市の無縁納骨堂を案内してくれた横須賀市終活支援センター福祉専門官の北見万幸さんが教えてくれた。
「ここも一杯になるとどうするのですか?」と問うと、北見さんは持っていた懐中電灯の光で部屋の奥の空洞を照らした。
「この貯蔵庫は広いの。まだまだ保管するスペースはあります」
誰も葬儀をする人がいないときは、墓地埋葬法などを適用し、亡くなった市区町村が埋火葬する義務を負うことが決められている。
市役所のキャビネットや倉庫などで遺骨を数年間、保管し、市の職員が住民票、戸籍などをたどり、親族など遺骨の引き取り先を探すが、拒否されたり、連絡がつかなかったりすると、横須賀市の場合、最終的にここに遺骨が運び込まれる。