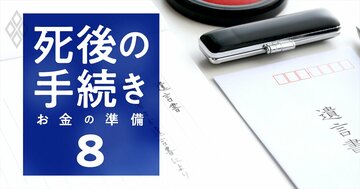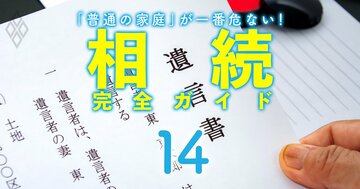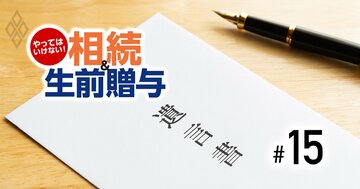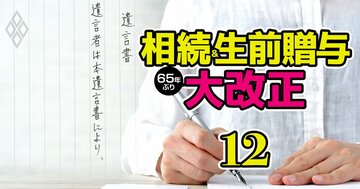パソコンやスマホが高齢者世代にも行きわたっている今、手元のデバイスで遺言書を作り、クラウド上で保管することが可能となるかもしれない。日本は東日本大震災のような大規模な自然災害を多く経験している国であり、紙ではなくクラウド上への保管の整備は急務とも言える。ただし、遺言書のデジタル化には課題も多い。
信頼できる遺言書を
デジタルで作れるのか
遺言書は、遺言者の死によって効力を生ずるため、贈与とは大きく異なる。特に自筆証書遺言は、本当に自身の意思で書いたのか、悪意を持って誰かに書くよう求められたり、死後に改ざんされたりしていないか、慎重に判断する必要がある。そのため、遺言者の真意を担保する意味も込めて、「自筆」で書かなければいけないというルールが設けられてきた。
だが、遺言書がデジタル化することで、筆跡を確認することができなくなる。具体的にどのような形であれば本人の真意を担保できるのか、相続人や第三者によるデジタル遺言の悪用を防げるのか、十分に検討する必要がある。
たとえば、改ざんを防ぐ方法にはブロックチェーン技術の活用が考えられる。法務省は録音や録画の活用、電子署名化も検討している。ただし、こうした新技術による遺言書の作成は、デバイスの操作に悩みやすい高齢者にとって大きな負担となる可能性もあり、第三者の力を借りながら作成せざるを得なくなる可能性も考えられる。その場合、誰にサポートを依頼するのか、も議論をするべきである。
すでにアメリカでは、フロリダ州などでデジタル遺言制度がスタートしている。フロリダでは、遺言書と証人が公証人の前で本人確認書類を提示した上で、遺言書の内容を読む様子が録音・録画されている。この際には、「自らの意思で署名したこと」を宣言している。この方法なら、生前の様子が明確に記録されているため、改ざんも偽造も起きにくい。日本でもこうした方法は検討できるだろう。