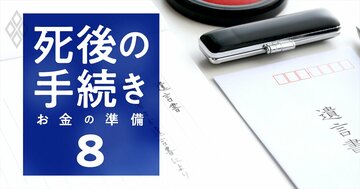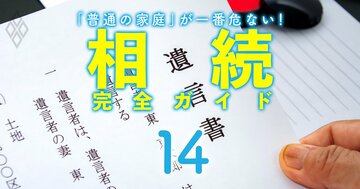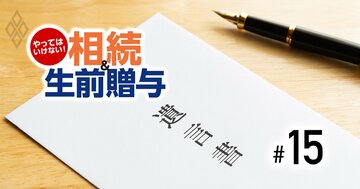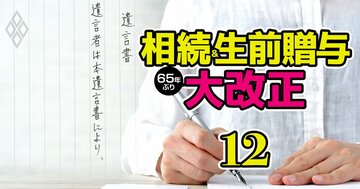高所得者・資産家の遺言書
骨肉の争いを避けて作るコツとは
今後、日本でもデジタル遺言制度が導入される可能性は高いが、技術がどれだけ進化しても、家族に配慮を尽くした遺言書を作らなければ、死後に骨肉の争いが勃発してしまう可能性はある。高所得者・資産家の遺言書は、遺産を巡って家族が分裂してしまうおそれもある。
そういったトラブルをさけるためには、まずは信頼できる専門家に相談することがおすすめだ。家族の分裂を防ぐために、すべての財産を自治体へ寄付する選択もあるが、遺言の無効を巡る争いとなる可能性もある。専門知識を持たないまま、自筆証書遺言を残すことは危険だ。
近年、子どもがいない相続に備えて遺言書を作る動きも高まっている。野崎氏のように自治体への寄付を検討する方はもちろん、ボランティア団体や学校などへの寄付も活発だ。しかし、遺贈にはリスクもある。今回の野崎氏のように、遺留分に配慮の無い寄付は、遺贈先と相続人間で争いとなる可能性も高い。
また、遺贈先によっては「いらない財産」をもらうことになる可能性もある。喜んでもらえるだろうと思って不動産を遺贈しても、遺贈先が受け取らない場合もある。たとえば積極的に遺贈を受けている「国境なき医師団」でも、山野林、農地、地方のリゾートマンション、海外の不動産の遺贈は換価しにくいため、受け取らない方針を示している。円満な相続や遺贈のためには、さまざまな配慮と知識が必要だ。
たとえデジタル遺言によって自筆証書遺言が身近になったとしても、相続税や遺留分対策、遺言執行の対策はもちろんのこと、これまで大切に育ててきた事業の継承などを視野に入れるためには、税理士や弁護士などと連携しながら遺言書を作ることが望ましいだろう。