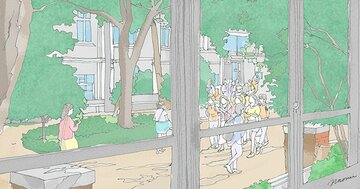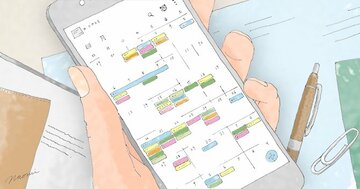「人との関係を大切にしながら自律的に生きる自分」
“いかに生きるか”という問いに向き合うタイミングは、人によって異なる。私の場合、高校時代がそのタイミングだったと思う。中学までは、「将来、どんな仕事をしたいのか?」と問われても、「ネクタイを締めなくてもいい仕事」と答えることが多かったように記憶している。
私が育ったのは典型的な昭和の家庭で、父は会社でバリバリ働き、母は専業主婦をしていた。父は大企業でそれなりの肩書を背負っていた。しかし、それが父にとってたいへんな重荷だったらしく、精神安定剤を常用し、自律神経失調に悩まされていた。滅多にない休みの日にさえ仕事が頭から離れずにうなされている父に対して、母は不満を抱いているようだった。私が中学1年生のとき、父はとうとう脳血栓という病に倒れ、それ以降、言語障害と半身不随のために一切の賃金労働に従事していない。私たち家族の目には、父は病によって仕事の責め苦から解放されたように見えた。
そのような両親の姿を見て、私は、大人になることにさして希望を見出すことなく育った。むしろ、父のようにはなりたくないという思いが強かった。それゆえ、「なりたい自分」や「就きたい仕事」も、「ネクタイを締めなくてもいい仕事」という否定形でしか表現できなかったのだと思う。
転機が訪れたのは高校1年生のときだった。父の退職に際して、父が勤務していた会社が私のアメリカ留学の費用を負担してくれると申し出てくれた。高校生の交換留学がまだ珍しい時代だったこともあり、当時の私には、期待よりも不安の方がはるかに大きく、留学に「行かされる」という気分だった。
結果、私は、1年間、ミネソタ州の小さな村にホームステイして、その村の人たちの生きざまを間近に体験することで、人生観が揺さぶられた。
ホームステイ先の「お父さん」は、小学校で音楽教師をしていた。当時のアメリカの公立学校の教師は、授業が終わったら早々に帰宅し、長期休みの間は学校に行かないのが普通だったようだ。その代わりに薄給だったが、私には、とても「人間らしい」生活をしているように見えた。陽があるうちに帰宅する「お父さん」は、よい人生を歩むために時間をたっぷり使っていた。あるときは、村はずれの朽ちた巨木をチェーンソーで切り倒し、厳しい冬の寒さをしのぐストーブの薪を作っていた。あるときは、自宅の増築や修理のために大工仕事をしていた。あるときは、近所の知り合いに頼まれて家々のペンキ塗りに出かけていた。そして、多くの時間を家族と楽しむことに割いていた。私もバスケットボールやトランプをして遊んでもらったし、アメフトやバスケの試合観戦にもよく連れて行ってもらった。もちろん、「お父さん」は音楽教師としての仕事をおろそかにしていたわけではなかった。「お父さん」の教え子でもあった近所の若者や子どもたちに、「お父さん」はとても慕われていた。
日本の「父」の生きざまとアメリカの「お父さん」の生きざまには、とてつもなく大きな違いがあると私には感じられた。そして、私の中に、“いかに生きるか”という問いが突き付けられ、「なりたい自分」が私の中に生まれた。「なりたい自分」を一言で表現するならば、「人との関係を大切にしながら自律的に生きる自分」ということだった。
いまにして思えば、私の「キャリア」の出発点は、この経験にあったのかもしれない。「人との関係を大切にしながら自律的に生きる自分」というイメージは、その後の私の選択や行動に大きな影響を与える基準であり続けたからだ。