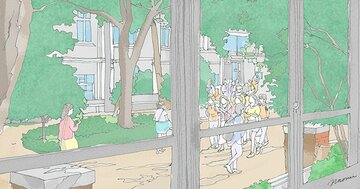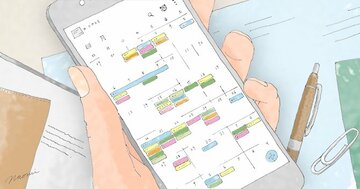自分の思いを相手に伝え、相手の思いに耳を傾ける
前述の「鶴女房」を演じた中学生たちは、自分自身の人生と物語の主人公の人生を行き来しながら、人生において起こり得る物語を読み解いていった。生徒たちは、愛情、欲望、他者との関係について、我が身のこととして考えたのだった。なかでも、若者と鶴女房との思いのズレに焦点を当てて話し合いを進め、夫婦の思いのズレを演じていった。「若者は鶴女房に不自由のない生活をさせたかった。その一方で、鶴女房はぜいたくをしたいとは思っていなかった」――二人がどのような生き方をしたいのかということを話し合い、理解していれば、きっとあのような結末にはならなかった、と。善かれと思って判断を下した結果、他者との思いのズレが徐々に広がっていき、悲劇へと導かれていく。生徒たちは、「鶴女房」を演じることを通して、自分の思いを相手に伝え、相手の思いに耳を傾けることの大切さを実感した。
高校生の私がアメリカに留学したとき、何をするにしても、ホームステイ先の家族から「It’s up to you」と言われた。「君次第だよ」「君が自分で決めなさい」という意味だが、休日の予定、食事の選択、学校での活動の選択など、あらゆる場面で、この言葉を聞いた。「It’s up to you」という短い言い回しに、私は、「君の思いをしっかり表現しなさい。そうしたら、私たちは君の思いの実現に手を貸しますよ」というメッセージが含まれているように感じた。
私は育ってきた生活の中で、「自分がどうしたいかを人に伝える」大切さを感じることは少なかったし、その大切さを知るための教育も受けてこなかった。自分の思いを語ると、周囲に迷惑をかけるような気がしたし、私の考えは大人に察してもらうものだと思っていた。
自分の思いを言葉にして他者に伝えるということは、人生において、とても重要なことだ。それは、会社や社会の期待に添いながら“主体性のないキャリア”を積み重ねるのではなく、自分自身の人生を歩みながら“主体的なキャリア”を積み重ねていくことにつながる。
やがて、さまざまな出会いと選択の末に社会人となった私は、障がい者の学びの支援に関わる仕事に携わることになった。それでもなお、“いかに生きるか”という問いが続いている。「人との関係を大切にしながら自律的に生きる自分」というイメージを持っていながらも、「そのような生き方を選択するのはなぜなのか?」といった、一段深い問いに直面することも多くなった。論語では40歳を「不惑」というが、50歳後半になっても、私は、「天命を知る」どころか、「この生き方でいいのか?」と迷ってばかりいる。
そんな私の貴重な出来事のひとつに、障がい者支援を長く行(おこな)っている起業家との出会いがあった。その人は、障がい者の生活を支える事業所を運営しており、通ってくる障がい者が力をつける作業を大切にし、私に語ってくれた思想は、私の仕事にも大きな影響を及ぼした。そして、あるとき、こんな言葉を発した――「事業所に通ってくる障がいのある人たちには、死ぬ間際に人生を回想して、“いい人生だったなぁ”と思いながら死んでいってもらいたいと思います」
“いかに生きるか”は、死ぬ間際に人生を回想するときの思いを想像することで考えられる――これは、私にとって衝撃的であり、示唆的だった。私自身の生き方に光を与え、他者の人生に関わる私の仕事の力にもなった。
もちろん、人によっては、“いかに生きるか”の根拠を宗教に求める人もいるだろう。尊敬する誰かを基準にして、生き方の確信を持っている人もいるだろう。しかしそれでも、「いい人生を生きる」という価値は普遍的だ。私の場合は、自分自身が“いかに生きるか”を考えるときにも、他者を支えることに挑むときにも、最期に「いい人生だった」と回想できるように、という基準が腑に落ちた。
「いい人生」を歩むために「自分がどう生きたいか」を考え、言葉にして他者に伝える。他者からも力を得て、また、他者の力にもなって、自分なりの生き方を実現していく――「キャリア」はそのような関係の中で立ち現れてくるものだと思う。