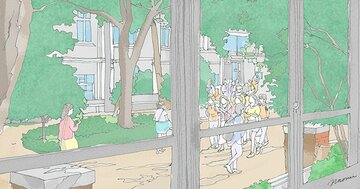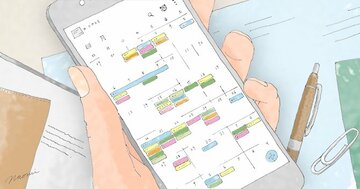「いかに“主体的に”生きるか」を考える経験が大切
時として、私たちは、人生の物語を単純化して捉え、「結婚できたから幸福になれた」とか、「金持ちになったからハッピーエンド」といった結末に一喜一憂しがちである。しかし、実際の人生はそう単純なものではない。「鶴女房」の演劇教育に接して私が感じたのは、「人生の物語には奥行きがあり、その奥行きへの着眼こそが、“いかに生きるか”を考えること」というものだった。
教育現場においても、「キャリア」という言葉がしばしば取り上げられるようになっているが、「キャリア」は、表面的な進路や職業選択、人生設計だけではなく、「いかに生きるか」という視点が大切だと私は思う。いろいろな偶然に左右される状況の中で、「いかに“主体的に”生きるか」を考える経験が、さまざまな選択肢を持つ子どもたちには必要なのだ。だから、生徒たちが、演劇を通して「生きざま」を考え、語り合った「鶴女房」の授業は、キャリア教育としての深みを持った。
「キャリア」について論じるとき、私たちは、他者が評価する役職や肩書を獲得することに焦点を当てがちだが、それは表面的な「キャリア」に過ぎない。どんなに立派な役職や肩書を得ても、与えられた状況の中で自分が納得できる生を営む必要がある。「キャリア」はその結果として現れてくるものに過ぎない。つまり、「キャリア」は、自分自身が“いかに生きるか”を深く考えた経験に裏付けられるものなのだ。